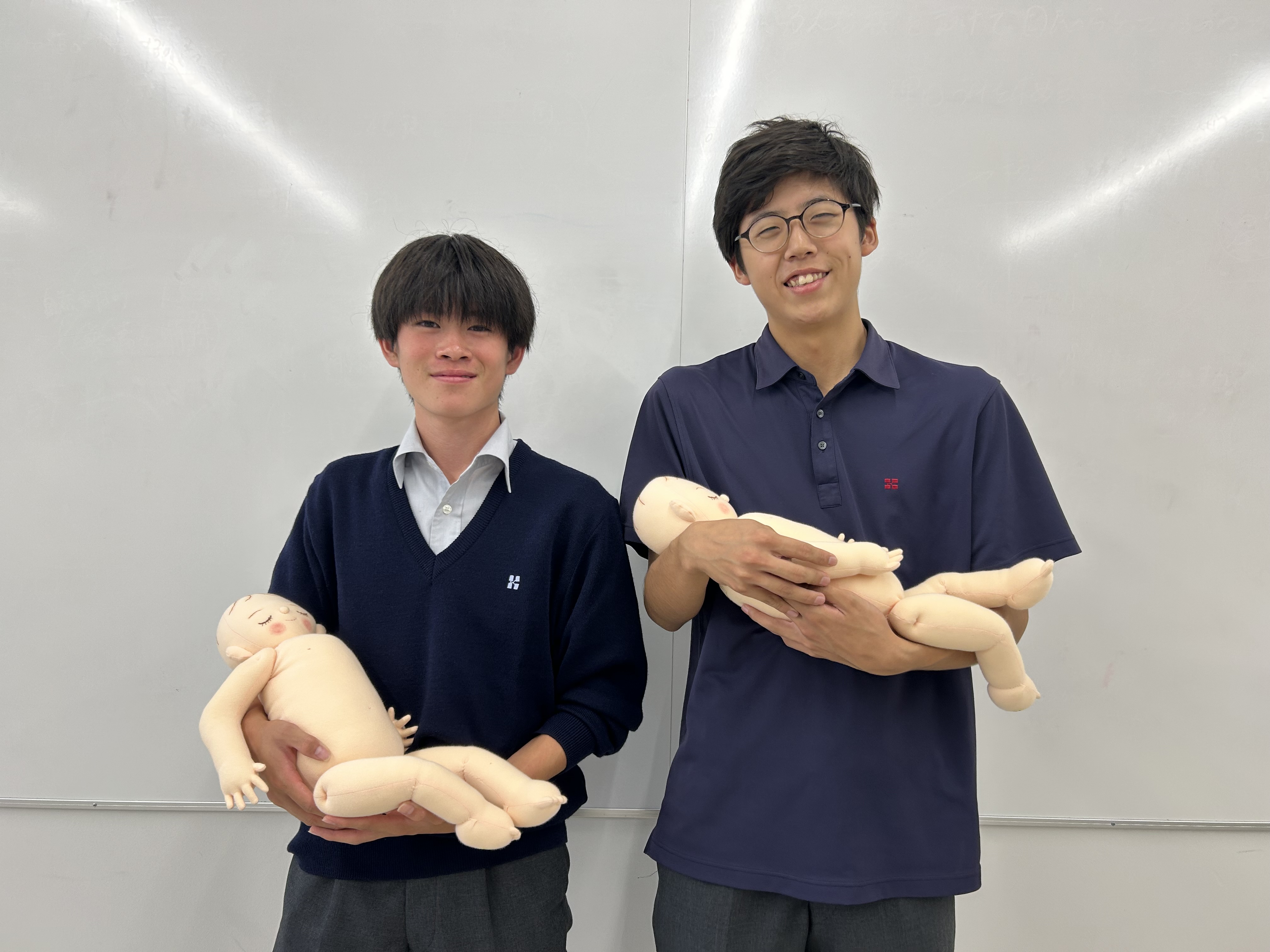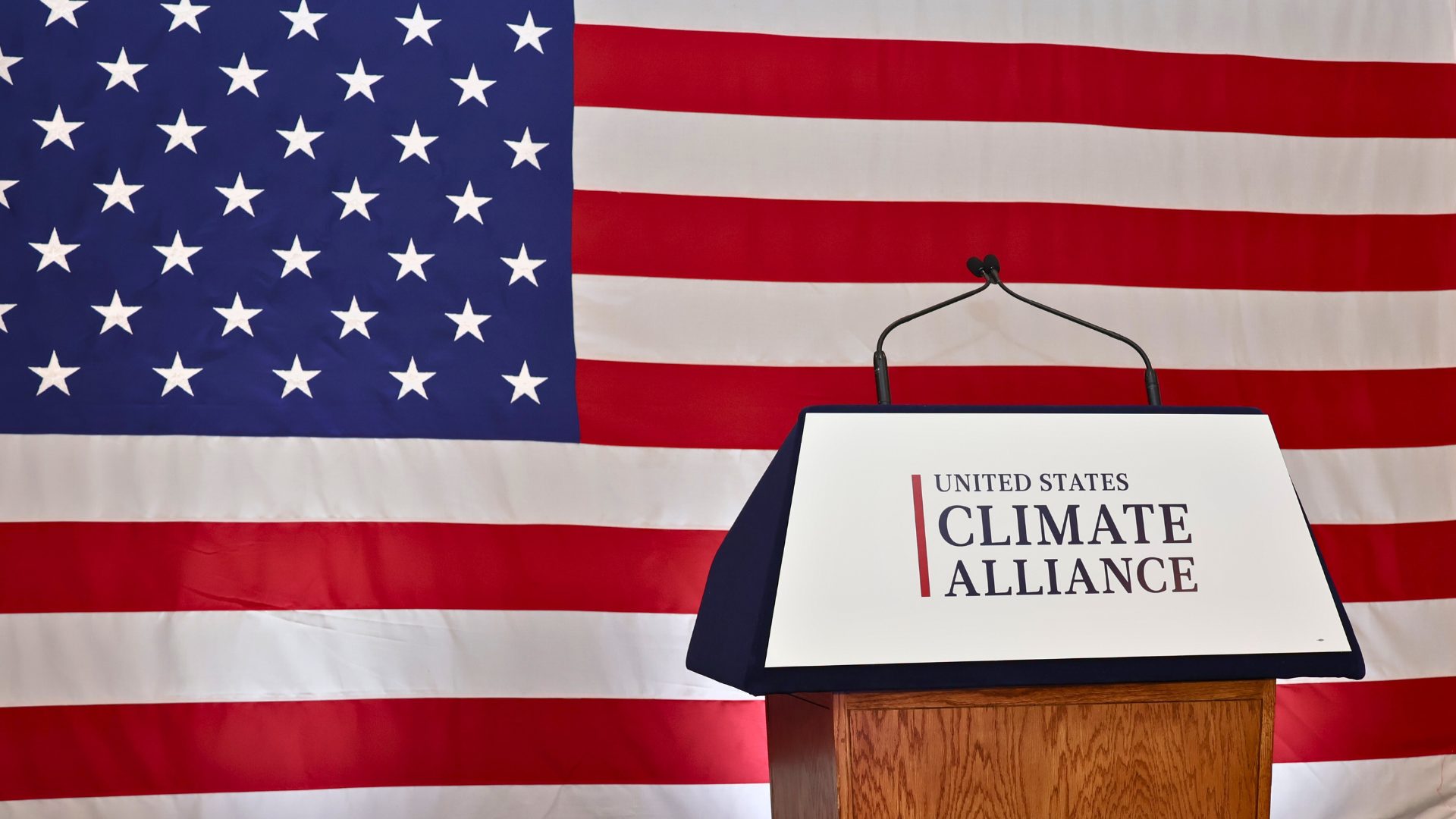「名古屋議定書」の採択から1年が経った。生物多様性条約の締約国の中には、議定書発効に向けて法整備を進めている国も多い。医薬品、化粧品、食品、飲料メーカーをはじめ、海外の動植物や微生物に依存している企業にとっては、新たなリスクといえる。
同議定書により「遺伝子資源へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分(略称ABS)」の国際制度が定められた。事前の同意なく他国の生物を使って研究するだけでルール違反となる。
遺伝子資源には、土壌に含まれる微生物など顕微鏡サイズの生物も含まれる。近年は多様な企業がバイオ研究を進めており、自覚もないまま他国の法に抵触してしまうケースも考えられる。
そこで、レスポンスアビリティ(東京都目黒区)は有料サービス「遺伝子資源の利用に関するリスクチェック」を開始した。企業の研究開発や製造過程を簡便に確認して、リスクの有無を見極める。重大なリスクがあれば専門家への紹介も行う。
足立直樹代表は「不正利用が摘発されて研究成果が突然無効になった場合のダメージは計り知れない。リスク調査は持続可能な経営につながる」とチェックの意義を語る。
足立氏は熱帯雨林などを研究していた元生態学者。同社は生物学や生態学を修めたコンサルタントをそろえて、企業の相談を受け付けている。(オルタナ編集部=瀬戸内千代)













-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)