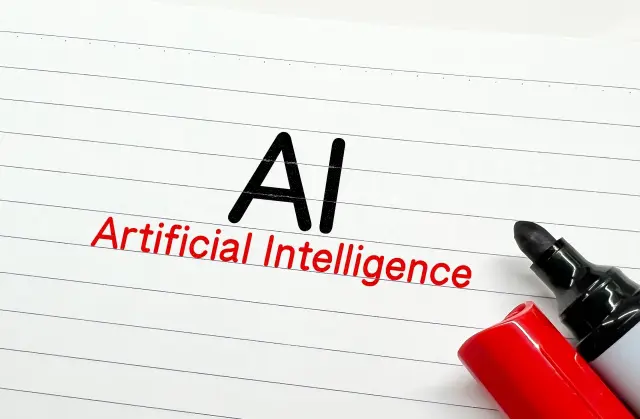記事のポイント
- 長野県諏訪地域の伝統保存食である寒天の製造現場を取材した
- 天然寒天の製造には、自然環境の力をとことん生かしている
- 衰退の危機にあり、食べることで将来につないでいくことが大切だ
■小林光のエコめがね(37)■
前回に続いて、今回も、藻の話をしよう。1月半ば、長野県寒天水産加工業協同組合の組合長、五味嘉江さんが営む寒天製造現場を訪問し、伝統産業を継ぐことで見出した価値について語っていただいた。
昨年6月から長野日報紙上で「長野環境人士」という対談を始めた。個人の活動を深堀りする「自然にやさしく、暮らしを楽しく」シリーズと、企業の経営を論ずる「自然を取り入れ、企業価値を高める」シリーズがある。今回は前者の取材の一環で、寒天製造現場を訪れた。
寒天は、おそらく平安時代ごろに中国からお寺の食料として伝わり、以来、京都や奈良で製造されてきた伝統食材、伝統保存食である。修験道の断食修行中の僧侶に許された限られた食料の一つでもあったという。
江戸時代に、諏訪の行商人の小林粂左衛門さんという方が製造方法を京で学び、地元に持ち帰って伝え、その後、この地方の気候がことのほか寒天製造に向いていたので、当地の重要な産業となった。
最も栄えた頃には、240事業所を数えたというが、今や、他の健康食材に押され、わずか10軒くらいが寒天製造を続けるだけになってしまったという。ちなみに、全国市場占有率はほぼ100%で、この地方のみで孤塁を守っている。
論者としては、寒天は知っていたが、その製造現場を見るのは初めてだった。そして、結果、なるほど、「寒天」とは言い得て妙な、環境ビジネスだと感心した。
テングサなどの海藻は半分乾燥させ、緊結された荷姿で入荷するが、その海藻類を洗い、本来の姿に戻すのに大量の真水を使う。この最初の工程で、諏訪地域は恵まれている。八ヶ岳の清冽で安定した伏流水が豊富に得られる。
次の工程は、海藻類の「蒸し煮」で、そう多量のエネルギーを使う訳ではないが、昔は、薪を使ったそうだ。今はA重油を使っていて、小さな燃料タンクがあった。敢えて蒸し煮と書いたのは、沸騰した釜の火を止めて8時間程度蒸したときが、寒天成分が一番抽出できるそうで、煮沸ではないのである。
そうした蒸し時間で濾し取った寒天原料と、残りの海藻とに分かれ、残りの部分は天かすと呼ばれる。昔は肥料として珍重され有効利用された由である。そして、寒天原料は固まると、コンニャクと瓜二つの風情になる。
そこからが、地域の再生可能エネルギーの出番だ。このコンニャクのような生寒天を、天日干しするのである。まずは、夜間には、北面に向けて放射冷熱を使い、寒天から沁み出た水分を凍らせる。朝が来ると、凍ったまま陽が当たる南に向けて、水分を蒸発させ、寒天本体を乾いた風で乾燥させる。この繰り返しで、あの乾燥しきった棒状の寒天ができる。

写真1は、パネルの上に並べられ、南天に向けて太陽の光を浴びて、水分を飛ばしている寒天軍団である。右手奥に重なって見えるのは、展開前の半乾きの寒天で、雨や雪、そして過剰な暑さなどを避ける場合は、このようにして冷えた状態を保ち、カビなどが発生するのを防ぐ。確かに寒天は、菌などの培養地に使うので、カビが生えたら始末に悪かろう。

この景色を見て、論者は、現代の太陽光発電所の光景(写真2)に似ていることに気付いた。しかし、寒天製造は、PVパネルが並ぶ発電所での発電に比べ、ずっと巧妙なものである。
まず、底地は、春からは水田、そして、秋にお米が収穫された後、残りの稲わらは、初冬に寒天干し場の地面に敷かれる。これが寒天が汚れるのを防ぐグラウンドカバーの役割を果たす。したがって、この土地は、廃棄物まで活かす二毛作なのである。その上、寒天の製造には、太陽光や熱だけでなく、夜間の冷熱、放射冷却も使われる。ここもエネルギーの二毛作である。
見た目は似ているが、自然環境の力をとことん使い尽くしているのが、寒天製造の仕組みであった。
この寒天製造が、今三重苦にあえいでいる。既に述べた、他の健康食品との競争による消費者離れがあるほか、テングサなどの原料の海藻が海の温暖化や、海女さんなど収穫の担い手不足から、生産量は減り、値段も高騰している。そして、この八ヶ岳山麓の寒天干し場も、温暖化によって、寒天の水分がきれいに凍らず、乾燥の工程が大変に手間のかかるものになっていると言う。
寒天という、八ヶ岳山麓の自然の化身と言うべきものを、その背景にある物語に思いを馳せつつ、味わっていただきたい。食べることで、素晴らしい自然と人とのこんな興味の尽きない物語を将来につなぐことができる。









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)