記事のポイント
- 2024年の通常国会で生物多様性増進法が成立した
- 生物多様性の増進のために民間の力を活用しよう、という狙いだ
- どうすれば、この法律を役立てていくことができるのか
■小林光のエコめがね(42)■
2024年の通常国会で「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(生物多様性増進法)が成立した。いろいろな内容を含んでいるが、要すれば、民間の力を、自然保護へ、もっと正確に言えば生物多様性の増進のために活用しよう、という狙いの政策である。
この「エコめがね」では、民間の力、特にビジネスを通じて自然環境保全を進ませていく動きを報告し、その一層の活発化を訴えてきたところなので、今回の、新政策にも大なる関心を払っている。そこで、今回は、この法律を役立てていくためのポイントを考察してみた。
■ 民力の活用にはすでに歴史がある
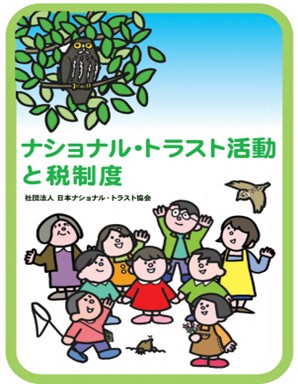
そもそも自然の保全は、各種の公益の中でも、私益からは相当に離れた位置にある。私たちが毎日吸う空気の健全さ、毎日飲む水の安全などは、私益と密接な関係にある価値であって、それを守ることにほとんどの人は違和感を覚えないだろう。
けれども、どこか遠い地方にある希少な植物、鳥や昆虫、きれいな景色を守ることにどれほどの価値があると言うのだろう。
その価値を測定するためには特別な手法が用いられたりするし、価値自体も、私人が直接享受できる価値としてではなく、社会のポートフォリオの中にそうしたオプションを残しておく価値として理解がされることもあるほどである。
こうしたことから、自然保護は、政府の仕事と考えられ、長い間、公的な規制の結果として実現されてきた。例えば、国立公園の指定と開発規制などである。
私自身の経験から見ると、最初の風穴が開いたのが、ナショナルトラストに対する税制支援であった。
ナショナルトラスト活動とは、イギリスの活動に範を取ったもので、自然の豊かな土地を民間団体が買い取って、自ら保全をする活動である。
日本では、1985年、こうした活動に対する寄付金を所得から控除すること、そして、このような善意の団体が負担しなければならなくなる不動産取得税や固定資産税などを減免するなど、税制上の特例措置を設けた。こうすることで、自然保護活動を支援する政策が始まった。
当時、論者は、環境庁の官房総務課次席補佐として、国会対策、税制改正要望を含む法令審査やその成立支援を担当していた。今でも強く記憶にあることは、ナショナルトラスト支援税制を認めてもらうに際して、税制所管当局に向けて、「役所だけでは国中の自然保護はできない。他方、民間だって自然を保護できる」といった言い方で、哲学のいわば180度転向を宣言したことである。
大それたことだと思いながら、そんな文章を書いたことを今でも覚えている。このような発想の転換が、今考えると、今日当たり前になってきたネイチャーポジティブな経営やTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)などへの国内の道が開けていく第一歩だったのだろうと思う。

その後、民間の活動を自然環境保全に組み込む政策は、折に触れ、進化していった。自分として、一段ステップが上がった政策が登場した、と感じたのは、自然再生推進法(2002年成立、議員立法)だ。
この法律は、過去に失われた自然環境を官民が力を合わせて再生することを目的に、民間の活動を含んだ計画を協議会で作り、その計画の実施について、民間団体も、公的機関と連携して役割を果たすことができるといった内容である。
当時に戻ろう。自分は、この法律の制定過程には関わっていなかったが、この仕組みはもっと広い対象に適用しないともったいないな、と直感した。
そこで、環境保全活動・環境教育推進法(03年制定、議員立法)という、もっと広い土俵の法律を、当時の自民党環境部会環境教育小委員長の鈴木恒夫議員のリーダーシップの下で制定するお手伝いをさせていただいた。その中で、環境教育のために民間が土地を保全し一般に公開するケースに関して同様のスキームを持ち込んでいただいた。
簡単に歴史を振り返ってみたが、言いたいことは、自然保護に民間の力を呼び込むことには既に歴史があり、今回の法律はその流れを受け継ぎ、発展させるものである、ということである。
■ 民力活用には課題がある
では、民間が自然保護をする場合の弱点は何だろうか。
まずもって、保護の内容が心配になる。民間に特別の努力をすることを、罰則を持って課することは到底できない。したがって、民間の善意に期待できる範囲に保護の内容も自ずと限られる。そこで、「なんちゃっての保護」で終わることのないような技術的、制度的な工夫が必要になる。
法令担当者のいわば業界用語であるが、「マッチポンプ規制」という概念があり、こうした時に登場する。名称独占とか何らかの特権を与える代わりに、品質保証のルールを定め、その違反に関して罰則を構える、といったタイプの規制を、自ら揶揄して述べたものだ。
民間の場合は、土地所有権が譲渡などされた場合に、保護がそれこそ反故にされる心配もある。そこで、約束事が承継されるものであることを法律で規定することも一つの工夫になる。都市計画での地区計画などで既に使われてきた手法である。
こうした制度的な工夫で、民間が高度な保護活動を行うことを支え、促すことはできるが、科学的に見た場合の適正な保護の内容は、どうやって担保することができるのだろうか。まして、相手は生物多様性といった、かなり高度の概念である。これをどうして実現できるのだろうか。これこそが、民間が自然を扱うときに論者が一番心配してしまう事項である。
一例を挙げよう。寄り道になるが、本欄でも取り上げたが、神宮外苑の再開発である。
(この続きは)
■ 神宮外苑は生物多様性増進の努力がそもそも足りない
■ 清水建設の「再生の杜ビオトープ」の経験から言えること








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























