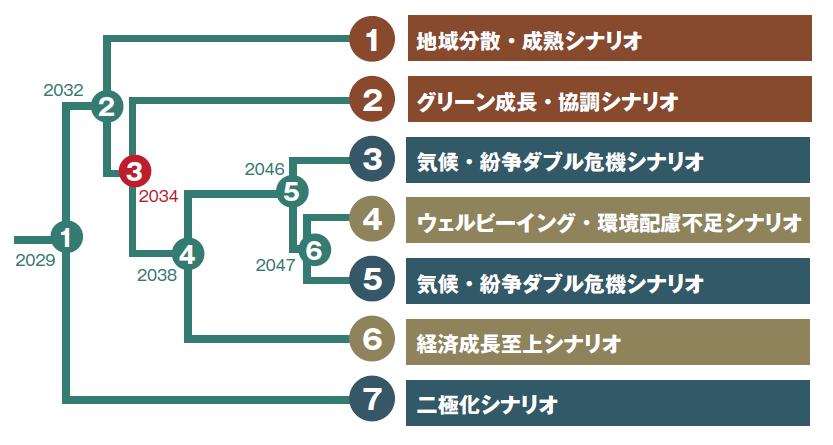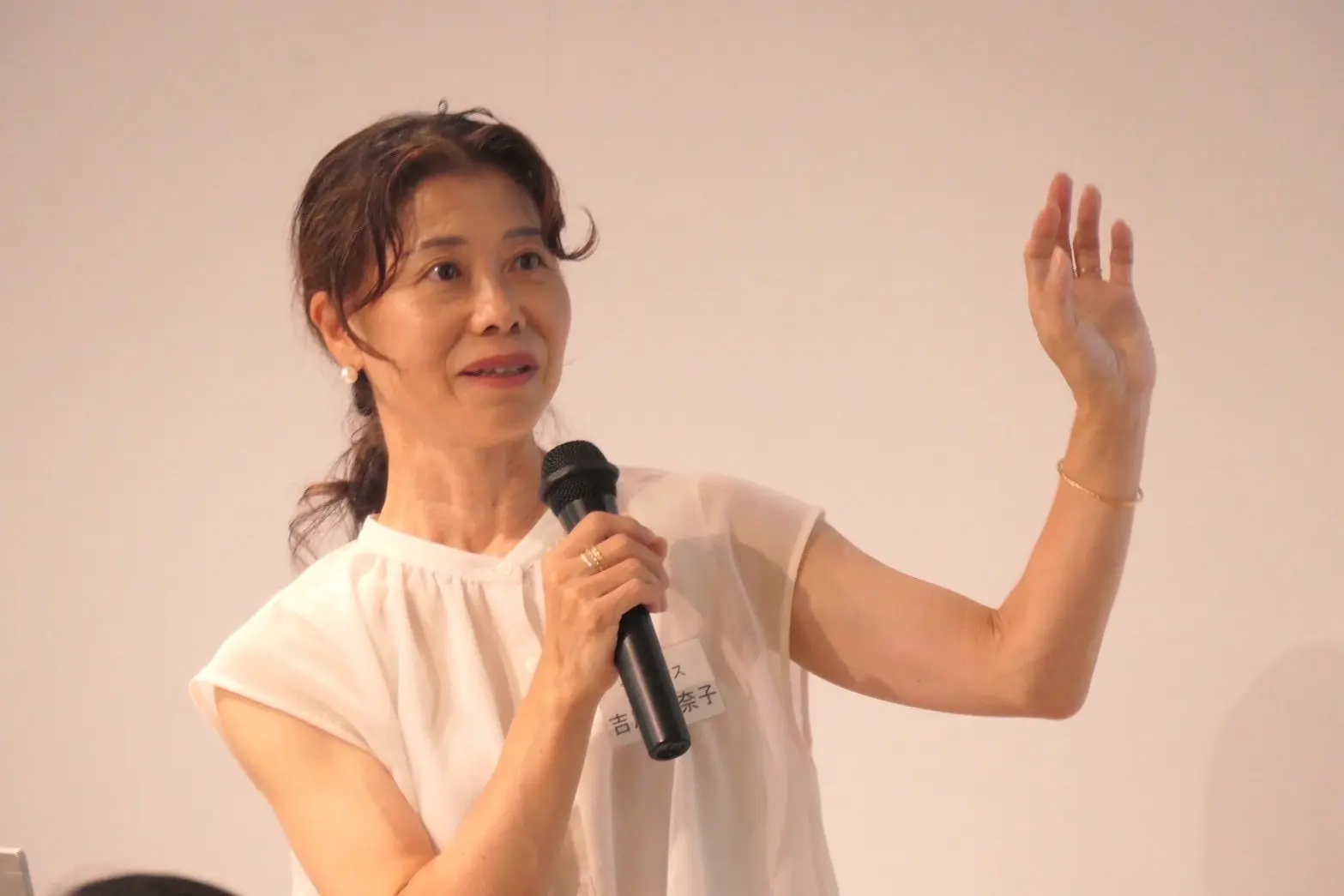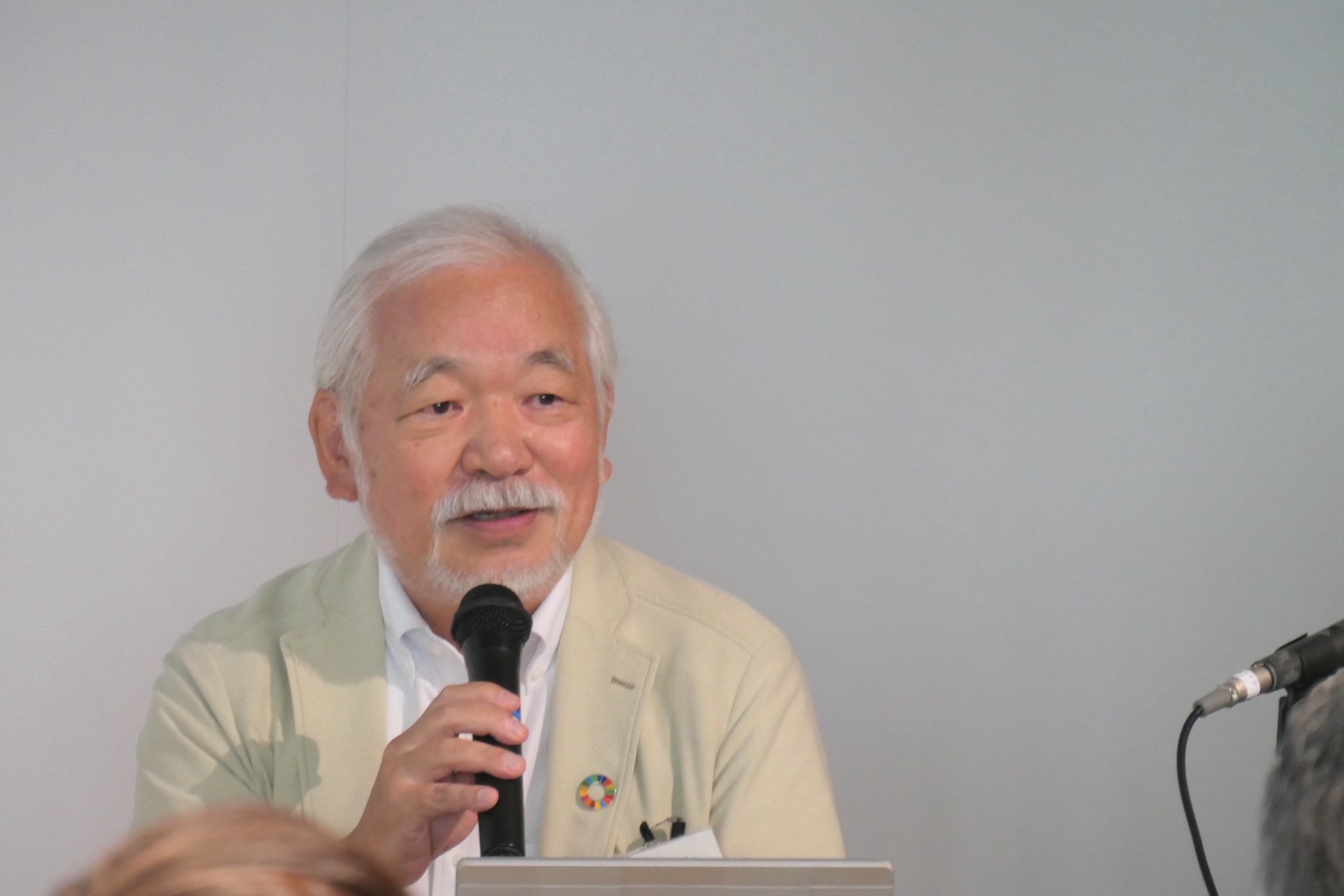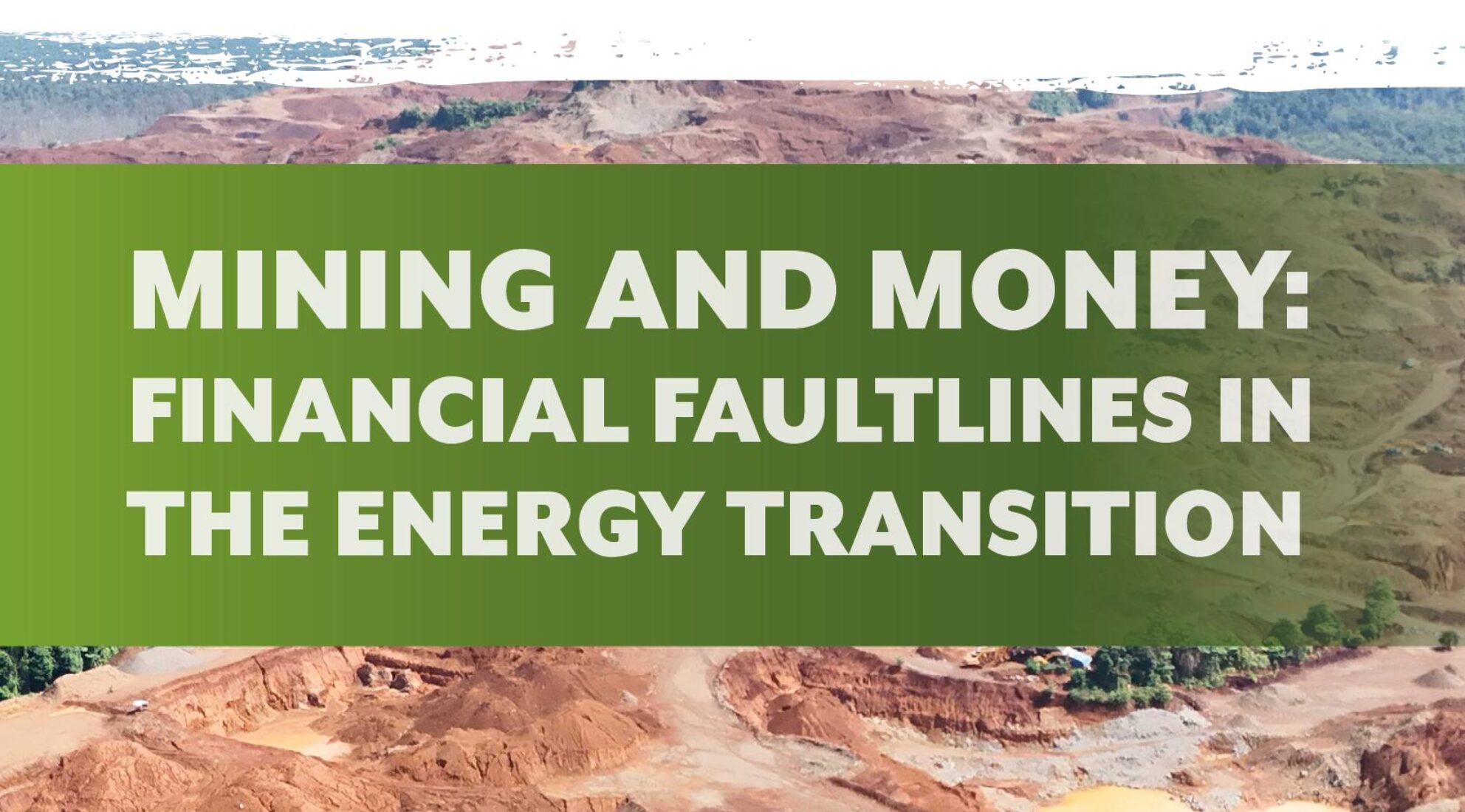記事のポイント
- ゼネコンが建築ライフサイクルコストで「ゼロカーボン」を競っている
- ZEBは運用中に着目しており、新築非住宅では3割弱が取得した
- 大手ゼネコンではエンボディードカーボンに着目しはじめている
建設業界の脱炭素の流れとして注目される、建築物のライフサイクルでのCO2排出量削減だ。建築物の脱炭素化に向けた施策で有名な「ZEB」は運用中のオペレーショナルカーボンに着目した認証だ。新築非住宅では3割弱が取得する。一方、運用時だけでなく建設時や解体時も含めたエンボディードカーボンにも着目した建築ライフサイクルコストをどう減らすかが課題となっている。(オルタナ編集部=萩原 哲郎)
これまでの非住宅建築物の脱炭素の取り組みは主に運用中のCO2排出量(オペレーショナルカーボン)を減らす省エネの取り組みが中心となってきた。一方で、建築物のライフサイクルのなかでCO2排出量は運用段階49%に対して、建設や修繕などの維持管理・解体などの「エンボディードカーボン」と呼ばれる部分の排出量が51%にのぼる。
こうしたなか、業界内では2022年に三井不動産と日建設計が「建設時GHG排出量算出マニュアル」を策定。24年10月には国交省が、建築物のライフサイクルカーボン算定ツール「JーCAT」を公開した。
■新築物件の3割がZEBに
そもそも、ZEBとはどういった認証か。ZEBは2016年4月から始まった認証で、従来の建物で必要なエネルギーに対して、省エネ+創エネで0%以下となる物件を「ZEB」物件として認証している。
「ZEB」以外にも、省エネと創エネで25%以下まで削減する「Nealy ZEB」、省エネで50%以下まで削減する「ZEB Ready」、延べ面積が1万㎡以上の建物を対象とした「ZEB Oriented」がある。
第1号物件は清水建設が設計施工した木造建築「生長の家 茨城県教化部新会館」だ。普及が進んでいき、24年3月末時点で民間の非住宅建築物のZEB普及率は面積で2%超。23年度の新築物件では27%にのぼる。
ZEBが主な対象とするのは運用中のCO2排出量(オペレーショナルカーボン)となるが、エンボディードカーボン削減に取り組む重要性が増している。
EUは24年4月にEU建築物エネルギー指令を改正し、28年から1000㎡超の新築建築物についてライフサイクルGWP(建築物のライフサイクルを50年として、その期間に排出する温室効果ガスを二酸化炭素に換算したもの)の算定・開示を義務付ける。30年には全ての新築建築物に規制を広げる。
日本でも国交省が算定ツールを公開したり、民間のツール開発が相次いでいるが、現状は任意の取り組みに期待しているもようだ。
■ゼネコン各社「ゼロカーボン」競う、ZEB超えも
大手ゼネコンは先行して建築物の脱炭素に取り組んでいる。
大成建設は22年に法政大学の川久保俊教授と「T-ZCB」を開発した。これは建築初期の計画段階で調達から施工・運用・修繕・解体までのライフサイクルでのCO2排出量と削減効果を可視化する。
削減効果は調達フェーズ・施工フェーズ・運用フェーズで評価し、たとえば調達では鉄骨使用量や杭の削減、施工ではEV重機の採用、運用では自然換気・自然採光などだ。
運用・修繕・解体の段階では太陽光発電などの創エネで運用段階のカーボンマイナスを目指す。これにより調達・施工段階でのCO2排出量を削減していき、竣工から60年で累積排出量をゼロからマイナスにする。従来建築物に比べて、50%削減でZCB-Ready(ZEBと同等)、75%削減でNearly-ZCB、100%削減でNet-ZCBとなる。
このT-ZCBを活用して埼玉県幸手市内に「大成建設グループ次世代技術研究管理棟」を建設しており、ゼロカーボン達成をめざしている。
竹中工務店は「ライフサイクルカーボンゼロビル」として、資材製造時から、建設工事、建物利用時、解体工事・廃棄処理も含めた建物のライフサイクル全般におけるCO₂排出ゼロをめざす。
同社の特徴は、解体時に出た廃棄物のリサイクルにも目を向けているところにありそうだ。エンボディードカーボンにはリサイクルは含まないが、竹中工務店の「ライフサイクルカーボンゼロビル」では既存タイルの再利用や、解体した際に分別が容易になる易分解解体などにも取り組む。
鹿島建設や清水建設でもツールを利用して、エンボディードカーボン削減に取り組む。鹿島建設では25年10月竣工のビルで新築から解体までの工事によるCO2排出量を基本設計から実施設計で35%削減した。
今後はエンボディードカーボンとオペレーショナルカーボンの双方を減らしていく取り組みが必要となる。ZEB比率もさらに高めていく必要があり、清水建設は25年度の目標として受注する設計業務のうちZEB割合を50%以上にすると掲げている。



_page-0001.jpg)







-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)