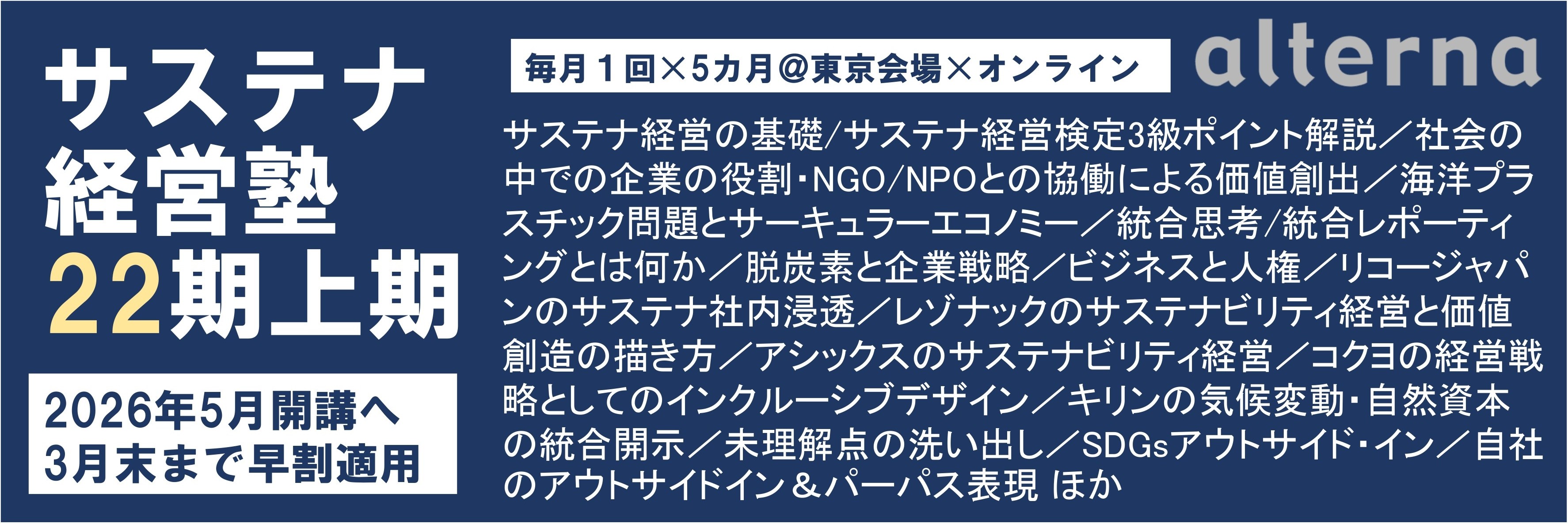記事のポイント
- 日本農福連携協会は、農福連携の新たな可能性を探るスタディツアーを実施
- 農福連携は、農業と福祉分野の課題を解決する取り組みだ
- 企業が積極的に参画することで、「農福連携」のさらなる発展が期待される
一般社団法人日本農福連携協会(東京・千代田)は2025年2月、「農福連携」の新たな可能性を探るスタディツアーを実施した。農福連携とは、農業の現場で障がい者などが就労して活躍することで、生きがいを得るとともに、農業経営の発展に寄与する取り組みだ。ツアーには、サステナビリティやDEI(多様性・公正性・包括性)を推進する企業の担当者など約30人が参加した。
■「農福連携を始めるのに、心配することはなかった」
肌寒い海風が吹く2025年2月、千葉県南東部・いすみ市の菜花畑は、一面を緑で覆われていた。かごを背負った「菜花ガールズ」たちが、菜花を一つひとつ収穫していく。それを受け取った社会福祉法人土穂会「ピア宮敷」(千葉県いすみ市)の利用者は、サイズを確認しながら丁寧に袋に詰め込む。

ピア宮敷は、知的障がい者を中心に、生活介護事業、就労支援事業、グループホーム運営、相談事業など、多岐にわたる事業を運営する福祉事業所だ。人手不足の地元農家から相談を受け、2019年に菜花畑を引き継いだ。そこから「農福連携」の取り組みが始まった。
菜花畑では、地元のベテラン女性チーム「菜花ガールズ」が主に収穫を担い、ピア宮敷の利用者らが袋詰めを行う。出荷するには、菜花を15~18センチメートルにそろえる必要がある。初めは障がい者も、規格に合わせてうまく折れず、とまどっていたという。
ピア宮敷のスタッフが、どう説明すれば良いか思案していたところ、収穫していた女性がふいに枝を拾ってモノサシにした。障がい者にも理解しやすく、スムーズに収穫作業が進んだ。
ピア宮敷で地域支援を担当する内野美佐さんは、「農福連携を始めるにあたって、心配することはなかったのだと気付いた」と振り返る。
徐々に生産のノウハウが蓄積し、2023年には1.3ヘクタールで13.6トンもの菜花を出荷するに至った。2019年当初の生産量は6.6トンで、5年経たずに倍増した。

■7000の取組主体が農福連携に参加、5年で75%増
「おいしい」――。店内に、天ぷらを頬張る音が響く。「農福連携ツアー」の参加者たちは、菜花の天ぷらに思わず舌鼓を打った。ピア宮敷の菜花畑で採れたものだ。
ピア宮敷は2009年、いすみ市内にうどん屋「どんちゃん」(千葉県)をオープンした。障がい者の就労支援を主目的として始めたが、コシのある麺やコクのあるスープが人気で、15年以上にわたり地元で愛される店になった。

ピア宮敷が実践する「農福連携」は、障がいがある人が農業の現場で活躍することで、自信や生きがいを得るとともに、農業経営の発展に寄与する取り組みだ。障がい者以外にも、生活困窮者やひきこもりの人、刑務所出所者など、多様な人々が参画する。
農林水産省は2024年から、11月29日を「ノウフクの日」として定め、「農福連携」の推進に力を入れる。
農福連携に取り組む主体は、2019年時点で約4000だったが、2024年にはおよそ7000まで増えた。農林水産省は、2030年度までに1万2000に増やす目標を掲げる。
これからさらに「農福連携」を推進するうえで、大きな役割を果たすのが企業だ。スタディツアーでは、「農福連携」の現場を視察し、参加者が課題と可能性を探った。
■作業の細分化で、障がい者が「できる作業」増やす
「作業を細分化することで、障がいのある人もできることが増える。得意、不得意を見極めて、作業内容を約20種まで分けたことがピア宮敷の特徴だ」
こう話すのは、ピア宮第1工房の伊東孝浩・サービス管理責任者だ。流れ作業をデザインし、障がい者それぞれの特性、能力を見て仕事を振り分ける。こうした工夫を重ねることで、企業と連携できることが増えたという。
例えば、地元企業であるチーズ工房「千」(千葉県大多喜町)や、mitosaya薬草園蒸留所(大多喜町)などと連携し、ドレッシングやソース作りなども手がける。びんづめやシール張りなどを障がい者が担当する。カラースプーンの袋詰めでも、並べるだけ、入れるだけなど作業の細分化を徹底する。
千葉県大多喜町で育てたライ麦をストローに加工する作業では、汚れをとる、規定の長さに切る、太さを検品するーーと工程を細分化することで、障がい者一人ひとりができる作業を増やした。
ストローの長さを揃えるのが難しいという課題もあったが、工具を使うなど工夫して解決した。ストローは、都内の人気ジャズクラブや各地のカフェなどで利用される。

■「農福連携」で企業のDEIを推進する
ツアーに参加した企業からは、「農福連携」に取り組むうえで、本業との関連を考えなければならないとの意見も出た。法定雇用率の達成ありきの「農福連携」ではなく、より持続的な連携を模索すべきとの考えだ。
企業が「農福連携」に参加することで、DEIへの理解促進やメンタルヘルスの向上、イノベーション創出を期待する声もある。多様な価値観を受け入れることで、社員のウェルビーイングを高め、企業の持続的な成長を狙う。
ピア宮敷の内野さんは、「農福連携のこれからを考えるとき、キーワードになるのは『ユニバーサル農園』。農産物を作るだけではなく、誰もが輝けるように『人』も育てていきたい。働きづらさを感じている人たちと、農福連携に取り組んでいきたい」と話した。
(PR)日本農福連携協会