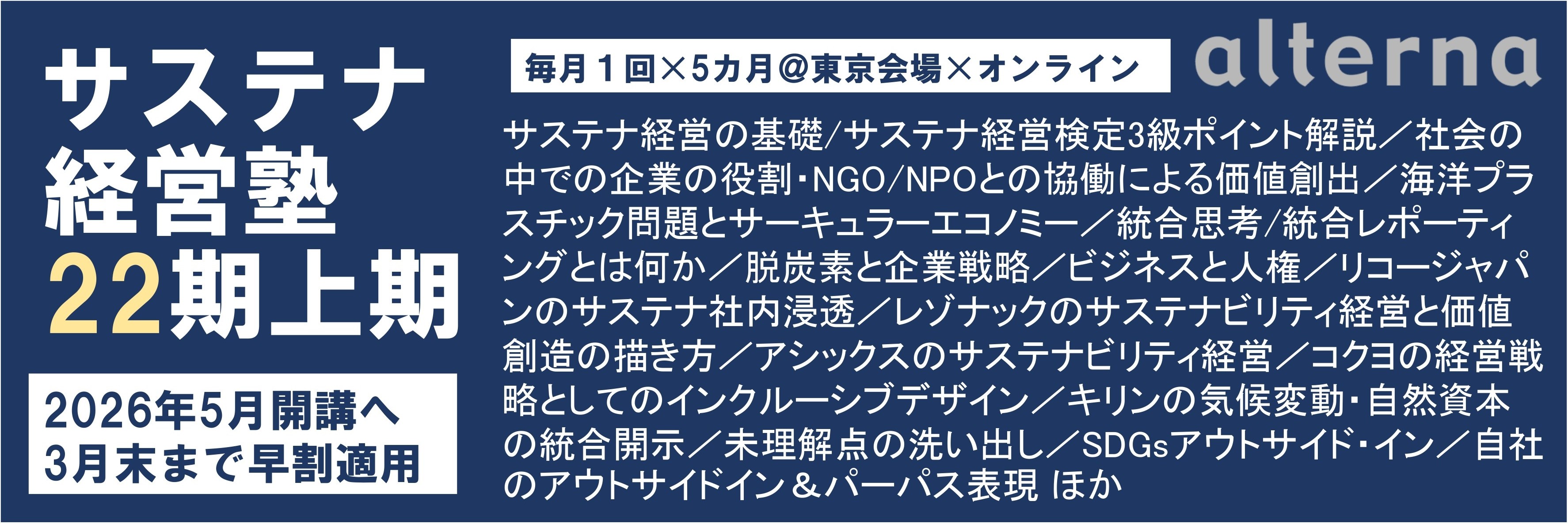記事のポイント
- 米国でDEI(多様性・公正性・包摂性)に対する圧力が強まっている
- その背景には、「DEIが行き過ぎている」との批判がある
- ジェンダー・ギャップ指数でG7最下位の日本で、企業は何をすべきか
連載:企業と人権、その先へ(15)
米国でDEI(多様性・公正性・包摂性)に対する圧力が強まっている。その背景には、「DEIが行き過ぎている」との批判がある。一方、日本は依然としてジェンダー・ギャップ指数でG7最下位にとどまっている。日本企業は、いま何をすべきか。「ビジネスと人権」の専門家である佐藤暁子・弁護士に寄稿してもらった。
先日、世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数で、日本は118位と、今年もG7で最下位となった。この指標だけで全てが反映されていないとしても、日本のジェンダー施策が遅れていることに疑いの余地はない。
そんな中、逆風も吹いている。特に米国の現状を見ると、企業の中にはDEI(多様性・公正性・包摂性)の取り組みを推進すべきか迷うところもあるかもしれない。この背景には、「DEIが行き過ぎている」という意見が存在する。
例えば「白人」「男性」「大学卒」といった、自覚がなくともマジョリティとして特権となる社会的属性を持つ人々が、自分の機会を奪われていると感じていることを指す。これは、マイノリティが直面する機会の不平等を是正し、衡平を実現するために講じられてきた積極的な是正措置への反発と言える。
だが、118位にという数字に表れているように、日本はそもそも、そのような議論が起きる土俵にすら立っていない状況だ。
厚労省による令和5年度「雇用均等基本調査結果」によれば、企業規模10人以上の企業において、課長相当職以上(役員含む)で女性が占める割合はわずか12.7%、配偶者が出産した男性のうち育児休業を開始した人の割合も30.1%にとどまる。さらに、男女賃金格差は女性が男性の75.8%と過去最高に縮まったものも、依然として明確なギャップが存在する。
エンタメ業界での性被害の深刻さが明らかになる一方、その他の業界でもセクシャル・ハラスメント(性加害)の事案は後をたたない。昨年、国連ビジネスと人権作業部会が訪日最終報告書で指摘した通り、「リーダーシップと意思決定における性別の多様性を促進する必要性」は、社会全体で推し進めるべき重要な課題だ。
また、LGBTQI+に対する差別や偏見の根絶、障害者雇用促進法が義務付ける合理的配慮の浸透など、多様性を保障するための政策課題も山積している。諸外国にあるような、包括的に差別を禁止する法律や国から独立して人権問題の調査や政策提言を担う国内人権機関が存在しないなど、政策の実効性を担保するシステムも不十分だ。
このように、DEIの浸透までまだ長い道のりにある日本社会は、その歩みを進めこそすれ遅らせる理由などあるはずがない。むしろ、一部でバックラッシュが起きているこの間に確実に進めることが、企業のレジリエンスの強化につながる。
人権が時の権力者によって歪められ、恣意的に政策が実施されることは残念ながら新しいことではない。だらこそ、不確実な国際情勢の中では、表面的な言葉だけではなく、自社がコミットした「国際人権」の実現に向けて具体的なアクションを取る必要がある。今こそ、企業の真意が問われている。