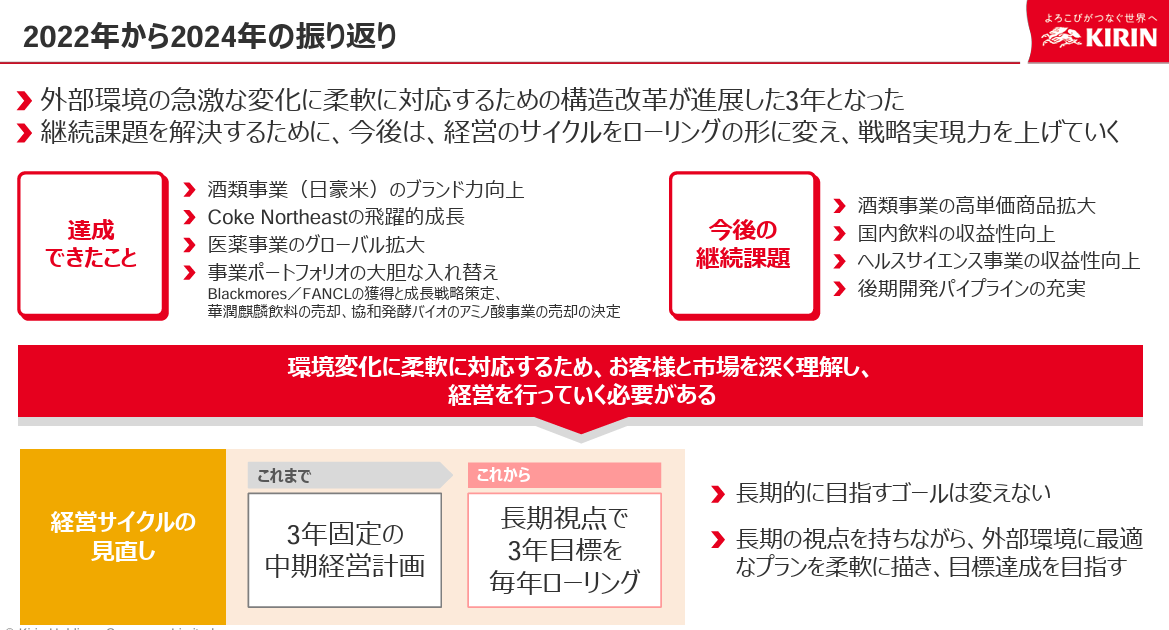日本のメディアに求められること
今回、世界に対して日本のメディアがSDGsに熱心に取り組んでいることを示せたことは、大きな意義があったと思います。また日本のメディアの署名数が一番多いことは世界に胸を張っていいでしょうが、本当に実態が伴っているか、国民に十分リーチできているかといえば、決して十分とは言えません。
世界経済フォーラムが去年世界28か国で行った調査では、日本のSDGsに対する認知度は、アメリカ、イギリスなどよりも低く、なんと最下位でした。最近、特に学生など若年層では、CSRやSDGsに対する関心は、以前とは比べものにならないくらい高まっていますが、国民全体に広がっているとはまだ言えません。そして、SDGsという言葉は時々耳にしても、個人個人が何をすればいいかよくわからないという人は多いでしょう。
それでは、我々の普段の生活の中で、何ができるかです。レジ袋の有料化を例にとってみると、最初はお金を取られることへの不満、マイバッグを持ち歩くことの面倒くささなど不便さを感じることもあったでしょう。しかし次第にマイバッグを持参する方向に生活様式が変わってきています。
これを、SDGsの17の目標に照らし合わせてみると、解釈はいろいろあるでしょうが、いくつかに該当していることがわかります。製造過程でCO2など温室効果ガスを多く排出することを考えれば、プラスチックを減らすことは「⑬気候変動に具体的な対策を」に貢献していると言えます。また海洋プラスチック汚染のことを考えれば「⑭海の豊かさを守ろう」にも該当します。また「⑪住み続けられるまちづくりを」や「⑫つくる責任 つかう責任」にも関係してくるでしょう。このほかにも該当するかもしれません。
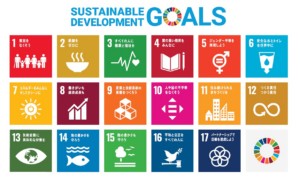
このように考えてみると、SDGsだからといって何も最初から大上段に構えなくてもよいように思います。一人一人の心がけ、心構え次第でSDGsの達成に向け、「参加できている」と言えるのです。みんながちょっとした参加意識を持つことが大事なのだろうと思います。
こうした中、メディアに求められることは、メディアの持つ最大の特性、強みである「伝える力」を生かして「伝え続ける」ことだと思います。SDGsの目標に照らし合わせると「⑰パートナーシップで目標を達成しよう」にあたるでしょう。
『より一層わかりやすく伝えていくことで、人と人がつながり、パートナーシップで世の中を変えていく』
国連が定めた2030年という期間までちょうど10年、目標達成に向けてメディアの果たすべき使命は大きいと改めて感じます。
(今回のトークセッションは、国連総会終了後も引き続き、国連の広報サイトUN Web TVでご覧になれます。)
吉川裕介・・・早稲田大学政経学部卒。1983年フジテレビ入社。
報道局では、多くの現場で記者活動や、番組制作を経験。
昨年よりCSR推進室長。
10年以上にわたって、フジテレビCSRプロジェクトチームに携わる。