世界に40億人いるとされる貧困層を新しい市場として開拓するBOP(ベース・オブ・ザ・ピラミッド=ピラミッドの土台、の意)ビジネスに、日本企業の参入表明が相次ぐ。BOPは貧困解決にも貢献すると期待されるが、その一方で貧困層を食い物にしたビジネスとの批判も根強い。BOPビジネスはこれからどこへ向かうのか。
BOPビジネスはダノンなどの欧米企業が先行すると言われるが、北海学園大学の菅原秀幸教授によれば、源流は1960年代のヤクルト本社の海外進出にあるという。ヤクルト・レディによる低所得地域での訪問販売こそが、BOPのビジネスモデルだという指摘だ。
その発生史的経緯はともかく、BOPという概念が米国の研究者によって最初に提唱されたのが1998年。それから遅れること10年、2009年に日本でも経済産業省が「官民連携によるBOPビジネスの推進」の取り組みを開始し「BOPビジネス元年」を迎えた。
そして今年7月、ユニクロを展開するファーストリテイリングがバングラデシュのグラミン銀行との合弁を表明。10月にはやはりグラミンと雪国まいたけ(新潟県南魚沼市)が、もやしの原料となる緑豆の栽培を目的とした合弁会社の設立で調印に漕ぎ着けた。さらに味の素も11月8日、国際NGOと共同でガーナでの栄養改善を目的にソーシャルビジネスの開発に着手すると発表した。
ところが、どの企業も表立ってBOPビジネスとは名乗らない。代わりに用いるのが「ソーシャルビジネス」という言葉だ。前者と後者に厳密な区別は難しいが、ソーシャルビジネスは社会的課題の解決が主目的で、営利追求が目的のビジネスはあくまでその手段、というニュアンスで用いられる。BOPビジネス=貧困層にモノを売りつける、という悪印象はどの企業も避けたいのだ。
こうした警戒は、途上国の住民を市場経済に強引に巻き込むものだとする、BOPビジネスへの根強い批判と不可分ではない。今年7月、世界最大の食品会社であるネスレがアマゾン川で自社製品を販売する移動店舗船(フローティング・スーパーマーケット)の運航を始めたところ、「ネスレがなくても生活してきた人々に販売する必要があるのか」「肥満など健康面の問題が増えるのではないか」との批判や懸念が噴出し、BOPビジネスの難しさを改めて示した。
貧困地域にビジネスを創出し、利益も生むと言われるBOPビジネスだが、万能の特効薬ではない。政府やNGO、ソーシャルベンチャーなど、様々な社会セクターとの協働なくして貧困解決はありえない。BOPビジネスがそのプロセスで成果を挙げられるか、真価が問われる。(オルタナ編集部=斉藤円華)2010年11月25日




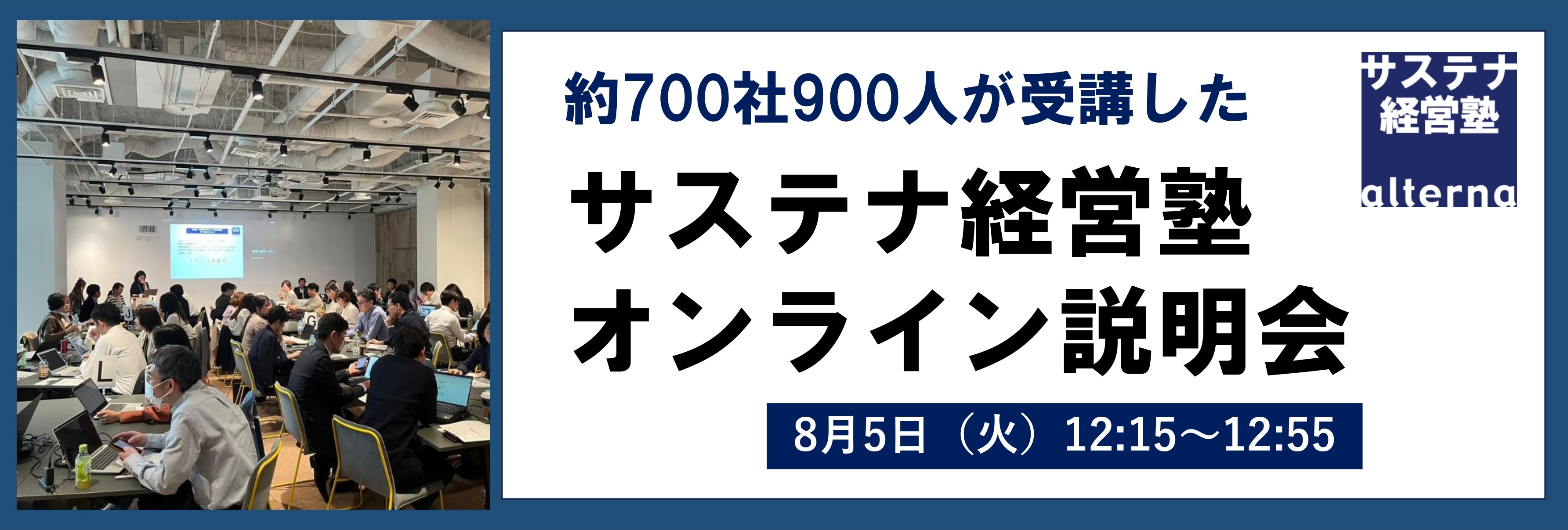




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























