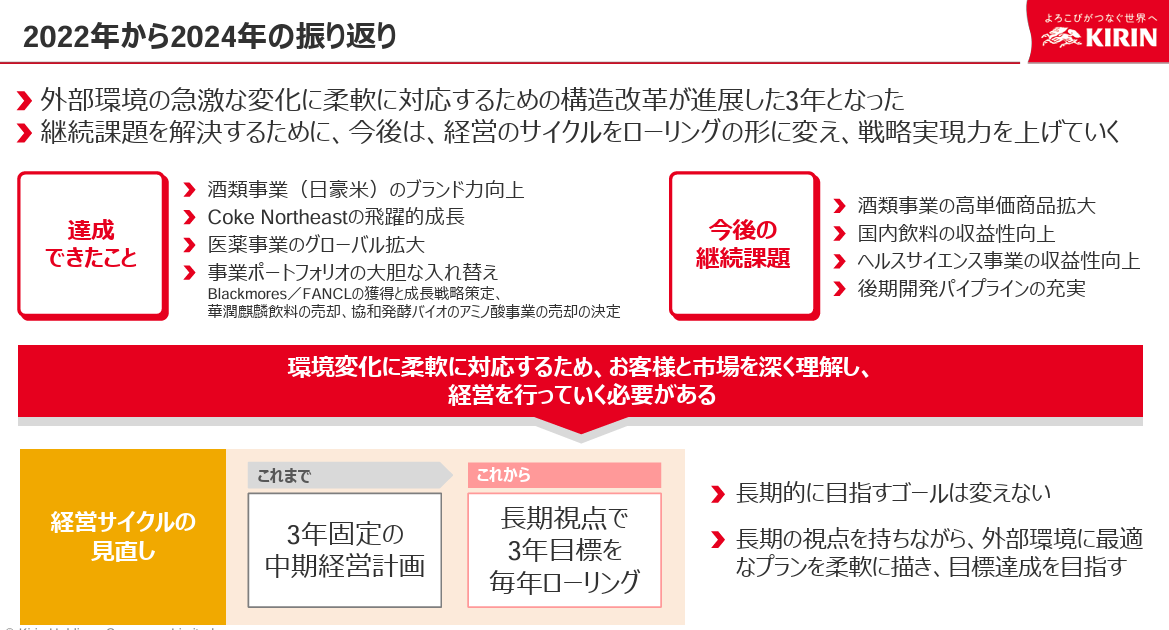その一方で、コロナ感染防止のために、多くの人がマスクをするようになってコミュニケーションしづらくなって困っている人が増えてきています。例えば、マスクによって声がこもるため、聞き取りづらくなったり、顔の表情が見えないため、おもてなしの気持ちや感情が伝わらず、ホスピタリティが低下してしまったりしています。
また、多くの聞こえない人は、口の形や表情を読み取って、話の内容を理解するため、マスクをすると情報がほぼシャットアウトされてしまい、困ってしまいます。
こういった伝わりづらさを解決するために、透明マスクなど、コミュニケーションを補完する製品が各メーカーから販売され、とても好ましい傾向だと思います。
このように環境が変わることで、これまでの当たり前が当たり前でなくなり、製品・サービスの価値が揺らいできています。そのような最中、ニューノーマルに適応した多様なコミュニケーションスタイルに対応したサービス・製品は今後一層注目されていくでしょう。
人間は一度便利だと思ったものを止めることはほとんどないので、コロナ禍で普及した便利なものは、今後もずっと残っていくでしょう。
ポストコロナ時代にいかに多様性に対応して仕事の生産性を上げていくか、生活の質を上げていくかが、今後、日本が浮上していくかどうかのキーになるのではないでしょうか。
例えば、これまで当たり前のように聞こえていた、または、見えていたなどが当たり前でなくなってきている現代だからこそ、聞こえづらさ、見えづらさなどをカバーするために、映像、音声、字幕テロップなどあらゆるコミュニケーションスタイルに対応したり、接客する場合はソーシャルディスタンスなど感染対策に配慮した上で、透明マスクなどを着用したりするなどして、ホスピタリティを向上させると良いでしょう。 皆さまも是非ともこのように多様なコミュニケーションスタイルへの対応を検討してみてはいかがでしょうか。
・家族内の多様なコミュニケーションスタイルへの対応を考えるイベント
http://bit.ly/IGB_20210130