■グッドガバナンス認証団体をめぐるー⑦「育て上げネット」
「若者と社会をつなぐ」をミッションに、就労支援や教育支援、子ども支援を通じ、働けずにいる若者を支援する育て上げネット(東京都立川市)。「働く=雇われる」という捉え方から離れ、若者の目線に立ち、リモートワークやインターネットを活用した最新の働き方や稼ぎ方を提案している。工藤啓理事長に活動内容を聞いた。(聞き手・村上 佳央=非営利組織評価センター、松田 慶子)
――事業を立ち上げられたきっかけを教えてください。
学生時代、父と若者支援の先進国と言われたヨーロッパを訪れる機会がありました。移民や親のない子供たちと共同生活をしながら支援をする現場を見学しました。
私が幼い頃、両親は家で学習塾を経営していたのです。障がいのある女性を受け入れたことをきっかけに、全国から不登校や非行、障がいなど、困難のある若者・子どもたちが集まってきました。30人位と寝食を共にしながらそれぞれの自立を支援する、そんな少し変わった家で育ちました。
ヨーロッパの支援現場を見て、実家の「塾」と似ている取り組みだと気づくと同時に、それが事業として成立していることに驚きました。若者の支援は、若者が社会を支える側に回ることで社会をよくするという「社会への投資」だ、という言葉に感銘を受け、帰国後に事業を立ち上げました。
――どのような支援をされていますか。
「若者と社会をつなぐ」ことをミッションに、働きたいけれど働けない、社会とつながりたいけどつながれないという若者・子どもたちの応援をしています。事業としては若者への「就労支援」、働きづらくなる前の予防的アプローチとして、定時制や単位制などの高校生に教育の支援をする「教育支援」、そうした高校にしか選択肢がなくなりやすい小中生を支援する「子ども支援」、ご家族そのものを支援する「家族支援」という四つを柱にしています。
就労支援で新規に相談に来られる若者は年間2000人位います。若者を受け入れる社会の側が間違っている、ということもあると考えており、その場合は「社会を若者の側に変えていく」というスタンスで支援しています。
――社会も若者の現状を知り、合わせることが必要なのでしょうか。
働きたいけれど就職活動をできない人は「無業者」と定義されています。就職活動をしないため、失業者にはカウントされませんが、若者(15~39歳)の17人に1人が就労しておらず、無業者は少しずつ増えています。非正規労働も多く、若者の自立を取り巻く状況は厳しいと言えます。
そのなかには「雇われる」働き方が合わない若者もいます。朝起きることやコミュニケーションを取ること、シフトをこなすこと…これらが苦手な人が雇われるためには、企業が必要とする形への「改善」が必要です。社会全体が「就職」目標に傾斜するなか、若者一人ひとりに合っているとは言えないと感じます。だからこそ、その若者に合った「働く」を一緒に考え、実現に向けて伴走する就労支援を大切にしています。
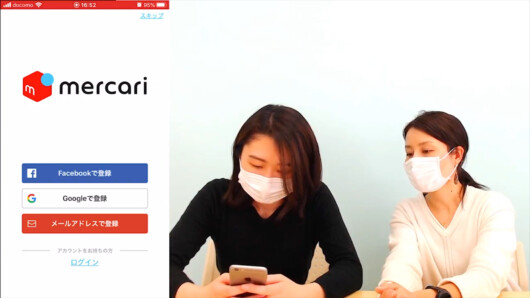
そこで「雇われる」以外の選択肢として、インターネットを活用した様々な「働き方」「稼ぎ方」に関する講座を始めています。例えば自宅にあるものや自分で制作した小物をアプリで販売する方法、動画を編集する方法、などです。単に「改善」を促すより、できることから始めましょうという提案にも賛同いただけて、とてもニーズが高いです。
興味深いのは、こうした稼ぎ方を学んだ若者の多くが就職活動もされることです。出品物が売れたり、誰かが「いいね」を付けてくれたりする経験を通じて、自分ができることを評価してもらい、動いてみようと思えるのかもしれません。また、自分に合った働き方として就職と自分で稼ぐ働き方を組み合わせたいという若者も多くいます。
――コロナ禍で、支援する若者の就労環境に変化はありますか。
これまでひきこもり状態で、外出できないと働けないというプレッシャーを受けていた若者が、立て続けに3~4人、クラウド系の事業会社でフルタイムのリモートワークの仕事に就きました。このほかリモートの事務系の仕事など、対面コミュニケーションが苦手な若者にとっては選択肢が増えています。チャットコミュニケーションではむしろ力を発揮する若者もいます。
逆に「リモートワークでは困る」という企業も若者もいますので、マッチングしやすくなった面があります。我々としてはリモート系の支援を少しずつ充実させています。
――時代の変化に合わせた働き方の提案ですね。
スマホやパソコンでのコミュニケーションは得意だけれど対面は苦手、という若者は一定数います。彼らにとって対面でのコミュニケーションが必要な働き方は合っていません。本当は黙々と作業できるような、昔でいう「工場労働」などが合っている話はここかしこにあります。では工場労働の現代版の仕事とは何かと考えると、例えばゲームやアプリのバグを発見する仕事などは、大変な人手不足でニーズが高いです。このように彼らの才能を生かせて、求人も多い仕事を見つけ、マッチングしていきたいです。
課題は、仕事と個人の間に入る我々が、こうした最新の仕事情報を常にアップデートしておくことです。ここが遅れると支援のボトルネックになってしまいます。
――事業を進めるうえで、気を付けていらっしゃることはありますか。

選択肢が増えている」とする工藤啓 理事長
多くの団体を協業することを大切にしています、先ほどの新たな働き方への支援に関しても、40か所ほどのNPOなどと一緒に進めています。行政に働きかけるときは「みんなで取り組んでうまくいったので、より多くの団体が参加できるよう制度を変更してほしい」という伝えかたをしています。
――「グッドガバナンス認証」を取得された理由や、その効果はいかがでしょうか。
NPO法人は日本で信頼されていない現状があり、対人支援をするNPOとしては、以前から信頼性の担保には課題感を持っていました。グッドガバナンス認証の取得を目指すうちに、ガバナンス面で我々に何が足りないのかを理解することができました。
取得後は企業からの与信調査への対応に大変役立っています。特に外資系企業からの調査は厳しく、本来なら報告のために多くの書類が必要であったところを、グッドガバナンス認証のおかげですべて揃えられたということがあり、とても助かりました。
今後NPOは企業との協業もいま以上に増えてくると思います。人権やハラスメントへの対応なども含め、社会や企業からの要請は変化しています。グッドガバナンス認証も今後ともに進化し、何をすべきかを教えてくださる認証であるとありがたいです。
◆「グッドガバナンス認証」とは
一般財団法人非営利組織評価センター(JCNE)が、第三者機関の立場からNPOなど非営利組織の信頼性を形に表した組織を評価し、認証している。「自立」と「自律」の力を備え「グッドなガバナンス」を維持しているNPO を認証し、信頼性を担保することで、NPO が幅広い支援を継続的に獲得できるよう手助けをする仕組みだ。詳しくはこちらへ。



































