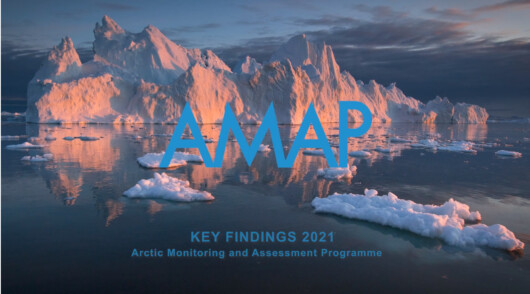
「AMAP Assessment Findings 2021」より
北極の温暖化は世界平均の3倍の速さで進行している。それに伴う異変を科学者たちが語る約12分のビデオが、このほど日本語字幕入りで公開された。これは北極評議会の北極圏監視・評価プログラム作業部会(AMAP)が5月に英語で発表した「AMAP Assessment Findings 2021」を日本の北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)が翻訳したもの。ArCS IIはAMAPの5つの最新レポートの日本語訳版も制作し公表している。(オルタナ編集委員=瀬戸内千代)
変わりゆく北極
北極評議会は北極圏にある8カ国から成り、その下部組織のAMAPは気候変化と健康をテーマに1991年から活動している。今年、ビデオと2年ぶりの政策決定者向けサマリー(要約)5つを発表した。
サマリーの1つ「北極気候変化のアップデート2021:主な変化傾向と影響」によると、北極の年平均気温は1971年からの49年間で3.1℃高くなった。スカンジナビア半島の北に位置する北東バレンツ海では最高10.6℃も上がったという。
2000年以降、15日以上続く寒波は北極から姿を消し、激しい嵐などの影響もあって、アラスカの一部の海岸線は毎年5mも後退しているという。これらの事実からAMAPは、「パリ協定の完全な実施」を強く求めている。
日本はオブザーバーとして貢献
日本政府は北極評議会にオブザーバー参加を続けており、AMAPにも日本の北極研究者が主に自然科学の分野で貢献している。ArCS IIは国立極地研究所が中心となって日本の北極関係者を束ねる2020~25年の国家プロジェクトで、日本社会に北極の状況を知らせる役割も担っている。
ArCS IIの榎本 浩之プロジェクトディレクターによると、2020年にはロシアの北極地域で永久凍土が解けて石油貯蔵タンクが倒壊し、2021年にはグリーンランドの最高地点で観測史上初めての雨が降ったという。
日本の立場について榎本氏は、「北極圏外から参加する第三者だからこそ、うまく機能する面があり、先住民側からも日本の関りを求められている」と語る。異変の影響を真っ先に受けるのは先住民たちであり、彼らとの協働の重要性は世界の北極研究者の共通認識になっている。
AMAP制作ビデオ「AMAP Assessment Findings 2021」









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























