不二製油グループは統合報告書2021の編集方針に「ネガティブな内容についても透明性をもって報告する」と掲げています。それは酒井幹夫CEOと西秀訓社外取締役の対談の中に明確に示されています。(オルタナ総研フェロー=室井孝之)
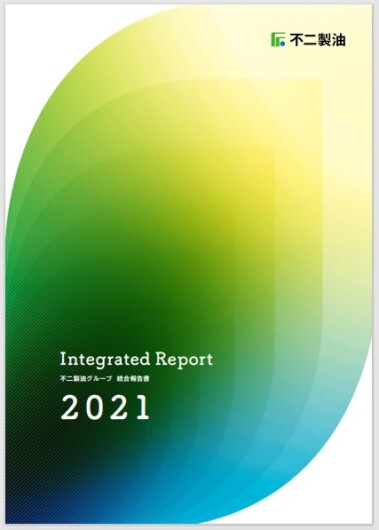
対談(CEO×社外取締役)で西社外取締役は、酒井CEOに対し「コロナ禍の環境変化に対する分析や、戦略策定、執行のスピード感が足らず、平時の感覚が残っている印象です」と述べました。
酒井CEOは「物流の遮断により原材料が調達できない、出荷が滞るなどの影響がありました。それに対応する調達面での協力も十分に行えず、世界各地で事業を行っていることのメリットを活かしきれなかったと認識しています」と答えています。
その他にも西社外取締役は、次の様に発言しています。
「コロナ禍の経済は、K字回復といわれ、業績を伸ばす企業と落ち込む企業に二極化しています。その中で、業績を伸ばすグループに入っていけるのかいうとやや心もとない」
「Plant-Based Food Solutions(PBFS)というコンセプトがありますが、これは不二製油グループの目指すドメインであって、戦略は表していないと思っています。植物性食品の全てをやれるわけではありませんので、そこをもっと研ぎ澄ましていくことが重要です」
「ポートフォリオ」がどういう単位で議論されているのかがよく見えてきません。事業とエリアのマトリクスをいかに中長期的に管理していくのか、どう収益を管理していくのかということが、見えづらいように感じています」
対談を通じて社外取締役が課題を質し、CEOが正直に誠実に答える姿は新鮮です。

また最高ESG経営責任者(C『ESG』O)を擁立している点も経営の本気さを感じます。
一方、他の編集方針に「ステークホルダーとの対話を通じて相互理解を深めることで、経営改善を進める好循環を継続する」とあります。
「ステークホルダーと対話」は、製品納品先、顧客、担当者、グループ会社トップの「声」が掲載されていますが、ビジネス面やグループ内のステークホルダーに限定されています。
ステークホルダーの範囲を広め、例えば人権に関して人権を専門とするNGOとのステークホルダーダイアログを行い、その論議内容を開示するなどの工夫はいかがでしょうか。


































