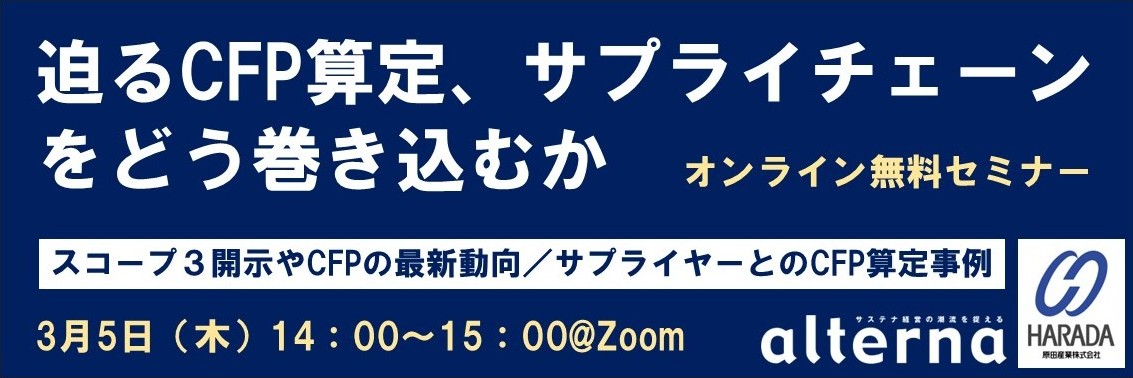最近、企業経営やブランディングの視点から「パーパス(存在意義)」を公表する企業が増えています。企業のサステナビリティ(持続可能性)推進担当という立場から様々な企業のパーパスが気になって調べていますが、パーパスの文脈には「世界」や「社会とのつながり」などの表現が多いように感じます。(高山 功平)

CSRやサステナブル経営に長く関わらせていただく中で、企業規模にかかわらず苦戦してきたのが「社内浸透」です。中長期的なサステナビリティの推進は、日々の業務の中で、どうしても優先度が下がってしまいます。
これは仕方がないと考えています。「気持ちは分かるし、大切なのは分かるけど、今すぐにじゃない」このような言葉を返された経験が多々あります。
その進みにくさが、ここ最近のパーパスの策定の流れで、良い方向に変わりつつあると感じます。パーパスの策定により存在意義を考えたとき、どうしても社会やステークホルダーとのつながりや貢献できることを考えなくてはなりません。
短期ではなく中長期的、自社ではなく社会という視点でのキーワードが組み込まれるため、「未来」というゴールがサステナブル活動と一致します。そして、企業にとってパーパスを最も行動として示しやすいのがサステナブル活動です。
これまで苦戦した社内浸透が、パーパスという追い風を受け、いよいよSX(サステナブル・トランスフォーメーション)の実現がしやすくなっています。
これまでは、本業とサステナブル別々に回していましたが、バランスよく両輪で回すために「パーパス」という車軸ができつつあると感じます。サステナブル推進に苦戦しているのであれば、まずは、パーパスの策定を社内で提案してみるのも一手だと思います。
高山功平(たかやま・こうへい)
株式会社ネオキャリア社長室サステナブル推進担当。1975年神奈川県生まれ。青山学院大学経営学部卒業。 企業のCSR、サステナブル担当としてのキャリア17年、子育て支援、障がい者雇用、障がい者スポーツ支援、ステークホルダーエンゲージメントなど中小企業のサステナブル推進を経験。