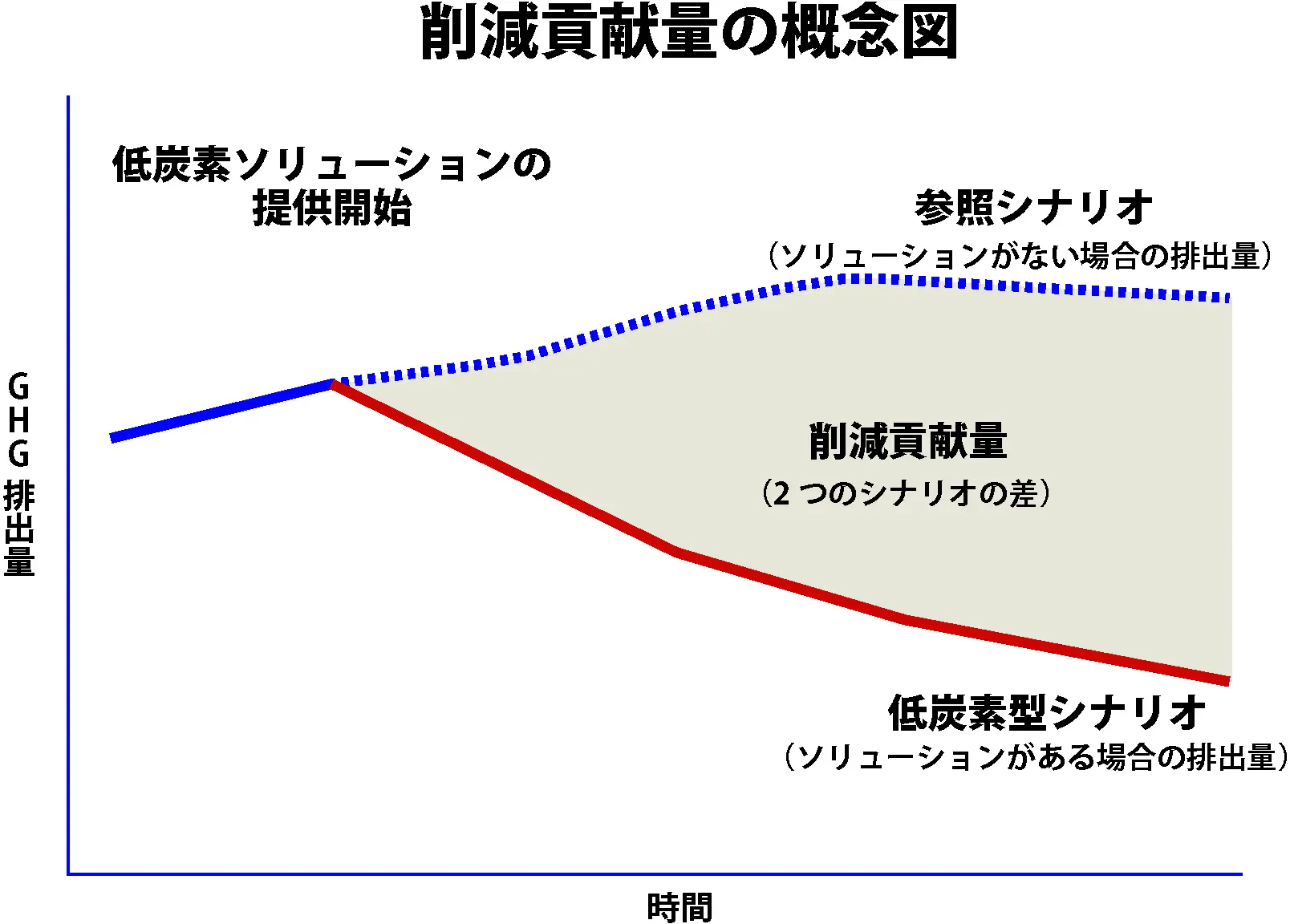記事のポイント
- 与党案に修正を加えた「LGBT理解増進法案」が16日に成立した
- LGBTQ当事者や支援者らは「差別を助長しかねない」として抗議していた
- 「適正に運用されるように、声を上げてほしい」と訴えた
与党案に修正を加えた「LGBT理解増進法案」が6月16日、参議院本会議で成立した。公布日から施行する。修正が加えられるたびに後退する法案に対し、LGBTQ当事者や支援者らは「差別を助長しかねない」として、強く抗議していた。企業や自治体、教育機関に対する努力義務規定も盛り込まれたことから、「適正に運用されるように、声を上げてほしい」と訴えた。(オルタナ副編集長=吉田広子)

■ 当事者の困難に向き合わず、トイレやお風呂の問題に終始
「LGBT理解増進法案」が衆議院内閣委員会で審議入りする直前、与党案に異例の修正が加わった。LGBTQ当事者や支援者らは、「理解増進ではなく、理解を『阻害』しかねない」として、強く抗議していた。特に問題視したのは、第12条として「すべての国民が安心して生活することができるよう留意する指針の策定」を追加したことだ。
差別禁止法の制定を求めてきたLGBT法連合会は、「実質的に多数派に配慮する規定になる」と批判した。障がいや男女雇用、部落などの差別を禁止する法律では、同様の記載はないという。
15日の参議院内閣委員会に参考人として出席した松岡宗嗣・fair代表理事は「衆院内閣委での審議は、トイレやお風呂の話題に終始していた。女性も性的マイノリティも安心して過ごせる環境整備は必要だが、いじめやハラスメント、自死など性的マイノリティが抱える困難を解消するつもりがあるのか、疑問だ。エビデンスやデータを基にした議論が欠けている」と発言した。
松岡代表理事は、「『当事者が差別といえば何でも差別になる』という言説があるが、そうではない。『合理的な理由のある区別』は差別にあたらない」と説明する。
「男女別に分かれた施設に関しても、施設の環境によって基準や対応は異なる。トランスジェンダー当事者は、当然断られる事情もよく理解している。0か100かではなく、環境に応じた『合理的な配慮』を考えていく必要がある」(松岡代表理事)
法案成立後、記者会見を開いたLGBT法連合会の神谷悠一事務局長は、「第12条に基づいて、『安心できない』からと、LGBTQ支援活動が阻害される可能性がある。そうしたバックラッシュ(揺り戻し)に対して、どう取り組むか。これからまた歩みを進めなければならない」と失望感をあらわにした。
■ 企業には理解を増進する努力義務規定も
LGBT理解増進法案では、企業に対し、理解増進の取り組みを促す努力義務が盛り込まれた。
第6条では、事業主に対し、「普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保などを行い、性的マイノリティに対する理解の増進に自ら努めること」を求めている。
第10条では、「理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする」としている。
もともと与党案にあった「民間の団体等の自発的な活動の促進」という記述は、維新・国民の要望によって削除されたが、阿部司・衆議院議員は「活動を制限するものではない」と参院内閣委で明言した。
企業は、DEI(ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン)を掲げ、人材確保の面でも、社会や顧客などステークホルダーの期待に応えるためにも、LGBTQ支援に熱心に取り組む。社内や、製品・サービスに社会の多様性を反映するという考え方も根付き始めている。
LGBTQなどの理解や権利擁護などの取り組みを評価するPRIDE指標2022」では、ゴールド318社、シルバー51社、ブロンズ29社が認定された。
Marriage For All Japanの松中権理事は、「これまで企業は、法律や訴訟にかかわることとは距離を置いていた。しかし、社会をより良くしていくための責任があるということを自覚し始めた。さまざまなチャネルを持つ企業には、法律が適切に運用され、LGBTQへの理解を正しく増進するためにも、ぜひとも声を上げ、アクションを起こしてほしい」と訴えた。