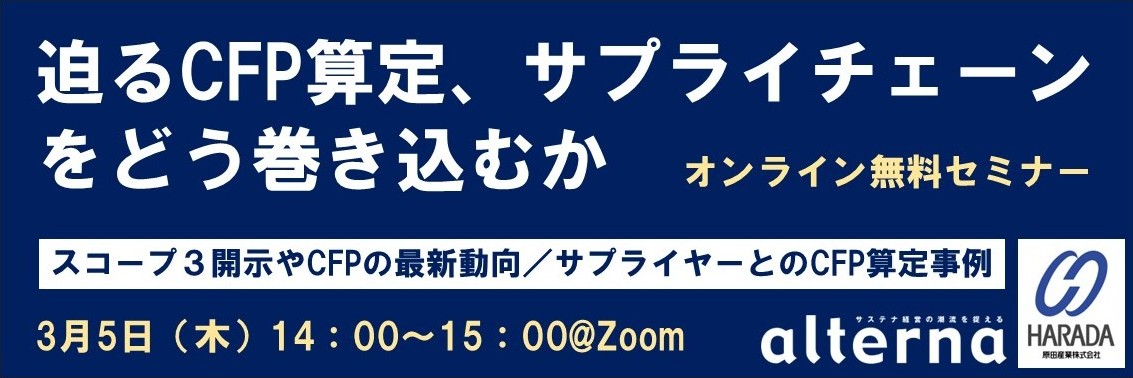記事のポイント
- オルタナが開いた第70回SBLセミナーにISSBの小森博司理事が登壇した
- 自社の重要課題を明確化し、投資家と認識を合わせることが重要だと指摘
- 経営戦略と整合した開示戦略の構築が競争優位の源泉になると語った
オルタナが7月9日に開いた、第70回SBLセミナーにサステナ情報開示の基準づくりを担う国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の小森博司理事が登壇した。サステナ情報開示については、各国の規制当局が強化する動きがあるが、小森理事は、「単に基準に備えるのではなく、企業自身が投資家とのコミュニケーションを通じた価値創造を目指すべき」と強調した。小森理事の講演内容をまとめた。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)

サステナビリティ情報開示を巡る企業の現場では、長らく「開示対応疲れ」という深刻な問題が蔓延していました。投資家が何を求めているのか不明確な中、次々と登場する様々な開示フレームワークや評価制度に対応するため、企業は膨大なリソースを投入し続けてきました。
一方で投資家側も、統一された基準がない中で企業が提供する情報の比較可能性の難しさの問題に直面していました。同じ企業なのに異なるデータプロバイダーから全く違う数値が提示されるといった混乱状況にも陥っていたのです。
この状況を問題視した国際金融安定理事会(FSB)は、資本市場が合理的に機能していないという判断を下しました。
気候変動をはじめとする社会課題が深刻化する中、企業が適切な基準に基づいて開示を行い、投資家が的確な判断を下せる環境を整備することが急務となっていました。そこでFSBは、これまで会計基準を担ってきたIFRS財団に対し、サステナビリティ分野でも基準策定を行うよう要請したのです。
2021年のCOP26において国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立が公表され、世界各国の金融当局団体である証券監督者国際機構(IOSCO)の全面的な支援のもと、「グローバルベースライン」となるS1およびS2基準の策定が進められました。
■ISSB基準での情報開示、36カ国が導入へ
これらの基準は、各国で法的拘束力を持った開示制度として導入されることを前提として設計されており、現在36カ国がこの基準を採用または採用予定となっています。
日本においても、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)がISSB基準をベースとした日本版の基準を策定し、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業を対象として段階的な義務化が開始される予定です。
この動きは、これまでの任意開示中心の環境から、統一された基準に基づく義務開示への大きな転換点を意味しています。
■財務情報と同じ判断軸でESGを評価へ
ISSB基準の核心となるのが、IFRS会計基準と共通のマテリアリティの定義を採用したことにあります。これにより、財務情報とサステナビリティ情報が同じ判断基準で開示・評価されることになり、企業の統合的な情報開示が可能となりました。
マテリアリティの定義は、短期・中期・長期の時間軸において、企業のキャッシュフロー、資本コスト、資金調達、さらにはビジネスモデルに重要な影響を合理的に与え得るリスクと機会を対象としています。
この定義の明確化によって、企業は投資家が真に必要とする情報に焦点を絞った開示が可能となります。従来の統合報告書では、マルチステークホルダー向けの情報が混在し、150ページから200ページに及ぶ膨大な資料となることが多く、投資家にとって使いづらいものとなっていました。
新しい基準では、投資家の意思決定に直結する情報のみを抽出し、効率的で効果的な開示を実現することが期待されています。
企業にとって重要なのは、2027年の義務化開始前の任意期間中に、自社のマテリアリティを明確に定義し、短期・中期・長期の時間軸を設定することです。これらの定義は取締役会レベルで決定される必要があり、その後、自社の事業をよく理解している投資家との対話を通じて、投資家と定義を揃える必要があります。
この対話プロセスは、企業と投資家の間に存在する情報の非対称性を解消する重要な機会となります。企業は自社の詳細な情報を保有している一方、投資家は同業他社や市場全体の動向について幅広い知見を持っています。
ISSB基準では、マテリアリティの定義と時間軸について定めました。これによって企業と投資家双方の視点を統合し、より精度の高い開示内容を構築することが期待できます。
■サステナビリティを「経営マター」へ
ISSB基準の実効性を高めるためには、取締役会レベルでの積極的な関与が不可欠です。従来、サステナビリティ関連の開示は現場レベルで作成され、取締役会では形式的な承認に留まるということが多くあったと推測します。
しかし、ISSB基準では、マテリアリティの最終判断から開示内容の決定まで、すべてのプロセスに取締役会メンバーが関与することが求められています。
この変化の背景には、サステナビリティ課題がもはや単なる環境・社会問題ではなく、企業の中核的な経営課題、戦略マターであるという認識の転換があるのです。
気候変動対応や人的資本の活用は、企業の競争力や持続的成長に直結する戦略的要素であり、経営陣が主導的に取り組むべき領域です。特に重要なのが、サステナビリティ部門と財務・経理部門間のコネクティビティの強化です。
会計基準が主に過去の財務情報を扱うのに対し、サステナビリティ開示は将来情報が中心で、確実性の程度も異なります。これらの異なる性質を持つ情報を統合的に開示するためには、部門間の密接な連携が必要となります。
IFRS財団内でも、会計基準を担当する国際会計基準審議会(IASB)とサステナビリティ基準を担当するISSBとの間でコネクティビティ向上のための議論が活発化しています。
企業においても、CSuO(最高サステナビリティ責任者)とCFO(最高財務責任者)、さらにはCEOを含めた経営陣レベルでの連携体制の構築が急務です。社外取締役に対するサステナビリティ教育も重要な課題として浮上しています。
■生物多様性と人的資本の基準化は検討課題に
ISSBは現在、S2の気候変動に続く基準として、生物多様性と人的資本に関する基準策定を目指した調査を進めています。しかし、これらの分野は気候変動とは異なる複雑さを抱えており、基準化への道のりは平坦ではありません。
生物多様性については、地域やセクターによる影響の違いが極めて大きく、普遍的な指標の設定の議論が必要です。同じ業界内でも、事業展開地域や具体的な事業内容によって生物多様性への影響は大きく異なるため、統一的な基準策定には慎重な検討が必要と思われます。
一方、人的資本についても、世界中の企業にとって共通の重要課題であり、デジタル化の進展や労働市場の変化によって、人材の確保・育成・活用は企業競争力の源泉となっており、投資家の関心も高まっていますが、具体的にどのように投資家のリターンに影響するかは明らかではありません。
ISSBでは、新たな基準策定に際して厳格なデュープロセス(内部規定に基づいた適正な対応)を採用しています。まず徹底的なリサーチを実施し、基準策定による企業の負担と投資家や資本市場全体への便益を詳細に分析します。
その結果、資本市場全体として明確なプラスの効果が認められる場合のみ、基準策定に進むという慎重なアプローチを取っています。現時点では、生物多様性と人的資本の調査を継続しながら、調査結果を踏まえて最終判断を行う予定です。
■欧州企業は決算期後「2カ月」で保証付き開示
2024年12月期から欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)に基づく開示を開始した欧州主要企業の実績は、日本企業にとって重要な示唆を提供しています。注目すべきは、多くの企業が決算期後わずか2カ月で限定保証付きの開示を実現していることです。
この迅速な開示を可能にしているのは、年間を通じた継続的な保証プロセスの導入です。保証人は中間決算時に暫定的な保証を実施し、第3四半期でフォローアップを行い、その後毎月保証作業を継続することで、期末時点での迅速な最終保証を実現しています。
しかし、このプロセスが機能するためには、企業側でのデータ整備とシステム基盤の構築が前提となります。特に重要なのは、スコープ1・2・3の温室効果ガス排出量算定のためのデータ収集・算定システムの整備です。
これらのシステムは、サプライチェーン全体からのデータ収集、複雑な計算処理、継続的なモニタリングを自動化する必要があり、高度な技術が求められます。
興味深いのは、これらのプラットフォーム開発を担う企業の多くが若い世代によって設立・運営されているスタートアップ企業であるということです。社会的意義を重視し、最新技術を駆使してサステナビリティ課題の解決に取り組む若い起業家たちが、この分野をリードしています。
■規制対応ではなく投資家との対話による価値創造を
ISSB基準の最大の特徴は、真のグローバル統一基準として機能することです。現在36カ国が採用または採用予定となっており、多国籍企業にとっては、世界各地の子会社やサプライヤーが同一基準で開示を行うことで、大幅な効率化が期待できます。
シンガポールなどでは、非上場企業であっても一定規模以上の企業には上場企業と同等の開示基準を適用する検討が進められており、日本企業の海外子会社やサプライヤーも対象となる可能性が高いです。このような状況下では、グループ全体で統一された開示基準を採用することの戦略的価値が一層高まっています。
特に、グローバルに事業展開する日本企業にとっては、国内規制の動向のみならず、国際基準の変化を常に注視し、自社のビジネス戦略と整合した開示戦略を構築することが競争優位の源泉となります。これは、従来の規制対応型のアプローチから、戦略的な情報開示への転換を意味しています。
■まずできることから開示を
ISSB基準の導入をきっかけに、統一された基準に基づく開示を通して企業は投資家との建設的な対話を行い、サステナビリティ課題への取り組みを競争優位の源泉として活用することが可能となります。
必要なのは、マテリアルなサステナビリティ課題を経営の中核に位置づけ、取締役会レベルでの戦略的な意思決定プロセスを確立することです。
財務部門とサステナビリティ部門の連携強化、内部統制部門との連携、若手人材の積極的活用、継続的なシステム投資により、戦略に基づいた効率的で効果的な開示体制を構築することが重要です。(談)