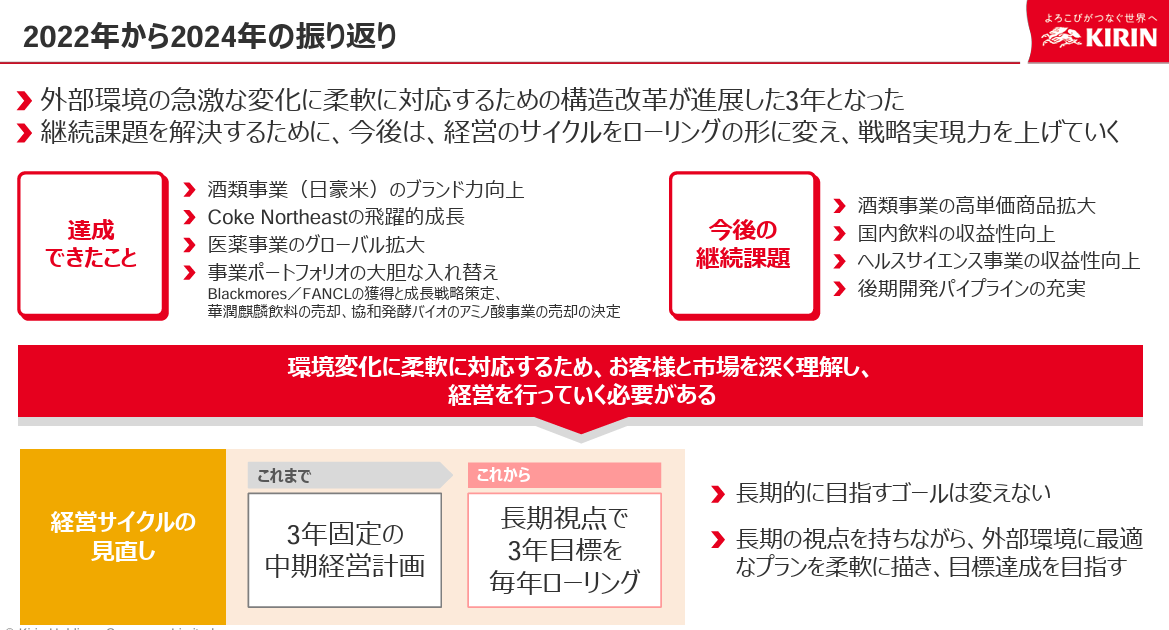記事のポイント
- SDGs採択から10年が経つが、半分以上のゴールが足踏み・後退している
- 日本の進捗状況についても、「SDG3(健康)」以外、課題は残るとの評価だ
- 企業には「深刻な課題が残る」領域を減らすための実質的な貢献が求められる
2015年のSDGs採択から10年が経つが、半分以上のゴールが足踏み・後退している状況だ。国別の進捗状況を示すダッシュボードを見ても、日本では「SDG3(健康)」以外、課題が残る。なかでも「深刻な課題が残る」とされる領域を少しでも減らせるよう、企業の実質的な貢献が求められている。(サステナブル経営アドバイザー・足立直樹)

「赤:深刻な課題が残る」「橙:重大な課題が残る」
「黄:課題が残る」「緑:達成済み」で色分けしている
SDGs(持続可能な開発目標)が採択されたのは今から 10年前、2015年9月25日~27日の国連持続可能な開発サミットでした。そして翌2016年から活動がスタートし、今年でちょうど10年です。2030年まで残り5年、私たちはどこまで来ているのでしょうか。
■10年の成果と停滞:現実は厳しいが前進はしている
2025年7月に発行された国連の報告書『SDGsレポート2025』によれば、評価対象169のターゲットのうち、達成または順調に進んでいるのはわずか18%です。中程度の進展の17%を加えても、全体の35%にとどまります。
一方で、31%がわずかな進展、17%は停滞、18%は後退しており、半分以上の目標が足踏み、あるいは逆行しているというのが現実です。
国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「私たちは、いるべき場所にいない」と述べたのは、その危機感の表れでしょう。「残りの期間でSDGsを達成するために、ギアを上げなければならない」とも言っており、切迫した現状を物語っています。
それでも、この10年間に確かな前進があったことも事実です。国連報告書は次のような成果を挙げています。
・ 極度の貧困層は2015年の10.8%から2023年には8.5%へ減少。
・ 児童婚はこの10年で20%減少。
・ 母子死亡率は2000年以降で34%減少。
・ インターネット利用率は世界の3分の2に達し、10年前の倍近くに増加。
思い起こして欲しいのですが、2016年当時、「サステナビリティ」という言葉を知る人はごく一部でした。それが今では、小学校の授業でもSDGsが教えられ、企業も自治体も市民も行動に移すようになっています。
まだ表面的な取り組みも少なくありませんが、17のターゲットが共通言語となったこと自体、大きな進歩です。
■日本の現状:平均点は上がったけれど……
国連の報告書に先立ち、持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が6月に発表した『持続可能な開発レポート2025』では、国別の進捗度が評価されています。これによると、日本のインデックススコアは80.7点(前年比+2.0)でした。OECD加盟38カ国の平均点(79.5)よりやや高く、世界で19位となっています。
高評価を得たのは、貧困(SDG1)、健康(SDG3)、教育(SDG4)、雇用(SDG8)、産業とイノベーション(SDG9)です。エネルギーアクセス(SDG7)も良いのですが、再生可能エネルギーへのアクセスが8.8%で低い状態です。
一方で、ジェンダー平等(SDG5)や不平等(SDG10)は依然として低水準です。
気候変動(SDG13)もさらに努力が必要であり、水と衛生(SDG6)も水ストレスが低くはないことと、輸入財に含まれる「仮想水」消費の多さが課題だと指摘されています。
さらに、消費と生産(SDG12)、海洋生態系(SDG14)、陸域生態系(SDG15)は「重大な課題」と評価され、サーキュラーエコノミーと生物多様性という重大な課題への取り組みが遅れている現状を示しています。
■赤く染まった日本のダッシュボード
これら17のターゲットの進捗状況を緑・橙・黄・赤と色分けして示したダッシュボードで見ると、今年の日本は赤(深刻な課題が残る)やオレンジ(重要な課題が残る)ばかり。まるで警告灯がともったかのようです。緑(達成済み)が健康(SDG3)だけとなってしまい、もしかして一気に後退してしまったのかと、最初に見たときにはドキッとしました。
しかし、これは評価基準が厳しくなったことが大きな要因です。目標水準が「OECD上位国」や「パリ協定整合レベル」に引き上げられたため、特に先進国ほど採点が厳しくなったのです。
それでも、「悪化していないなら安心」とは言えません。そもそも基準が高くなったのは、世界全体が次の段階へ進もうとしているからです。求められているのは、これまでの延長の努力ではなく、構造そのものの転換なのです。
■次の5年へ向けて企業がすべきことは
国連では今後5年間を、食料システム、エネルギーアクセス、デジタル化、教育、雇用と社会保障、気候と生物多様性という6つのトランジション(移行/構造転換)に焦点を当てています。そして、その実現には政治的リーダーシップ、持続的な投資、質の高いデータ、国際協調が不可欠だとしています。
日本は今のところ世界第3位のODA(政府開発援助)拠出国ですが、円安や財政制約の中で、資金での貢献には限界があります。これからは、技術・知恵・制度設計で世界に貢献する方向に進化すべきではないでしょうか。
そしてもちろん、SDGsの進捗を眺める意味は、順位を競うことではありません。自分たちの立ち位置と、変えなければならない現実を知るためです。
企業にとって大事なのは、ダッシュボードの「赤」を減らすためにどう貢献するか、そしてその変化を自社の事業・サプライチェーン・地域社会の未来づくりにつなげることです。
「私たちはもっと早く動かなくてはならない。私たちは共に動かなくてはならない」というグテーレス事務総長の言葉を噛み締めたいと思います。
2030年までのあと5年。サステナビリティは、「いつか」ではなく、「今」問われている実行力のことです。
※この記事は、株式会社レスポンスアビリティのメールマガジン「サステナブル経営通信」(サス経)525(2025年10月8日発行)をオルタナ編集部にて一部編集したものです。過去の「サス経」はこちらから、執筆者の思いをまとめたnote「最初のひとしずく」はこちらからお読みいただけます。