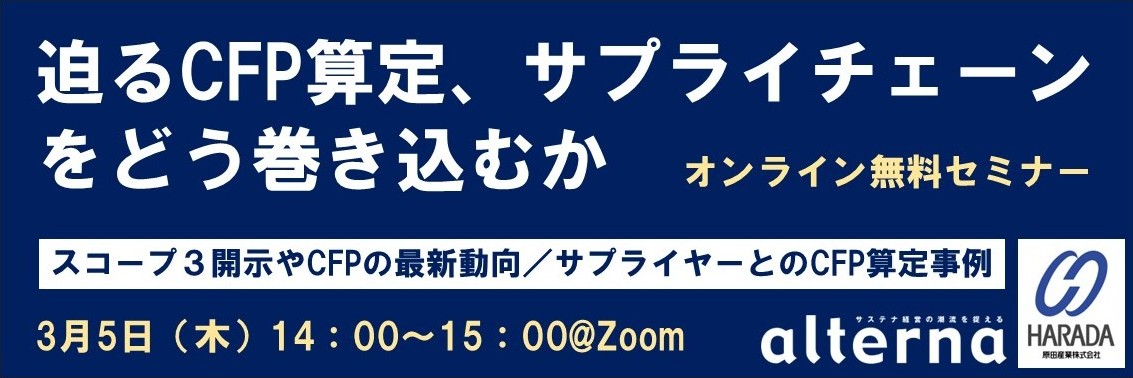■日本民間公益活動連携機構・二宮雅也理事長ロングインタビュー
金融機関の口座に預けられたまま10年以上取引されていない「休眠預金」が、社会課題の解決のために活用されることになった。指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)は、初年度の活動方針の骨子を決めた。まず約30億円を、草の根活動支援など5つのプログラムに沿って配分する。本格的な始動を控え、同機構の二宮(ふたみや)雅也理事長(損害保険ジャパン日本興亜会長)に今後の方針を聞いた。(聞き手・オルタナ編集長・森 摂、富永周也)

毎年700億円発生する「休眠預金」を使い、社会課題を解決
――JANPIAはどのような目的で設立されたのでしょうか。
昨年1月に休眠預金等活用法が施行されたことに伴い、同法に定める「指定活用団体」となることを目指して、昨年7月に一般社団法人日本経済団体連合会(日本経団連)によって本機構が設立されました。休眠預金とは持っているだけで、10年以上にわたって取引をしていない口座に眠っている預金で、現在毎年700億円程度発生するとされています。
これをいったん、所定の機関に移管し、社会課題の解決や民間公益活動のために活用する制度を作るための指針が休眠預金等活用法であり、法に則っていかに具現化していくかが本機構の使命です。
今年4月から、休眠預金などの活用に関して「資金分配団体」の公募のための説明会を全国各地で始めました。資金分配団体とは民間公益活動を行う実行団体に助成などを行う団体で、JANPIAが提示する「優先的に解決すべき社会の諸課題」を踏まえ、役割を担っていくものです。