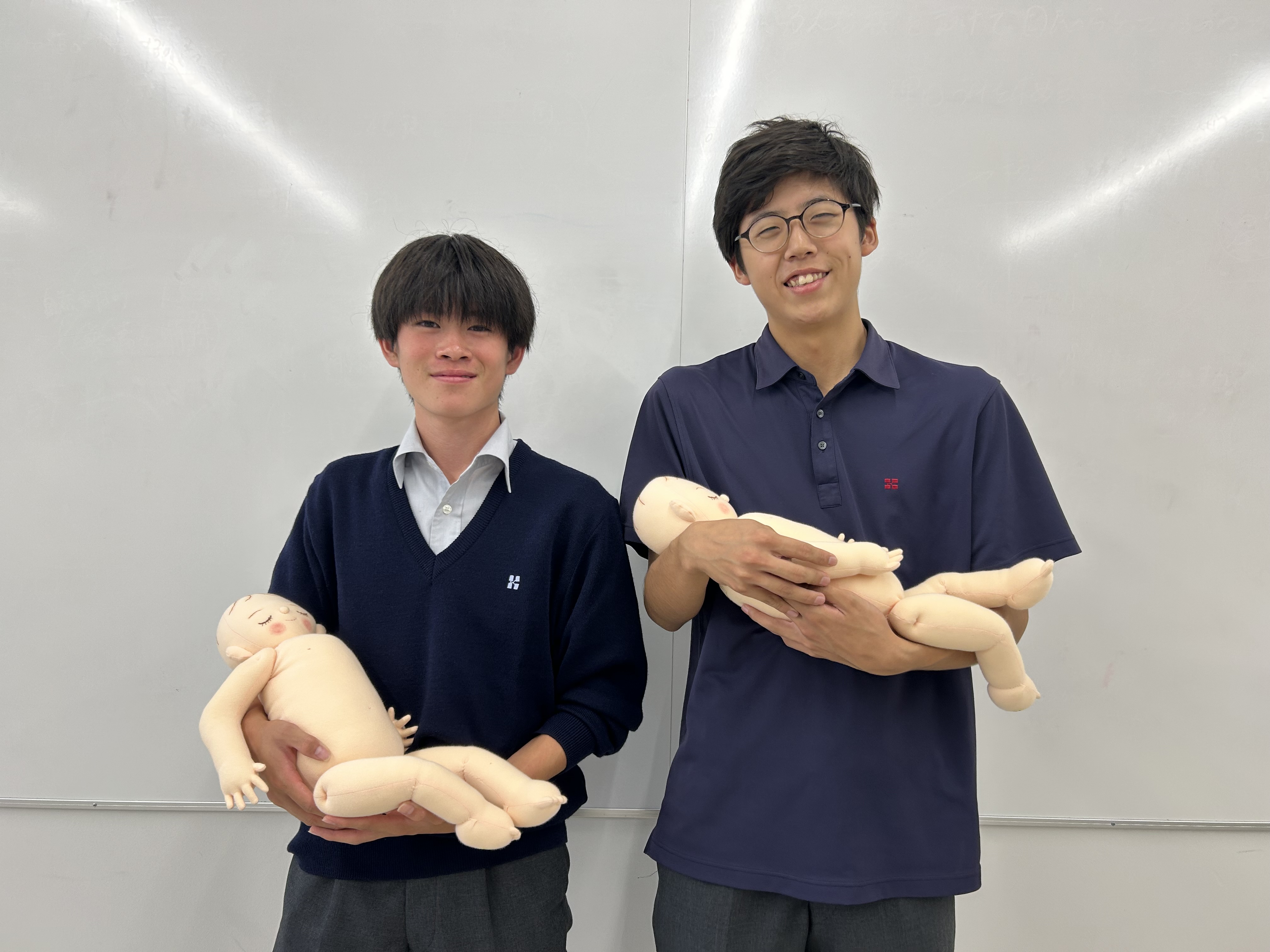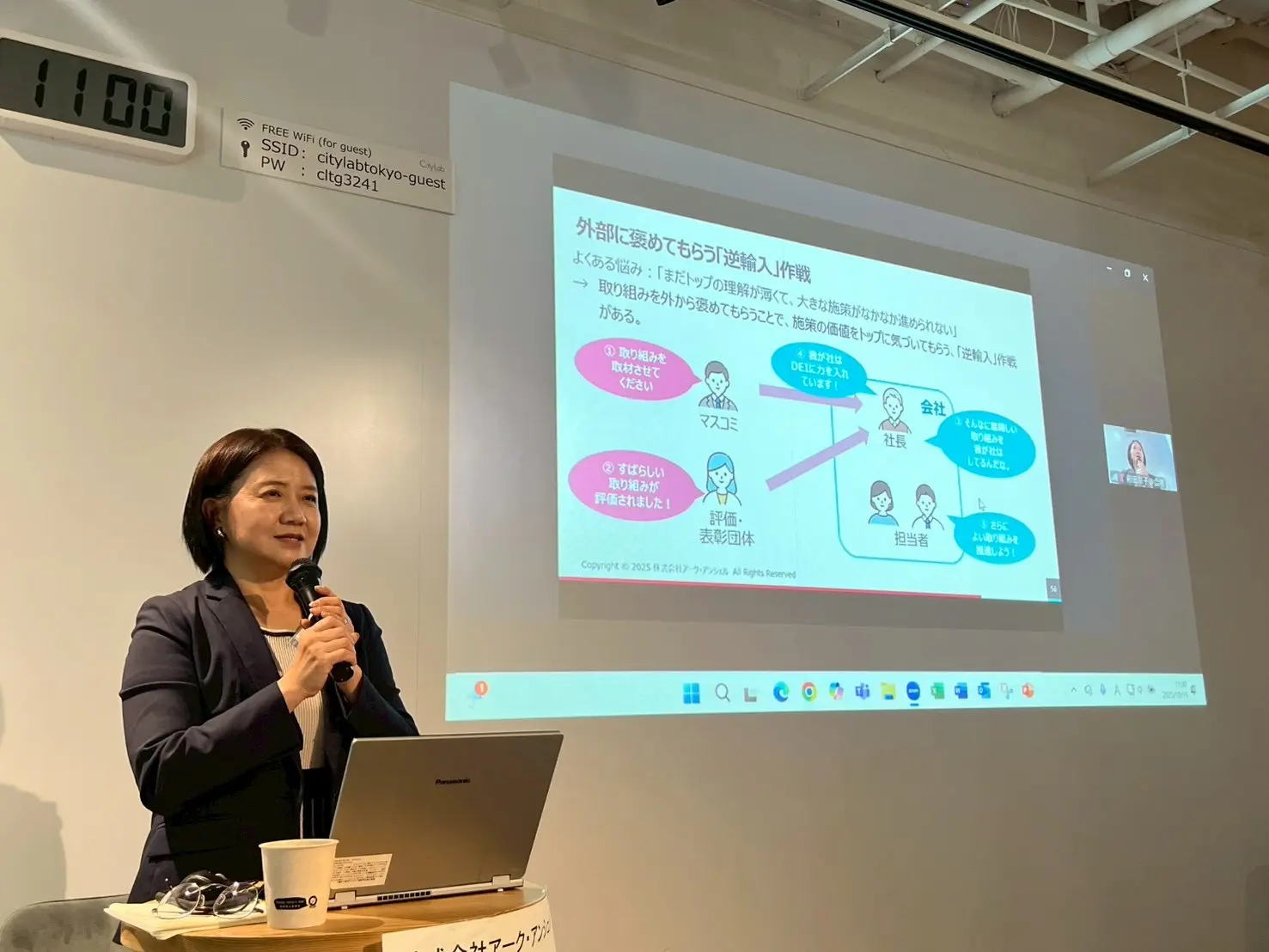「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(12)
船越は定年後、ひょんな縁から国際協力NGOで働いている。のんびり余生を送るつもりだったが、そんな甘い夢は妻の芳江に一蹴されてしまった。「ローンは残っているし、下の子は大学に入ったばかりなんですよ。生きていくためにもっと稼いでくれなくちゃ」。そう上目づかいに訴えられては返す言葉のあろうはずがない。
NGOでの仕事はファンドレイジング担当、つまり寄付集めをすることである。世知辛い時代だけにお金持ちでもそう簡単には財布のひもを緩めてくれない。米つきバッタよろしく平身低頭しても、個人だとせいぜい3千円、企業の場合は体よく追い返されるのが落ちである。なかなか骨の折れる仕事だ。どこかにポーンと気前よく大金を寄付してくれる大金持ちはいないものか、頭を痛める毎日だった。
そんなある日、事務所に年配の女性から電話がかかってきた。「3,000万円ほど寄付させてほしいのですが」。電話の主は遠慮がちに、いきなりそう切り出した。サンゼンマン、そう言ったきり、船越は声が出なかった。とにかくお話をうかがいたいということで会うことにしたが、家が狭いという理由で事務所近くの喫茶店が待ち合わせ場所に指定された。
大金を寄付しようという人だから、家が狭いというのは謙遜で、間違いなく資産家に違いない。うちのNGOは飢餓や貧困に苦しむアフリカの子供たちを支援しているから、そういう社会の問題に関心の強いインテリ女性だろうか。大口寄付者だから、会報で是非広報したいものだ。寄付税制の改正で確定申告すれば半額分は税金から還付されることも説明しなくては。船越は喫茶店で女性を待つ間、あれこれ思考をめぐらせた。そのせいか、当の本人が目の前に立っても声をかけられるまで気が付かなかった。小柄でやせた身体にグレーのカーディガンをはおり、スーパーの袋から大根がのぞいている初老の女性は白髪混じりの頭を気にしながらテーブルについた。船越は、その女性の話を聞きながら、段々、事情がわかってきて、寄付者というもののイメージを根底から覆されることになる。
――私は富子と申します。名前だけお金持ちみたいね。苗字は聞かないでください。ことしで七十五歳になります。父が若いころから大酒飲みで芸者遊びに明け暮れ家は貧乏でしたの。中学を出てすぐに働き質素に誠実にコツコツ生きてきました。3つ違いの義雄という弟がいて、私の給与で高校までは何とか出してやりました。私は働きづめで独身を通しましたが、まじめな弟はかわいいお嫁さんをもらって結婚し幸せそうでした。父が亡くなったあとは母を私が引き取りました。いつか、弟夫婦もいっしょに4人で暮らせたらとささやかな夢を育んでいました。
ところが母が心臓発作で急逝してしまったんです。本当につらかったです、身内は義雄だけになってしまったのですから。でも、もっとショックだったのは、幸せに暮らしているとばかり思っていた義雄が離婚したんです。嫁が新しい男をつくって出ていったの。まじめなだけが取り柄の石部金吉で、男として魅力に欠けたんでしょうか。義雄はやけをおこし人生を投げたような感じになり、ある日、勤務先の社長とぶつかってしまいましたわ。覚悟の喧嘩だったのか、すぐに辞表を出し退社しました。報われない人生なんですね、義雄も。その直後、弟を病魔が襲ったんです。長い闘病生活でした。そんな弟も昨年、両親のもとへ旅立ちました。病気の義雄は正直、私には重荷でした。でも、義雄がいたからこそ私は働き続けられたし、生きて来られたんです。最近、そのことに気がつきました。
私はとうとう天涯孤独の身になってしまいましたわ。困ったのは、義雄が残した家と貯金です。というのも、私自身が、身辺を整理し人生を終える準備にそろそろ取りかかろうかと考えていた時だったからです。自分のことだけでも大変なのに、突然、家やお金を残されても困るんです。人が一生に使えるお金なんて限度があるし、死ぬまでに施設でお世話になるにしても、経費は決まっていますからね。
それで何か形に残る生きたお金の使い方はないかしらといろいろ考え、人にも相談したんです。そしてあなた方のNGOを見つけたのよ。海外で貧しい子、エイズやマラリアで親をなくした孤児、学校に行けない子、医療を十分に受けれない子、そんな子どもたちのために活動している、あなた方には頭が下がります。本当に有意義な活動です。貧しかった私たちの幼少期に重なる子どもたちですよね。日本も終戦直後は貧しくて、私たちも子どものころはコッペパンひとつ手に入れるのも大変な時代だったわ。弟もつましい生活の中で少しずつ貯金していました。子ども好きでしたから。義雄も貧しくて学校に行けないような子どもを支援するということなら喜んでくれると思うんです、間違いなく。
富子の話に船越は心をうたれた。人を助けるということはこういう人がすることなんだと納得できた。団塊の世代に属する自分のほうがいくらか年下だが、終戦後の豊かでないころの記憶もいくらかは残っている。近くの藪になっているカキやいちじくが最高のおやつだったし、テレビのCMで流れるおいしそうなショートケーキを食い入るように見つめる弟妹を痛ましく感じたものだ。改めて富子を見ると、強い意思を感じさせる風貌のなかに品格を感じた。美しい、素直にそう思った。
「3,000万円はあすにも振り込みさせていただきますが、ひとつお願いがあります」
「はい、何でしょう」
「私たち、つまり、私と弟のことですが、対外的には名前は一切出さないということでお願いします。寄付があったこと自体も内緒にしてください。税務署とかマスコミとかに追いかけられるのは御免こうむりたいものですから」
事務所に帰るとスタッフに取り囲まれた。
「ねえ、ねえ、どんな女性だったの、大富豪? 芸能人?」
「成り金でしょう。株とか山林とか、違う?」
「いやいや、外資系の高給取りじゃないかな。アメリカ人なんか大金を寄付する人いるじゃない」
そんな周囲の喧騒に「残念でした。普通の人だったよ。ごく普通の地味な女性」とひとこと。きれいな人、という言葉は場違いなようで、飲み込んだ。
「なんだ、がっかり」。拍子抜けする事務所スタッフを無視して、自宅に電話を入れた。
「あぁ、芳江か、俺だ。きょうは早めに帰る。熱燗を1本、頼むよ」
「どうしたの、珍しいわね。いいわよ。だけど1本だけよ」と妻の渋い声が返ってきた。
ローンだ、教育費だと、家族の生活に追われる人生、それも悪くはないか。船越はカバンをひったくるようにして勢いよく立ち上がった。
(完)




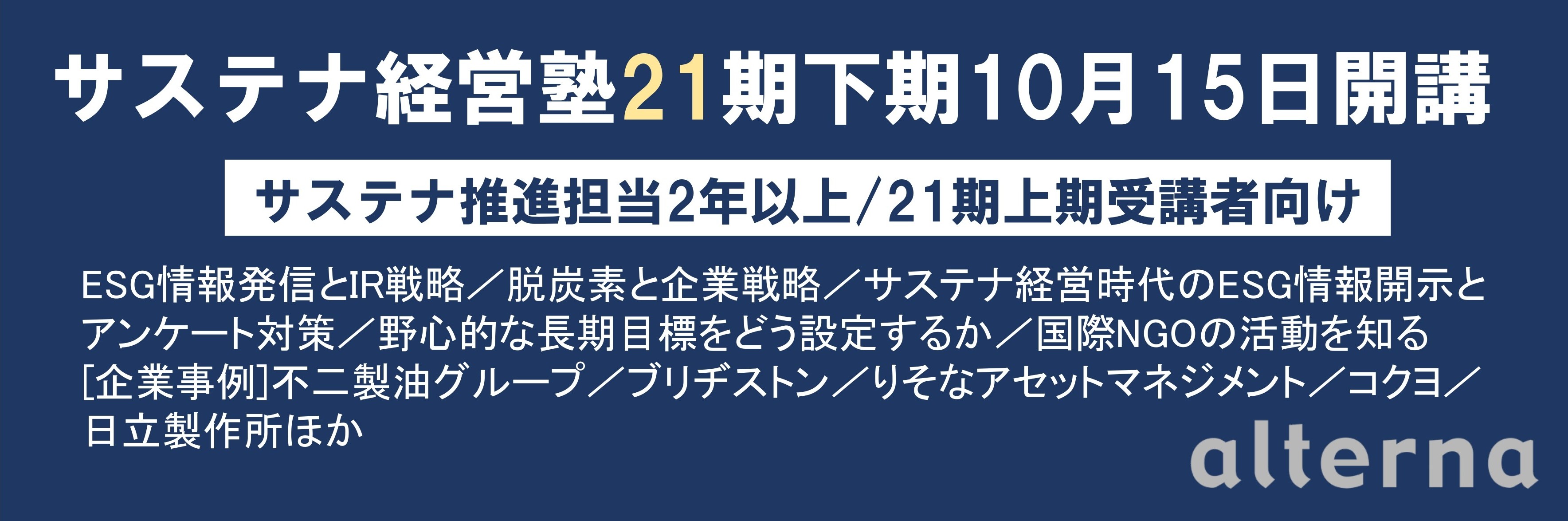








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)