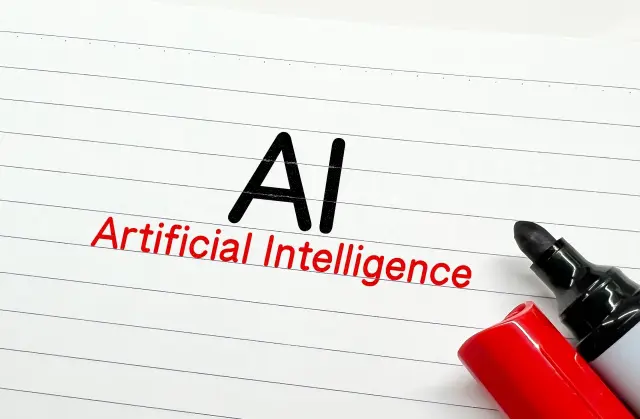■「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(65)

カウンターに一列に並ぶ黒い影。目を凝らすと何とカラスだった。六羽はいるだろうか。止まり木につかまり丸い目を細めて行儀よく寿司をつまんでいる。
「あいつらついに寿司屋までやってきたか。スポーツクラブを占拠してお風呂で行水するので人間が小さくなっていると聞いたが」とカウンターの端に座った夫婦連れの男がささやく。
隣の妻も「神はカラスの濡れ羽色というけれど、みんな九十九髪だわ。昔だった姥捨て山よね」。
ワオッこの穴子おいしい、と素っ頓狂な声が上がった。厚化粧の金持ちカラスがはしゃいでいる。「この店のお寿司大好き。シャリが小さくて食べやすいし握りのお任せも六貫からあってありがたいわ」。
「レストランだと一人じゃ敷居が高いしね」。こちらは九十五歳のしわくちゃカラスである。「夫に先立たれてからは食事を作るのも面倒だし出前も飽きたわ。週に一度、このお店でぜいたくするの。大将、いつもの、握ってちょうだい」。
「ヘーイ、毎度。トロですね。きょうはいい本マグロがはいっていますよ」。板前の声がはずむ。
「あなた、志賀直哉の『小僧の神様』読んだかしら」。九十五歳が金持ちカラスに尋ねる。
「確か、秤屋の小僧が寿司の屋台でマグロを食べようとするお話よね。ひとつ六銭だよと店の人に釘を刺され、いったん手に取った寿司を戻すんでしょう。かわいそうよね」
「そうなの。あんたみたいな金持ちにはわからないかもしれないけど、寿司は昔も今も高級品だから。親切な人がその小僧さんに寿司をおごってくれるの。でも、後日、小僧さんがその人の住所を尋ねてみると、そこには稲荷の祠があるだけだったの」
「寿司は神様から小僧さんへのプレゼントということね」
「私たちのお寿司も神様の贈り物?寿司への思い入れは小僧さんに負けないわ。私が三途の川を渡る日も近いけど、うちの子供達ったらちっとも家に寄り付かない。遺産なんてやーらない。全部寿司屋で使ってやるから」
「いいんじゃないの。あっ、いけない。また、金の入れ歯が外れちゃった」
二羽のカラスはマス酒で盛り上がっていたが、横の四羽は静かに寿司をつまんでいる。座席が一つずつ空いているところ見ると、連れではなくそれぞれが一羽ずつ来店しているようだ。
その時だった。勢いよく玄関の引き戸が開き太った高齢のカラスが飛び込んできた。羽毛はボサボサ、腰が曲がり足元もおぼつかない。杖を頼りにヨタヨタと歩いているもののあわてている様子。トイレを探しているようだ。ところが何かにつまずいて転んだ。その拍子にプッと大きな音がした。
「あら、いやだ。漏れてしまったわ、糞が」
思わず発したカラスの一声にみんな鼻と口を手でふさいだ。すると、さっきの男が突然立ち上がり怒鳴り出した。
「なんだ、お前ら。いい加減にしろ。ここは人間が来る店なんだ。カラスの分際で寿司とはいくらなんでも生意気じゃないか。そのうえ、糞までまき散らしやがって許さんぞ」
すごい剣幕にたじろぐかと思いきや、金持ちカラスが敢然と反撃に出た。
「あんた、すぐ怒鳴るのはボケの始まりよ。偉そうに言わないで。このお年寄りは脚が悪いのよ。見ればわかるでしょう。尾羽うち枯らしているからってバカにしないでよ。皆一人暮らしだから大変なの。孤独死したりガンになっても入院できない友達もいる。だから助け合って生きているのよ。それを何よ。あんたは他人への思いやりってものがないの?」
「そうよ、そうよ」。トロをほおばりながら、九十五歳が「カラスが増えている時代なんだから仕方ないわよ。デパートだろうが推し活だろうが、温泉だろうが、今はどこもカラスであふれているの。でもね、ちゃんと金を払っているんだから文句を言われる筋合いはないわ」
ほかのカラスも加勢する。「おじさん、SDGs知らないの?カラスにだって人権はあるのよ」
思わぬ諍いに板前はどうしたものか、オロオロしていたが、「まあまあ、皆さん、落ち着いて。おい、ともかく糞の掃除を」と従業員に指示しながら、その場をおさめようと必死だ。そして思いついたように、そうだ、あれ、あれ、と言いながら奥から何かを持ってこさせた。すぐさま、エイ、ヤッという掛け声とともに受け取った被り物に頭を入れた。
オーッという歓声があがった。お面のような顔に大きな目。そう、フクロウだった。
驚いた夫婦連れの妻が「森の哲学者ね」と感心したようにつぶやく。
カラスたちもみな感心したようにうなずく。
「おっ、結構受けたようですね。ありがとうございます。そうです。いかに懸命に生きるか、それが大切です。フクロウ博士を見習いたいものです。では、ご夫婦にはこれをかぶっていただきましょうか」うれしそうに板前は別の被り物を取り出した。
「ありゃ、これは何だ。奇妙な鳥だ」夫婦がお互いを指さして首をひねっている。
それはコウモリだった。
「コウモリは確か哺乳類じゃなかったかな」男が苦笑いしている。
「そう、哺乳類翼手目。でも今日は特別に鳥の仲間にしてあげるわ。鷹に敬意を表して鷹揚自若といきましょう」金持ちカラスが笑った。
板前がコップを片手に叫んだ。「トルストイも孔子も言っている。鳥類はみな兄弟。皆さんがいなければうちの店はやっていけません。感謝です。これからもよろしく。さあ、乾杯しましょう」
「そうだ、カンパーイ」
「カンパーイ、イエイ」
夜がふけ、カラスは帰っていった。カー、カー、バサ、バサ。しわがれた鳴き声と大きな羽音を残しながら、一羽、また一羽と夜空に弧を描きながら古巣を目指して飛んで行った。
「みんないずれカラスになるんだから」、板前が言った。うなずきながら男が妻を見ると、驚いたことに、その背中には黒々とした羽がニョッキリ生え始めていた。




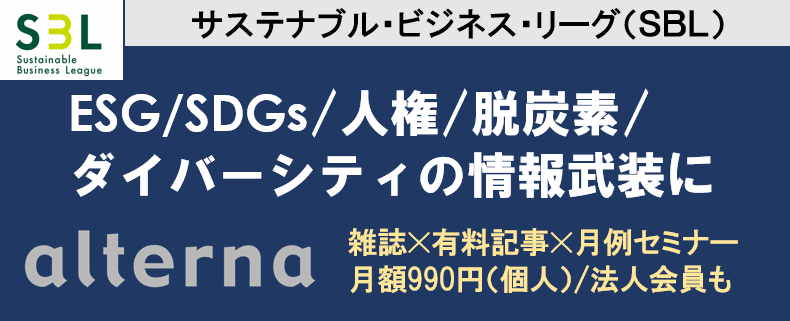




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)