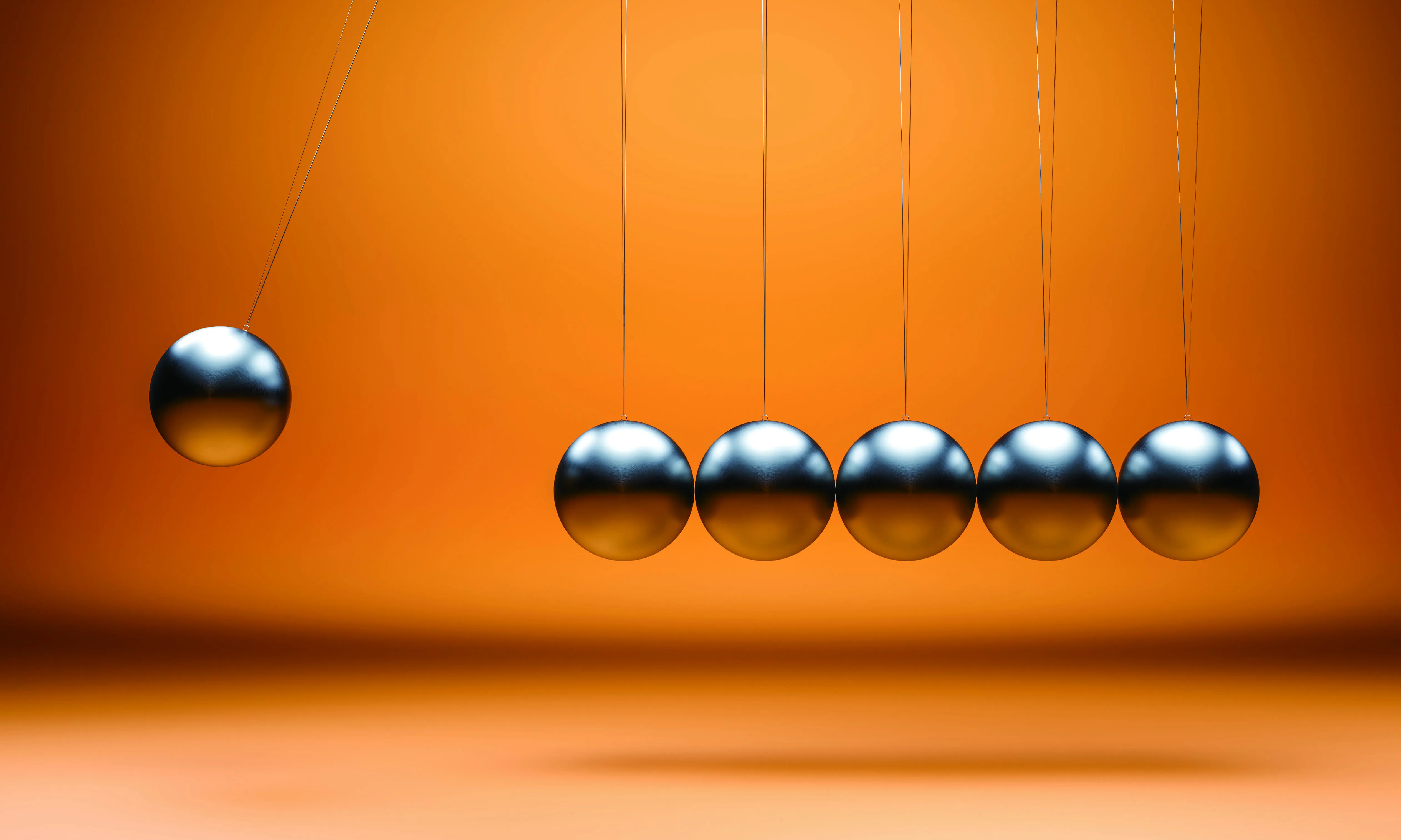「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(17)
田植えが終わり居間でのんびりしていた雅代のところに娘の玲子から突然電話が入ったのはほんの一週間前のことだった。
「お母さん、勇介が・・・」と叫んだきり、後が続かない。いったいどうしたの、と尋ねても嗚咽が続くばかり。ようやく落ち着いて、「きょう勇介を病院に連れていったら、難病だっていわれて。心臓弁膜なんとかという病名なんだけど、このままだと危ないのよ。でも、まだ小学校1年生だからね、手術なんて怖くて」
「そりゃ、えらいこっちゃ。とにかく上京すっから」
病院のベッドに横になっている勇介は、以前とは別人だった。たまに訪ねると玄関へ素っ飛んできたものだ。あのあふれるような生命力に満ちた底抜けに明るかった孫はいったいどこへいってしまったのか。今は、暗い眼をして不機嫌に黙り込んでいるばかりである。たまに口を開くと、「僕、手術なんか大嫌い。絶対にしないから」と挑むような言い方をする。
看病疲れの雅代がウトウトしていると、フロアの入口あたりがざわざわしてきた。この病棟は子どもの患者専用で、特に3階は難病の子が集まっている。一昨日、小児がんの子が亡くなった時もあわただしい動きがみられたが、きょうは何だろう。
廊下側は大きなガラス張りになっているので、雅代は何気なく入口の方に目をやった。そして思わず眉をひそめた。黄色の横縞のシャツにピンクと青のツートンカラーのベスト。虹色のパーマも嫌みだが、あの真っ赤な口紅に丸い大きな鼻・・・。それは紛れもないピエロだった。三日ほど前、婦長が突然部屋に入ってくるなり、こう切り出したのを雅代は思い出した。
「今度、ピエロが慰問に来てくれます。いえ、サーカスにいる本職ではなく、NPOの若い方なんですけどね。部屋まで来てもらいたいかどうか、皆さんの希望をお聞きしているんですが」
雅代は即座に答えた。「とんでもない。婦長さん、うちの勇介は重病なんですよ。笑っている場合じゃありません。ピエロなんて冗談じゃない。絶対にお断りします」。
明日の命もわからない難病に苦しむ子どもたちがいるというのに、お笑いのピエロでごまかそうなんて、とんでもない病院だ。そんなお遊びで子どもの病気がどうなるというのか。怒りで雅代の腹は今も煮えくりかえっていた。
その時だった。ハーモニカの音楽がきこえてきた。ピエロがリズミカルな調べに乗って主治医と何人かの看護師たちが両手を掲げて作ったブリッジを踊りながらくぐり抜けている。よく見ると、みんなプラスチックの赤い鼻をつけている。病状が軽い子どもたちがそれを取り囲んでキャッキャッと大はしゃぎだ。いつもは威厳に満ちているお医者さんや怖い婦長さんが急に身近になったようで、驚き半分、おかしさ半分なのだろう。
ピエロはそれだけで病棟の雰囲気をわずかだが確実に変えた。さっきまで、難病のフロアらしく重く沈んだ空気だったのに、さっと一条の明るい光が差し込んだようだった。よく見るとピエロは二人組で、先頭は男性で、ハーモニカを吹きながら楽しげに踊っている。女性の方は、後ろから男ピエロの腰に手を回していっしょにステップを踏んでいる。やがて、ピエロはひとつの病室の前で立ち止まった。あらかじめ、ピエロの訪問を依頼していた病室に違いない。女ピエロはドアを開けるふりをしてすぐ閉めた。今度はちょっとだけ開けるとそっと顔をのぞかせた。赤ちゃんをあやす時の「いない、いない、ばー」である。そんな単純な遊びでも中の子どもは大喜びである。いくらピエロの到着を楽しみにしているといっても、はい、来たよという感じですぐに部屋に押し入っても子どもの緊張は解けない。その固い心をほぐしながら、少しずつ関係性を作ろうという考え抜かれた手法のように雅代には思えた。
ハイタッチして部屋に入ったピエロは風船を飛ばしたり、手拍子をしたりで子どもも大喜びである。勇介もベッドで身体を起こしてガラス越しに観察している。ピエロが順番にいくつかの部屋を訪ねながらこちらに近づいてきた。にぎやかな気配と子どもたちが一体となって迫ってきた。勇介はもう窓にへばりついている。その背中が何かを訴えているように見えた。勇介、あんた・・・気がつくと雅代は廊下へ走り出していた。
「あの、ちょっと。すいません、ピエロさん。訪問をお願いしておりませんが、うちの孫のところにも来てもらえませんか。お願いします」
ピエロの男女は戸惑った様子で婦長と二言三言、言葉を交わしていたが、大きくうなずいた。女ピエロがベッドの上に座っている勇介の頭を軽くなでると勇介がにっこり笑った。孫の笑顔を見たのは、入院してから初めてである。男ピエロがリズムのある音楽をハーモニカで目いっぱい演奏している。勇介は音楽にあわせて手拍子をたたき身体全体でリズムを取ろうとしていた。
カシャ、カシャ。雅代は渡されたマラカスを振った。ピエロの手がすっと雅代の顔に伸び、赤い鼻をくっ付けられた。リズムははずれっぱなしだったが、目の前の勇介の身体に力がわいてきたことがうれしかった。ああ、勇介が笑っている。あんなにうれしそうに。カシャ、カシャ。まあ、大きな口を開けて。カシャ、カシャ、カシャ、カシャ・・・。腕が痛くなるほどいつまでもマラカスを鳴らした。気がつくと涙が頬を伝っていた。そして、止まらなくなった。女ピエロは出て行くと時、勇介に向かって「手術、うまくいくといいわね」と言った。
雅代は一階で待っていた。どうしても一言お礼が言いたかったからだ。
「きょうは本当にありがとうございました。ピエロと聞いて、お笑いかと誤解してしまいました。すみませんでした」
化粧を落とした女はきれいな人だった。
「病院は笑いとは対極の世界ですもの、お気持ちはわかりますわ。でもね、笑いの力って絶大なんですよ。赤い鼻ひとつプレゼントします」
男ピエロが丁寧に頭を下げた。「私たちは夫婦なんですが、幼い子供を病気でなくしましてね。だから、難病の子どもたちのことが人ごとには思えないんです」
次の日、キッチンで休んでいると、病院から帰って来た娘の玲子が駆けよってきた。
「勇介が手術受けてくれるって。よかったわ。元気になってサーカスに行きたいんだって。一体どうしたのかしら。あらお母さん、何? その赤い鼻、やあね」
(完)




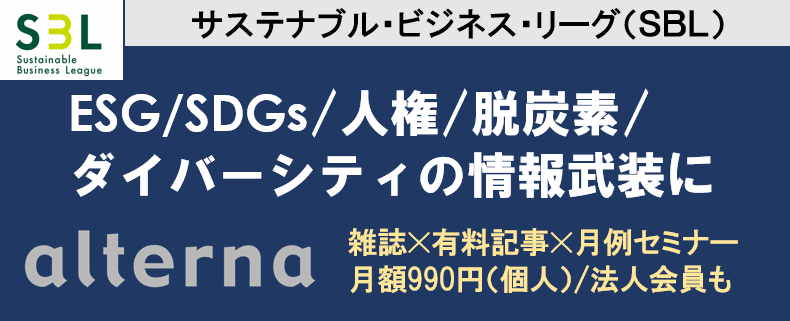























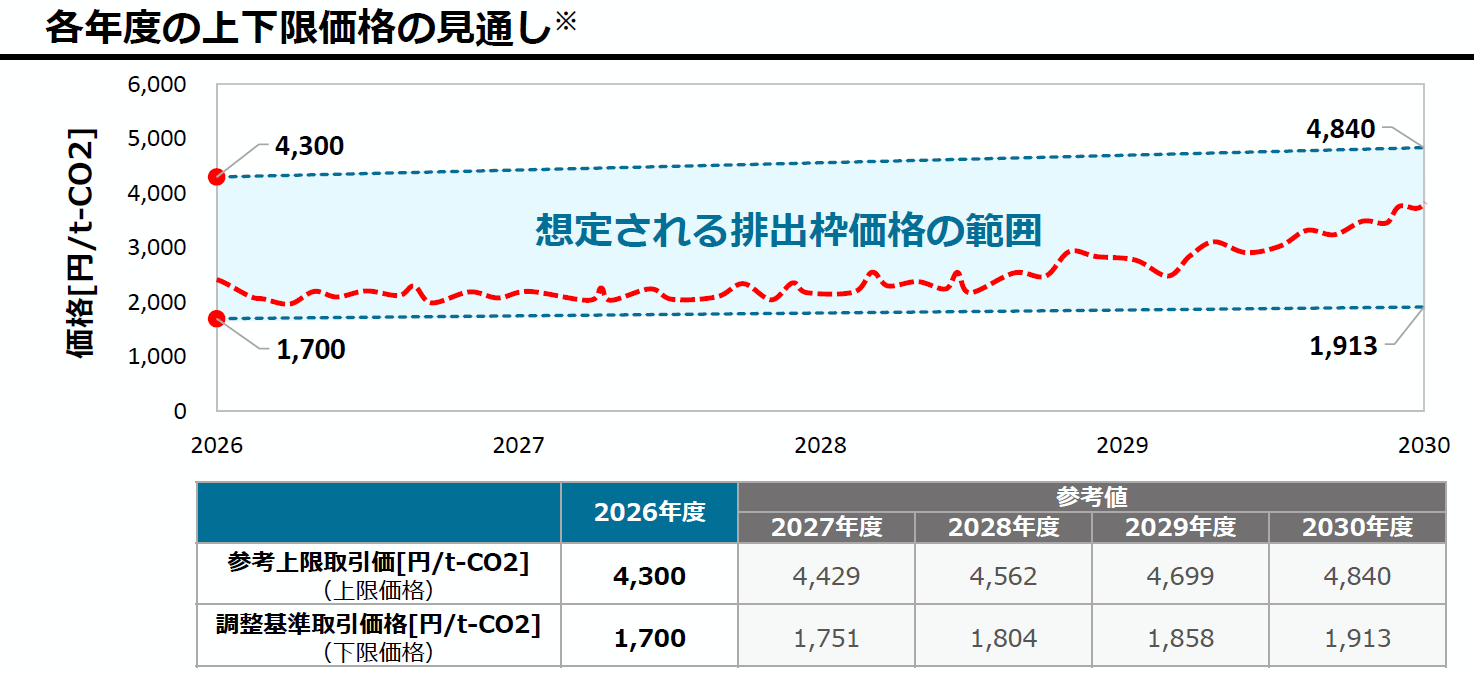
.jpg)