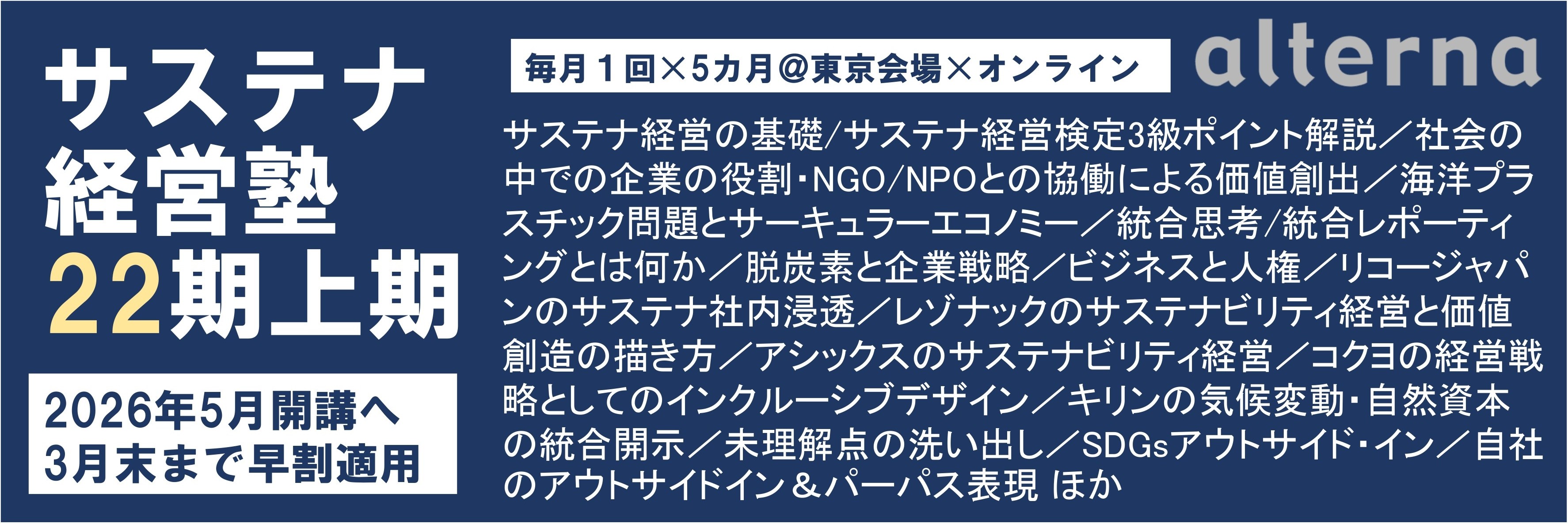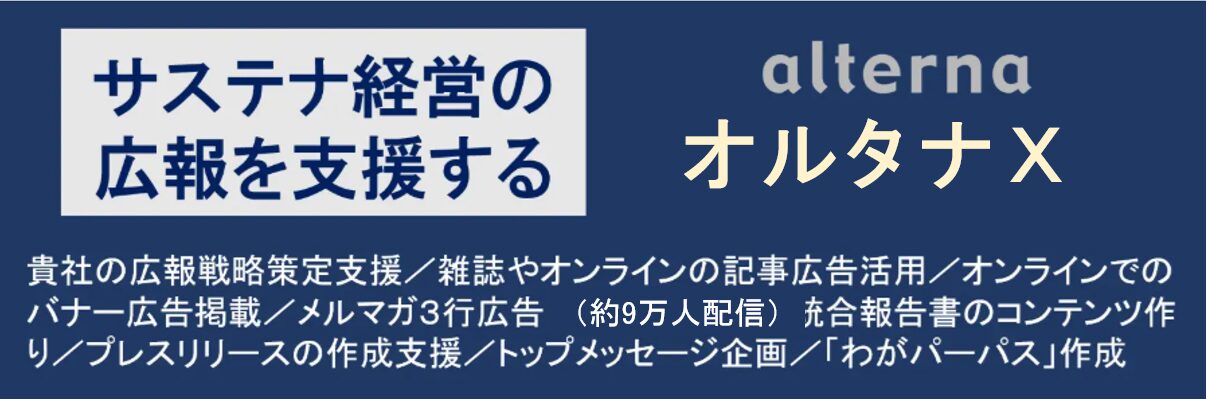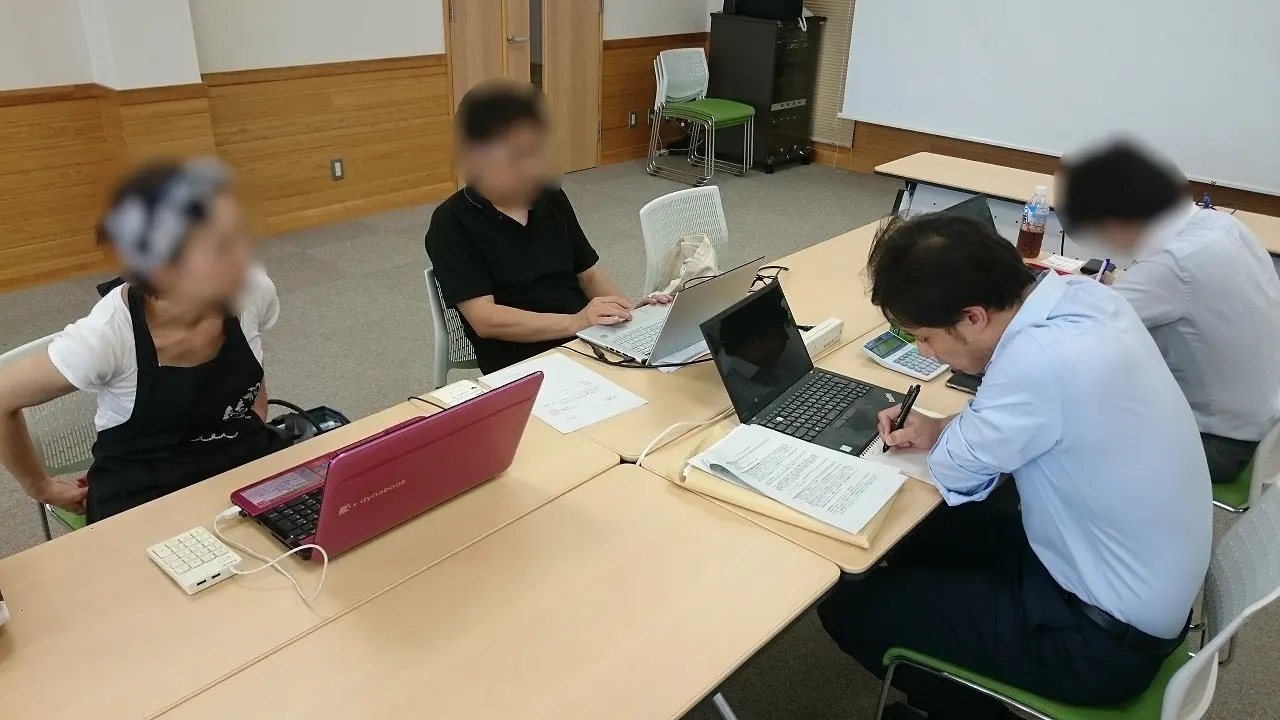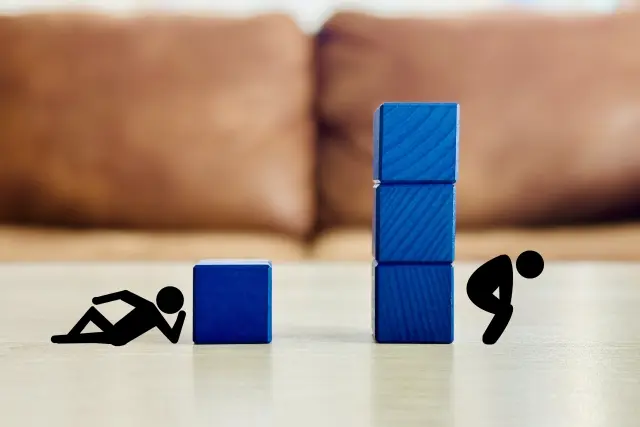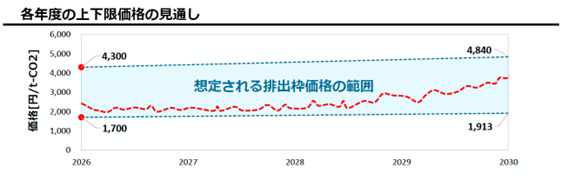私の勤める製薬会社に美人はいない。化粧品会社にでも就職すればよかったなあとずっと悔しい思いをしていたが、最近なぜか総務課でデスクの向かい側に座っている亜湖のことが気になって仕方がない。暑苦しかった大きな胸も不思議と女性らしく思えるし、極細のキツネ目もきりっとして好ましいのだ。
ある夜、研究室の梅本と居酒屋で一杯やることになった。同期だが、脱腸で巨大な陰嚢を持つ伝説の男である。
「山田君、職場の女性はどう」。梅ちゃんは長髪をかき上げながら探るような視線を向けてきた。
「なんだよ、唐突に。いや、実はな、亜湖っていう子、知っているだろう。気になってね」と打ち明けると、急に顔の表情が締まった。
「オー、効き目があるね。これはびっくり」
「効き目って、梅ちゃん、どういうこと」
「実はうちの研究室でホレ薬を開発したんだ。バイアグラとかイモリの黒焼きの類とは違う。これを頭からスプレーすると、あら不思議、最初に会った知り合いに狂おしいまでの好意を持つという秘薬だ。悪いとは思ったが、先日、ランチの後、カフェへ一緒に行っただろう。あの時、こっそり」
「俺に振りかけたのか。なるほど時期的にはぴったりだな」
「許せ、山田君。実験のためだ。この薬の効果は三週間だ。俺はカミさんに三週間ごとにこの霧を吹きかけて恋の森へ誘っているのだが、効果は絶大だぜ」
確かに、それから間もなくすると、効果が切れたらしく憑き物が落ちたように、亜湖が太った田舎娘にしか見えなくなった。
「あなたを灼熱の恋へと誘うさわやかミスト」という思わせぶりなキャッチフレーズのホレ薬はわが社の大ヒット商品になった。恋ミストのおかげで結婚できたという投稿がSNSにあふれ、売れに売れた。生産が追いつかずようやく商品が届いた販売店には長蛇の列ができた。
末期がんでもう長くないと医師から宣告されている父から、遺産の話をしたいから来てくれと連絡があり顔を出すと、突然怒られた。
「お前ほど気が利かないヤツはいない。ワシのことをもっと心配してくれてもいいだろう。もう遺産を分けるのはよす。お前の兄貴に全部くれてやる」
いつもは温厚な父なのにどうしたのかと合点がいかなかった。会社のトイレで一緒になった梅ちゃんにぼやくと、ささやかれた。
「山田君、それはイヤ薬のせいじゃないかな」
「イヤ薬?」
「もうイヤ、顔も見たくないと、百年の恋も一瞬で覚める薬を開発中なのだが実験段階で盗難にあってね。この薬をスプレーされると、急に周りの人に対して不信感が募り、人嫌いになるんだ」
週刊誌に「大手製薬会社が開発中だったイヤ薬が闇市場に流れ、高値にもかかわらず離婚希望者の間で奪い合いになっている」というスクープ記事が掲載された。父はこのイヤ薬を兄にかけられたに違いない。兄がギャンブルにはまっていることを私は知っている。母に聞くと私が行く直前に父は兄と会っていたという。間違いない。
一計を案じこちらから父の所へ出向いて、隙をみてホレ薬をシュッと一吹き。父に向かって、これまで育ててくれたことへの感謝と父の生きざまへの尊敬の念を言葉を尽くして丁寧に伝えた。すると父は前の時とは打って変わってやさしい態度で、「お前は父親思いだ。遺産はもちろん兄弟で分けてくれ」
兄に電話するとあせった様子で「そんなはずはない。遺産は全部俺にくれると約束したのに変だな。もう一度父に聞いてみよう」
先回りしてイヤ薬を天井から父にシュッ。そのまま聞き耳を立てていると父の怒声が響き渡った。
「兄のくせにお前は性格が歪んでいる。遺産はゼロだ」
イヤ薬は正式に発売されるとホレ薬を上回る勢いで爆発的に売れた。中にはホレ薬の効果で熱烈な恋愛の末に結婚したものの、冷静になって別れたくなった。そんな人も密かに購入したらしい。意外だったのは、幼児虐待やイジメ、家庭内暴力、パワハラ、殺人という社会事象がイヤ薬のせいではないかと疑われたことだ。街頭で外国人同士の集団暴行事件が起きた時も、イヤ薬の影響かと報道された。警察はこれ以上放っておけないとついに強制捜査に乗り出し、梅ちゃんは逮捕されてしまった。
権力の不当介入だと世論は盛り上がったが、捜査の過程で意外な事実が明るみになった。ホレ薬とイヤ薬を科捜研で分析したところ、なんの有効成分も発見されなかった。ホレ薬はただの砂糖水だし、イヤ薬は単なる塩水だったのである。会社は社長以下幹部が記者会見を開き平謝りだった。一方、梅ちゃんは取り調べで「恋愛なんて、そもそも思い込み。効果があるなら砂糖水だって本物でしょう」とうそぶいていると聞いて思わず笑ってしまった。父が私を許してくれたのは薬のせいではなく、不誠実な私が態度を改めたからに違いないと今にして悟った。
となると、亜湖のことはどうなるのだろう。もともと私は彼女を憎からず思っていたということか。思い悩む何日間を過ごしていたある日、会社の近くで亜湖を見かけた。彼女は猛烈な勢いで走っていた。手に何かをささげ、「待って、おばあちゃん。財布落としましたよ。ほら、これ」。あたりをはばからぬ大声で形のいいお尻を躍動させ胸ははじけんばかりに揺れている。すごい迫力だ。しかし、人柄の好さが伝わるのだろう。周囲の人も温かい目で見守っている。おばあちゃんがようやく財布を手にするとパチパチと拍手が沸き起こった。私も思わず手をたたいた。
亜湖は今、私の隣にいる。結婚したのだ。媒酌人はもちろん梅ちゃん夫妻にお願いした。多くの人が「あの薬は本物だった。ありがとう」と署名をしてくれたおかげで梅ちゃんは意外に早く刑務所を出られた。梅ちゃんの奥さんは何を言ってもニコニコしている天使のような人である。(完)
4o