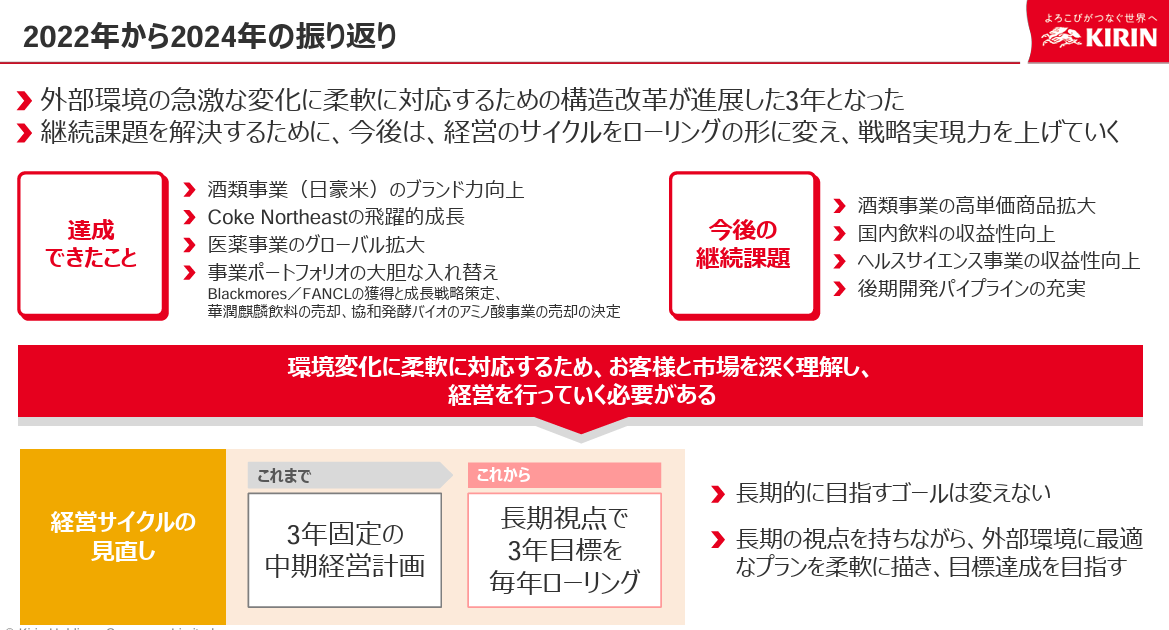株式会社オルタナは2025年4月16日、「サステナ経営塾」21期上期第1回を都内会場・オンラインで開催しました。当日の模様は下記の通りです。
① サステナ経営検定3級テキスト ポイント解説
時間:10:40~11:40
講師:森 摂(株式会社オルタナ 代表取締役・オルタナ編集長)

第1講には、オルタナの森摂代表取締役から、サステナ経営検定3級テキストのポイント解説を講義した。
・最初に、サステナ経営の目的と領域(3級テキストP.10)とサステナ経営の最重要ワードであるステークホルダー(同P.38)について触れ、将来世代や自然環境など「声なきステークホルダー」も含まれることを理解することが重要とした。
・2級テキストより、3級テキストの方が詳しい項目として「コンプライアンス(狭義と広義)」「ステークホルダー/ステークホルダーエンゲージメント」「NGO/NPOの存在」「国連グローバル・コンパクト」「世界の貧困と児童労働」を紹介した。
・特に、「コンプライアンス」(同P.20)」については、「サステナ経営の4つの領域」(同P.112)の図とともに、法的制裁を伴う「ハードロー」だけでなく、法的責任を問われなくても「ソフトロー」を守ることの重要性を歴史や複数の企業事例とともに概説した。
・また「サステナ経営の4つの領域」の図に関連して、SDGsの公式用語である「アウトサイド・イン」の概念について、その概念図とともに紹介。既存顧客にリーチするマーケットイン・アプローチと、社会課題を解決して価値を創出することで未来顧客にリーチできるアウトサイド・イン・アプローチがもたらす事業機会を、企業事例とともに説明した。
・またCSR/SDGs/ESGの基本的な理解とともに歴史的経緯を振り返り、どこからの要請なのかが異なると説明した。CSRは社会全体から、ESGは投資家・株主から、SDGsは国連・各国政府・NGO(非政府組織)からの要請ということで国際社会からという違いがありながらも、この3つを合わせて「サステナ領域」、統合報告書などでは「非財務領域」というと解説した。
・ESGに関しては、「E」の一丁目一番地は「脱炭素」、Sは「人権」、Gは「企業統治、内部統制、取締役会の機能・あり方」などがあるが敢えて「DEI」とし、DEIに最近概念として入ってきたEquity(公正性)について、図(同P.66)とともに解説した。
・その他の重要用語として、「マテリアリティ」については、最近は「マテリアリティ」という用語を使わない企業も出てきた事例とともに紹介した。「エンゲージメント」についても「歯車のかみ合わせ」という語源を鑑み、「中長期的な信頼関係を構築すること」と定義した。
・サステナ経営の転機は今からちょうど10年前の2015年だとして、CGコード、SDGs採択、GPIFのPRIの署名、英国現代奴隷法施行、パリ協定の採択など、サステナビリティの転機の年になったと紹介した。
②CSR/SDGs/ESGの基本的な理解
時間: 13:00~14:20
講師: 森 摂
第2講では引き続き森が登壇し、「CSR/SDGs/ESGの基本的な理解」について解説した。主な内容は下記の通り。
・サステナビリティの推進は、コフィー・アナン元国連事務総長(在任: 1997~2006)から本格的に始まった。アナン氏の「4つの贈り物」として、国連グローバルコンパクトやMDGs、国連責任投資原則、ビジネスと人権指導原則がある。
・その一方で、米トランプ大統領の就任後、反ESGの動きが加速している。政権発足後、エクエーター原則やNZBA(ネット・ゼロ・バンク・アライアンス)といった気候変動対策のイニシアティブから脱退する企業が相次いだ。なお、イニシアティブは「呼びかけ」という意味で、他者と協働して目標の達成を目指すことを指す。
・トランプ政権は米国のこれまでのDEI(多様性・公平性・包摂性)政策も否定する。米国では1960年代の公民権運動を背景に、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)が実施されてきた。20年のBLM(ブラック・ライヴズ・マター)運動から、DEIの「E」(エクイティ)の概念も広がった。
・しかし、米連邦最高裁は23年6月、人種を考慮することは「法の下の平等」を定めた憲法修正14条に違反すると判断した。1978年の最高裁で容認してから45年ぶりに判決を覆すなど、DEIを巡っては60年以上せめぎ合いが続いている。
・「E」(環境)では、気候変動の基礎知識に触れつつ、対策の重要性を説いた。気候変動は予測より10年早く進んでおり、24年の世界の平均気温は産業革命前と比べて初めて1.5℃以上の上昇幅を記録した。各国が脱炭素目標を達成しても平均気温を1.5℃以下に抑えられないという予測もあり、さらなる取り組みが求められる。
・「S」(社会)では「ビジネスと人権」に焦点を当て、児童労働や強制労働の問題に触れた。例えば東南アジアのパーム油の生産では、児童労働が大きな社会課題になっている。アフリカの紛争鉱物など、企業のサプライチェーンの上流で人権が侵害されている現状がある。
・「G」(ガバナンス)の原義はイタリア語の「guberno」(舵を取る)という意味で、進むべき方向性を指し示すという意味合いがある。ダイバーシティの推進はガバナンス課題でもあり、女性役員比率の高い企業の株価は好調というデータもある。
・企業のパーパス(存在意義)には、収益性といった経済価値の実現に加え、社会の繁栄への視点が欠かせない。サステナビリティ経営では、経済的・社会的価値を両立し、持続可能な社会の実現を目指す。
・例えば、オムロンは「ソーシャルニーズ創造」に取り組んできた。社会からの声を聞くことで、業界初の製品を多く生み出してきた。森は、「社会ニーズに対して取り組むことで、未来の顧客をつかむことができる」と呼びかけた。
③ワークショップ: 未理解点の洗い出し
時間: 14:35~15:55
講師: 森 摂(株式会社オルタナ代表取締役社長)
第3講では、「未理解点の洗い出し」をテーマにワークショップを実施した。主な質疑応答の内容は下記の通り。
・「社内浸透」や「情報発信」について、多くの質問が出た。「社内浸透」についてはサステナビリティに取り組むことの重要性をどう経営層に理解してもらうかや、サステナビリティ経営の目標を社員ひとりひとりにどう落とし込んでいくかといった点に関心が集まった。
・経営層に理解してもらうための手段として、森は「サステナ経営に取り組むということは、ブランド戦略であり、顧客戦略であり、人材戦略である」と指摘する。サステナ経営は「自社をサステナブルブランドとして全てのステークホルダーの信頼を勝ちとること」「顧客からのサステナ課題への対応要求に応えること」「より優秀な人材を採用し定着率を向上させること」の3つを可能にする。
・社員ひとりひとりの落としこみについては、「サステナ経営にKPIとKGIを設定してそれを業績評価に組み込んでいくことや、マイパーパスを設定させることが浸透に向けた取り組みとして有効だ」とアドバイスした。
・情報開示では「それぞれの課題への取り組みについて発信する際に優先度をつけるべきか」という質問がされた。これに対して「細則主義ではなく原則主義で取り組むべきだ」と指摘。コーポレートガバナンスコードでは、できることはコンプライし、できないことは説明するという「コンプライ・オア・エクスプレイン」であることを紹介し、「広報戦略も網羅的ではなく絞り込むことが大事だ」とした。
・また欧州と日本のサステナ意識の差についての質問も出た。森は「たとえばPFASについて、世界では規制が進むが日本では対策が後手に回っている。将来被害者が起こるかもしれないという『予防原則』が欠けている」と指摘。こういった差が出ている背景は不明であるものの、「この30年で世界と日本の差は大きくついたし、それがGDPにも表れているのでは」とした。
④サステナビリティの社内浸透
時間: 16:10~17:30
講師: 新井繁邦氏(リコージャパン株式会社経営企画本部ESGセンターESG推進部 部長)
第4講には、リコージャパンの新井繁邦・経営企画本部 ESGセンター ESG推進部 部長が「リコージャパンのサステナ社内浸透」について講義した。主な講義内容は次の通り。

・リコーグループは、創業当初から社会課題の解決と事業成長の両立を目指してきた。創業者、市村清は1946年に「三愛精神(人を愛し 国を愛し 勤めを愛す)」を提唱。「世の中の役に立つ事業をすれば、自ずと収益はついてくる」という考えは、創業時から受け継がれてきているという。
・同社は1970年代に環境活動を始め、1998年には桜井正光社長(当時)が「環境経営」という考え方を提唱した。環境問題への対応を事業成長の機会ととらえ、環境保全と利益創出の同時実現を目指した。
・リコーグループは現在、「財務目標」と並んで将来財務として「ESG目標」を経営目標として設定し、「ESGと事業成長の同軸化」を推進している。第21次中期経営計画では、7つのマテリアリティ(重要課題)に紐づく16のESG目標を設定した。具体的な目標は、「顧客からの評価」「GHG(温室効果ガス)削減率」「再エネ比率」「低コンプライアンスリスク グループ企業比率」「女性管理職比率」などだ。
・リコーはサステナビリティ経営の推進に向けて、ESG目標を役員報酬制度にも反映させている。2020年度からは、役員報酬(個人賞与額)に、2023年度からは取締役株式報酬に、2024年度からは役員株式報酬にESG目標を連動させた。16のESG目標の達成数で評価する。
・リコージャパンのESGの取り組みとして、マテリアリティの1つ「『はたらく』の変革」では、デジタル技術でオフィスや現場のワークフローを効率化し、顧客の生産性向上を支援する。例えば、コロナ患者を受け入れる病院では、電子ホワイトボードを導入し、スタッフ間の情報共有をリアルタイム化した。
・「脱炭素・循環型社会の実現」に向けては、再生可能エネルギーの導入に加え、再生プラスチック使用率50%以上の複合機の開発・販売やトナーボトルのリサイクルなどを進めた。リコージャパンの新設の事業所は、原則ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を進めている。
・リコーグループはサステナビリティの社内浸透にも力を入れる。毎年6月を「リコーグローバルSDGsアクション月間」として全社員に具体的な行動を促すほか、2020年からは、スキマ時間の10分でSDGsやESGについて学ぶ動画シリーズを展開する。
・リコージャパンでは、2018年に「SDGsキーパーソン制度」を発足。全国の支社で、SDGsに関する知識を持つキーパーソンを育成し、お客様とともにSDGsに貢献することを目指す取り組みだ。手挙げ制で募集し、現在、キーパーソン約750人が全国で活躍している。2024年7月には、「SDGsキーパーソンPro(プロ)制度」を立ち上げ、自社だけでなく、顧客のSDGs・ESG推進を支援することに力を注いでいる。
・新井氏は「SDGsキーパーソンの中で『何も活動しない人』の登録を防ぐために、はじめに、社内や社外での役割を明確にするようにしている。役割を明確にすることで、キーパーソン全体のレベルアップを目指す」と説明する。
・こうした社内浸透施策の結果、国内外グループ会社の97.7%の社員が「SDGsと自身の業務のつながりを感じている」と回答した(2021年3月時点)。さらに、「社会課題解決(SDGs/ESG)への取り組みは、はたらき甲斐や誇りにつながっていると思いますか」というアンケート調査には、91.6%が、「思う・少し思う」と回答した(2024年4月)。
・新井氏は、「エンゲージメントスコア(ES)が向上することも、ESGへの取り組みの大きな成果だ」と話す。「SDGs/ESGの推進は、経営課題であり、経営層と現場が一体となって取り組む必要がある。SDGs/ESGに関する取り組みは、5年後、10年後の将来財務を生み出し、社員に『はたらき甲斐』を感じてもらうためにも不可欠な活動だ」と強調した。