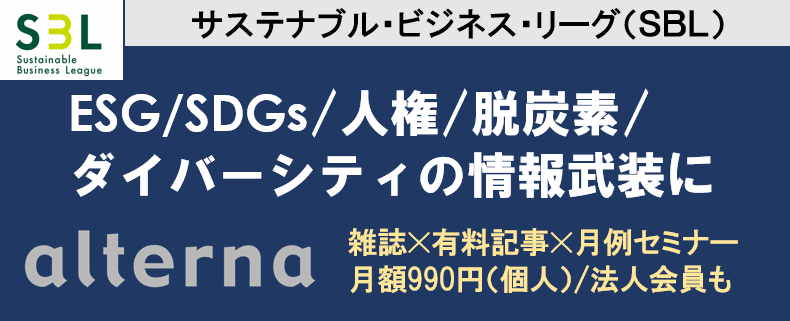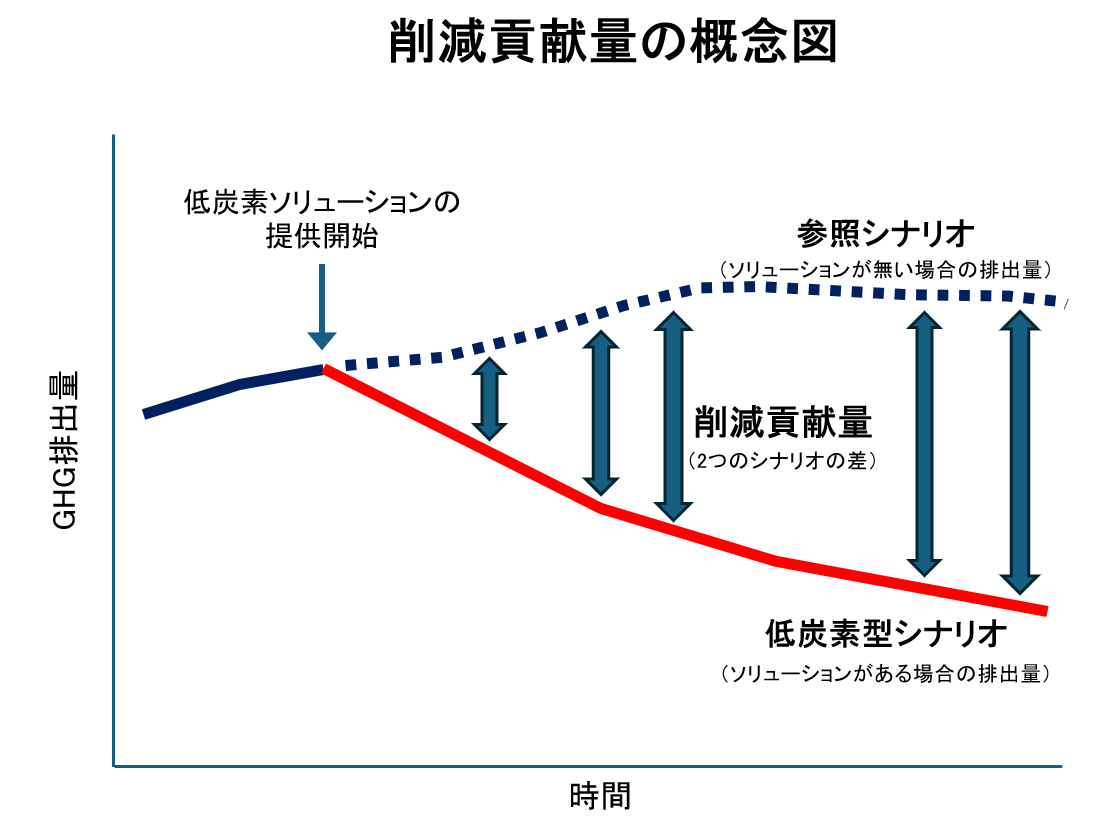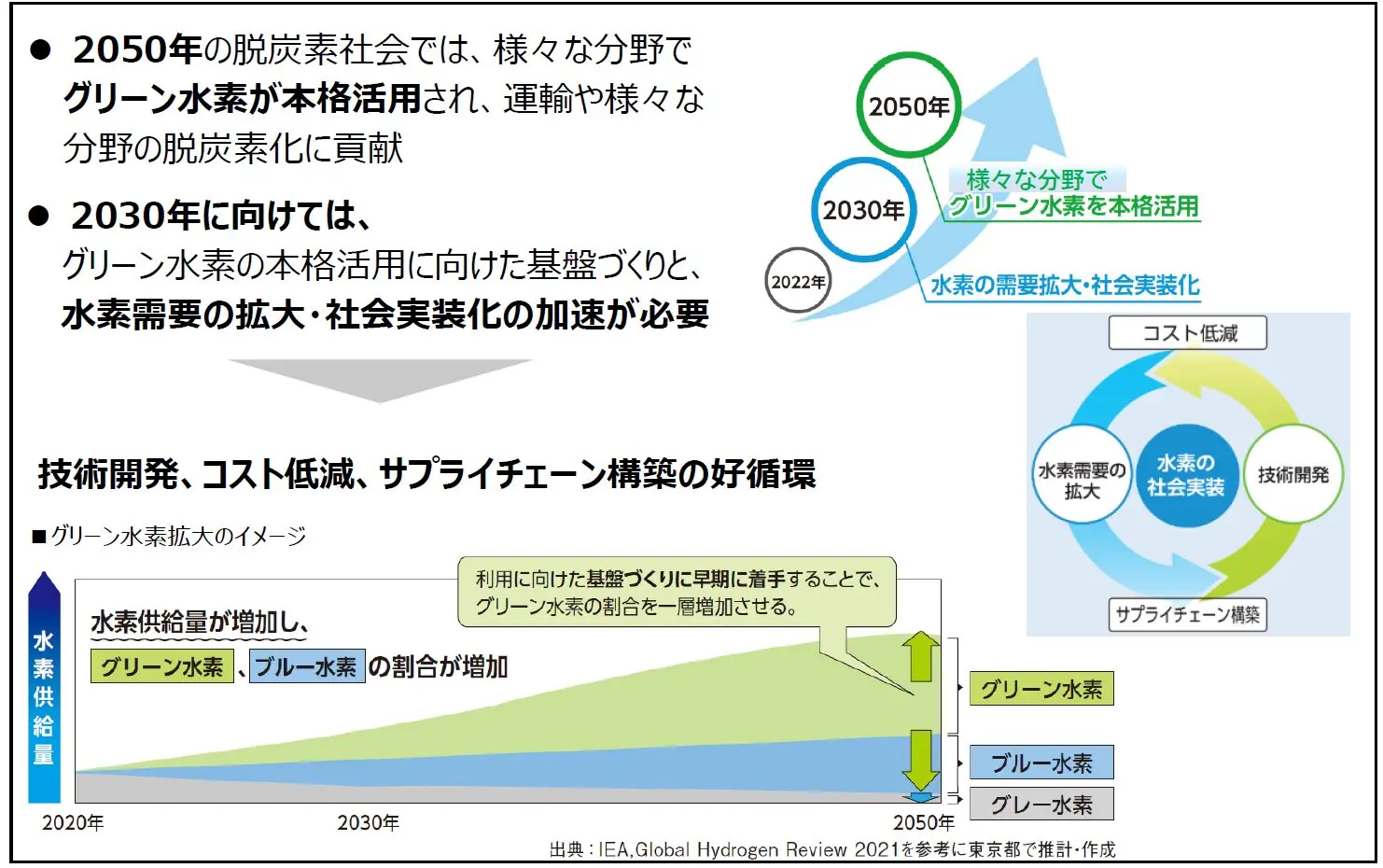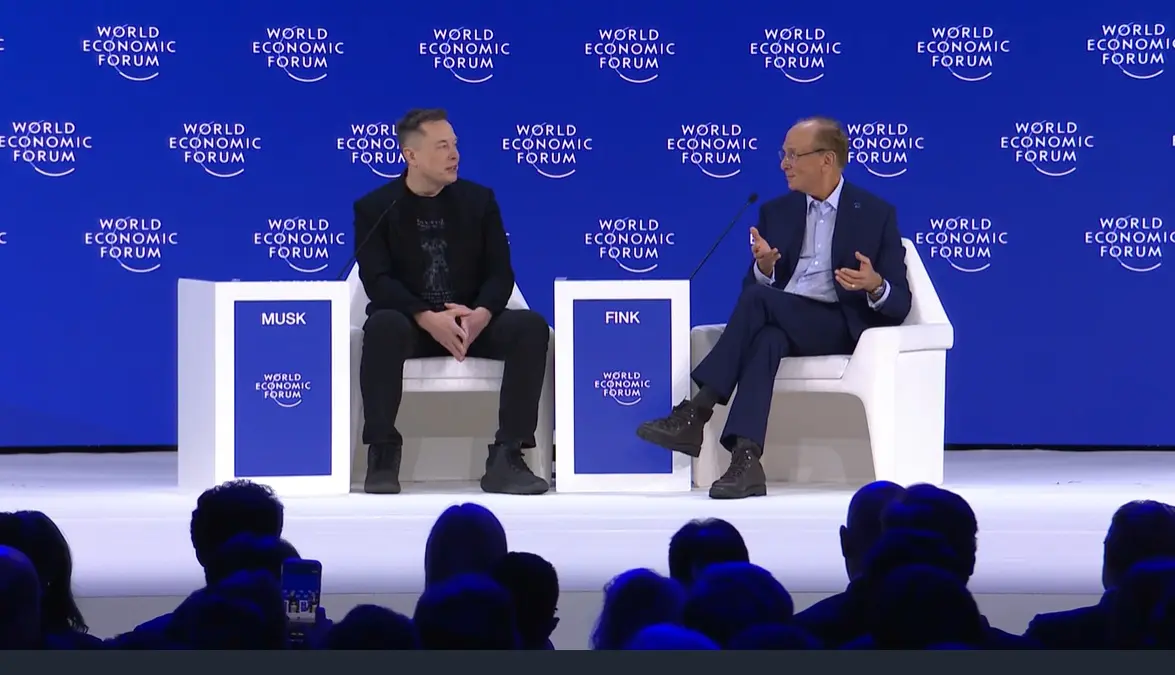■フラッシュ・フィクション「こころざし」の譜(45)
新聞社を定年で退職して以来久しぶりの同期OB会だというので出かけてみた。日比谷公園を見下ろすビルの高層階にあるレストランに二十人ほどが集まった。白髪が目立つ男たちの退屈な集まりだが、浦野が楽しみにしていたのは槇原との再会だった。
現役時代、特に親しかったわけではない。むしろその逆だ。人を押しのけるような仕事ぶりや上司への上手な取り入り方、一方で青筋立てての後輩への厳しい叱責ぶりには反発を感じていた。不思議なことだが、そういう男に限って出世するものである。いつの間にか、青唐辛子のハラペーニョが槇原のあだ名になったのも納得がいく。
そんな槇原の謎めいた噂話を聞いたのはいつのことだったろうか。彼は引退する時、論説委員を務めていた。社説を担当する記者としては最高のポストである。ところが、リタイアしてしばらくたったある朝、かつて自分の居場所だったイスにぽつねんと座っているところを出社した後輩が発見したのである。後輩はとまどいながらも声をかけた。「お早いですね、槇原さん。今日は何か御用でも」。
振り返った槇原の目は焦点が合っていなかった。無言で原稿用紙を取り出すと、慌てた様子で鉛筆を走らせながらつぶやいた。「静かにせんか。もう締め切り時間だ。忙しいから邪魔をするんじゃない」。
あのハラペーニョのことだ、何かの嫌がらせかもしれないと社内はざわついた。しかし、どうやら認知症のせいらしいと分かり、一件落着したそうだ。
その槇原が最近すい臓ガンを発症したと聞いた時、浦野の胸には苦い思いがこみ上げた。若手記者のころだが、槇原が秘書課の香澄と結婚すると分かった時、同期と語らって唐辛子のドライフラワーの花束を贈ったことがあったからだ。
香澄は当時、若手記者にとってマドンナ的で、正直に言えば浦野も密かに思いを寄せていた。よりによってあのハラペーニョと結婚するとは。皆、嫉妬し、憤り、そして毒のあるいたずらを思いついたのだった。

しばらくして唐辛子の辛味成分、カプサイシンがガンを引き起こす危険性があるとニュースで知った時は複雑な思いだった。ちょっとした冗談のはずが、重大な結果を招いてしまったのかもしれない。槇原のすい臓ガンの報に動揺したのにはそういう背景があったからである。
その槇原が珍しく同期の集まりに顔を出すという。浦野が参加することにしたのは当然である。あの尊大だった男がボケて、しかもガンを患っている。どんなみじめな様子でやって来るのか、見てやりたいという意地悪な欲望を抑えることができなかった。
一方で唐辛子のプレゼントを覚えているかどうかも気になった。忘れてしまっているかもしれない。それならそれでいいのだが。 注目の主は着古したトレーナに身を包み車椅子を押されて現れた。若いころは偉丈夫だったがすっかりやせ細り頭も禿げ上がって昔日の面影はない。表情もぼんやりして生気がなかった。順に近況報告が続き槇原の番になった。声は小さく弱々しかった。
「私は若いころに両親に死なれまして弟妹三人を育てあげるのに必死だった。仕事は辛かった。それでも上司にも仲間にも恵まれ何とかやってこられた。みんな、ありがとう」と声を詰まらせた。ボケは進行しているが、過去の記憶はしっかりしているようだ。
「実は認知症なんだ。この病気はいいね。嫌なことをすべて忘れられる。学生時代に腎臓ガンを発症したことがある。もう大丈夫かと思っていたら、この歳ですい臓に転移してしまった。でも薬で治った。ありがたいことに寛解したのです。日暮れて道遠し、の心境ですが、人生は一度きり。どんな道を歩もうとも最後は川が海に注ぐように皆、死の世界に流れこんでいくわけです」
槇原がねえ、嫌な奴とばかり思っていたが、苦労人だったんだ。ガン発症は学生時代か。会場のあちこちでそんなささやきが漏れた。
「今日はプレゼントがありますの」と突然、車椅子を押してきた老婦人が手提げ袋から小さな瓶を何本か取り出した。「皆様お久しぶり。槇原の家内の香澄です」。
エッ、香澄、まさか。老けたなあ。全員が目を丸くしている。
「わが家の庭で栽培している弥平とうがらしをお持ちしました。滋賀県湖南市で古くから作られてきたもので、鷹の爪の倍の辛さがあるの。こちらはバングラデシュ産で、ゴム手袋がないと収穫できないほど強烈な辛さのブートジョロキア。もちろんメキシコのハラペーニョも持参したわ。夫のニックネームですから大好き。唐辛子の辛味のもとであるカプサイシンはガン細胞のミトコンドリアのタンパク質を結合し、ガン細胞を殺してくれるんですよ。知っていました?」
槇原は疲れたということで、途中で退席することになった。そこここで別れのあいさつをしながら車椅子で移動している。出口近くで談笑していた浦野のところで止まった。
槇原は上目遣いに浦野を見上げた。いくらか顔つきが険しくなっている。香澄が夫の肩に手を置き「あなた、覚えているでしょう。浦野さんよ」。
槇原は相好を崩し「そうでしたね。久しぶりなのでうっかりしました。その節はお世話になりました。今日はこれでお暇しますが、どうぞお元気で」と頭を下げた。
隣の香澄が「結婚した時の唐辛子の贈り物、あれ、浦野さん、あなたの発案だったそうね。 槇原は人を恨まず病気に負けず、人生を前向きに生きてきたのよ。本当に一生懸命に」。
槇原は、別れ際、あ、そうそう、これプレゼントするよとのんびりした声で言って唐辛子の瓶を手渡した。香澄が「ギネスブックに載っている世界で一番辛いイギリスのドラゴンズ・ブレス・チリよ」といたずらっぽく笑った。
家に帰って好物のウドンにかけてみた。辛いというより痛い。体が一気に温かくなり頭から熱気が立ち上るようだった。
ふと、ぼんやりした槇原の顔とともに、頭から湯気を立てるという言葉が思い浮かんだ。