記事のポイント
- JR上野駅に設置された一台の装置「エキマトペ」が、利用者の注目を集めた
- アナウンスや発着音など、駅構内の音をオノマトペなどで可視化する装置だ
- 一つの装置の設置が、なぜこれほど大きな変化を生み出すことができたのか
2025年3月、JR上野駅の1・2番線ホームに設置された一台の装置が、多くの利用者の注目を集めた。それが「エキマトペ」だ。この音の視覚化装置は、駅のアナウンスや電車の発着音を文字や手話、オノマトペで表現し、聴覚障害のある利用者に情報を届けた。
前編で紹介したエキマトペプロジェクトは、技術導入という当初の目的を超えて、JR東日本という組織全体に波及効果をもたらしている。一つの装置の設置が、なぜこれほど大きな変化を生み出すことができたのか。その答えは、プロジェクトが触媒となって生まれた組織文化の変革と、そこから芽生えた新たな取り組みの中にある。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)
■ 現場から始まった「手話を教えて」の声
エキマトペプロジェクトの最も注目すべき成果の一つが、関わった社員の職場から全社レベルまで広がった意識変化だ。この変化は決してトップダウンで指示されたものではなく、現場の自発的な動きから始まっている。
東京駅に勤務する社員からの反応について、同社東京統括センター(東京駅)の田中彰彦さんは次のように語る。「社内には、切符を売るチームやお客さま案内をするチーム、裏方のチームなど、様々なチームがあります。各チームから月1回程度、手話を教えてという声が寄せられています。デフリンピックに対しても興味を持つ社員が多く、これまでと比べて明らかな変化を感じています」
この変化は物理的な距離を超えて広がっている。八王子支社勤務で、エキマトペに出演した田原佳奈さんは、職場の変化を実感している。「職場の聞こえる同僚からは『出てるね、いいね』『見てよかったよ、頑張って』といった反応をもらっていています。逆に、ろう者からは『こんな音があったんだ、知らなかった』『もっといろんなところに(エキマトペを)設置してほしい』『品川駅など他の駅にも』という反応がありました。聴者とろう者の反応の違いが面白いと感じました」
特に注目すべきは、エキマトペが設置された上野駅での組織的な変化だ。グループ経営戦略本部 経営企画部門サステナビリティマネジメントユニットの山下恵さんは、駅レベルでの取り組みの変化を説明する。
「上野駅には、サービス向上、安全性向上などを目的とした各種委員会が設置されています。この中に、共生社会実現に向けた委員会があるのですが、エキマトペ設置前までは多文化共生の観点で外国人向けの案内強化や、バリアフリー設備のご案内・使用方法の理解、LGBTQの理解促進等の活動をしていました。エキマトペとデフリンピックをきっかけに、今年度は手話にも焦点を当てた活動を企画したと聞いています。こうした新たなテーマが現場から生まれたことには大きな意味があります」
■ 管理職が発見した「聞こえない社員の強み」
こうした現場レベルの変化と並行して、社内の人材マネジメントを管理する立場からも障害のある社員との協働について新たな認識が生まれている。エキマトペプロジェクトをはじめ、日常業務を進める中で、山下さんは、障害のある社員との協働の具体的な効果を詳細に語る。
「聴覚障害のある社員は、文字に残しながら仕事をしてくれます。我々聞こえる側としても、記録を追いながら仕事ができるので、とても仕事がしやすくなっています」
これは単なる配慮を超えた、組織全体の業務品質向上への貢献を意味している。さらに印象的なのは、コミュニケーション能力に関する評価だ。
「端的に伝えるための言葉選びと要約する能力は、むしろ聞こえる人よりも強いと感じています。彼らと仕事をするときに、聞こえる人よりも意思疎通が困難だと思ったことは一切ありません。むしろ、伝えてくれる内容で私の思考回路も整理されて、とても仕事がしやすいです」
この評価は、障害者雇用の枠組みを超えた、真の戦力として障害者をとらえる認識の変化を示している。エキマトペプロジェクトを通じて、管理者側の意識にも根本的な変化が生まれているのである。
■ 聴覚障害社員の「発案」から始まったサービス改善
エキマトペプロジェクトの成果は、さらなる技術導入の呼び水となった。聴覚障害のある社員からの発案を受けて、鉄道事業本部モビリティ・サービス部門の土屋亘さんは設備面での新たな取り組みを検討した。
その結果として、「文字音声化ディスプレイの試行に至りました。デフリンピックを良い契機として、発案した社員が実際に担当し、駅や関係部署と協力して進め、会場の最寄り駅で試行という形で設置しました」と、話す。

さらに、駅でのお客さまとの対応の場での改善提案も試行している。「指差しシートや、耳マークの案内サインを設置するといったことも今回試行として会場最寄り駅の一部で行いました。」
一方、サービス面では更に大規模な取り組みが進行している。サービス品質改革部の瀧澤諄之介さんは、放送の文字化という新たなサービスについて詳しく説明する。
「お客さまの声を見ていくと、駅で困っていることとして『放送が聞こえなくて、今駅で何が起こっているかわからない』という話をよく頂戴していました。これを踏まえて、ヤマハさんが提供している駅の案内放送を文字化してお客さまのスマートフォンやタブレットに表示ができる『みえるアナウンス』というサービスを、8月1日から試行しています」
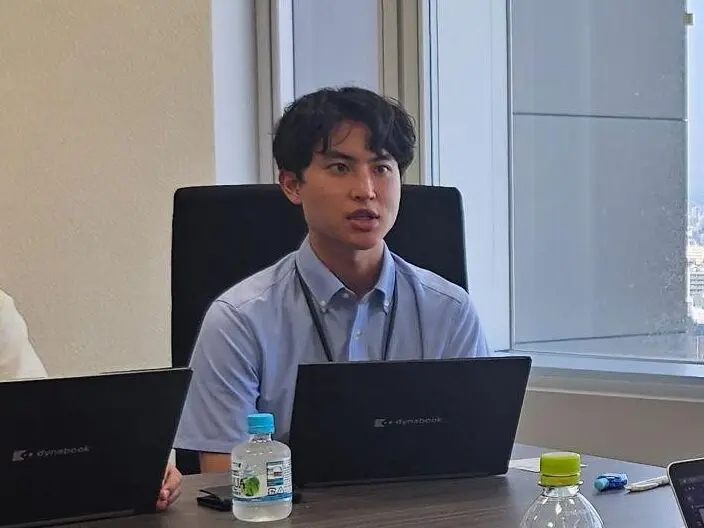
導入規模も大きい。「首都圏をはじめとして、横浜、八王子、千葉、長野のエリアで、年度内までに全部で12駅にて実証実験として試行導入予定です」
これらの新技術導入で注目すべきは、多くが当事者の発案によるものだということだ。この事実は、当事者の視点がいかにサービス改善の原動力となるかを示している。エキマトペプロジェクトが触媒となって、組織内の当事者が積極的に改善提案を行う文化が醸成されているのである。
■ デフリンピックが加速させる「機運醸成」
2025年11月の東京2025デフリンピック開催は、JR東日本にとってこれらの取り組みを社会に発信し、拡大する絶好の機会となっている。同社では大会の機運醸成のための多角的な取り組みを展開している。
広報・啓発活動としては、首都圏駅でのデフリンピックポスター掲出、新幹線車内誌「トランヴェール」での特集記事掲載、9月中旬以降の首都圏の駅社員や乗務員によるデフリンピックバッジ着用などが実施されている。
さらに注目すべきは、教育・体験機会の提供だ。駅たびコンシェルジュ(新宿東口店、池袋店、福島店)での手話教室開催(11月まで毎月)、障害当事者参画型交流の推進、各現場での委員会活動支援など、多層的なアプローチが取られている。
駅たびコンシェルジュでの手話教室は、特に注目される取り組みだ。毎回10名程度の参加者が、基本的な挨拶や自己紹介、簡単な会話を1時間でマスターできるよう、楽しく・優しく・分かりやすい指導が行われている。
「お子様連れでの参加や、小学生の方お一人での参加も歓迎」という方針で、幅広い年齢層に手話に触れる機会を提供している。エキマトペ出演の2人に加え、さらに3人の社員が講師として活躍している。

瀧澤さんは、より根本的な取り組みとして「障害当事者参画型交流」を会社目標に掲げていることを明かす。
「各現場の社員やグループ会社も含めて、障害のある方と交流をして、障害のある方の特性や様々な対応方法を知ってもらうという取り組みを行っています。出前授業もそうですし、駅の設備を障害当事者の方に体験して知っていただくという主旨です」
「こういった活動をさらに広げていって、回数も増やして、社員と障害のある方を結びつけるという活動を、草の根ではありますが続けていきたいです」
■ 「まず本人に聞く」ことから始まる共生社会
こうした経験を通じて得られた知見について、同社社員からは他企業への重要な提言がなされた。特にエキマトペプロジェクトに参画した田中さん、田原さんからのメッセージは、共生社会実現に向けて何が大事なのか、その本質を示している。
田中さんは当事者の声を聞くことの重要性を強調する。「障害者本人にまず聞く、まず尋ねるということがすごく大切な視点だと思います。周りの人が自分で見たこと、感じたことで判断するのではなく、まず本人に聞いてみる。そうすると新しい発見が必ずあると思います」
田原さんは個々人の多様性への配慮を訴える。「自分がこういうふうに感じたからこういうふうにやってと一方的に押し付けるのではなく、いろんな人がいるということを理解してほしい。障害がある人もそれぞれ違う課題を一人一人が持っています。それを活かすためには、自分の気持ちを表に出して相手の立場にも耳を傾けながらお互いに歩み寄ろうとする姿勢が大切です」
さらに田原さんは、より根本的な視点を提示する。「障害がある人もない人も関係なく、それぞれの人には生き方があります。挑戦するという気持ちを一人一人が持って、それぞれが持っている課題にちゃんと向き合っていく姿勢があれば大丈夫だと私は信じています」
組織的な取り組み方について、山下さんは要点を整理して語る。「当社においても共生社会の実現は、経営層から社員に対してしっかりトップダウンでその重要性が発信されています。その前提に立ち、当事者の意見を聞いて、彼らがやりたいと思っていることを取り組める環境作り・制度作りが重要になります」
特に重要なのは、現場レベルでの成功事例を積み重ねることだという。「彼らが当事者として取り組もうとしていることを応援する同僚や職場環境を作り、現場レベルでの成功事例をどんどん増やしていく。ボトムアップでトップが発信している共生社会を着実に実現していく。そうすることで、また新たな課題も見えてくると思います」
■ 「助ける」から「協働する」への意識転換
これらの経験を通じて、共生社会実現への新たな道筋が見えてきた。田原さんの言葉に、その本質が表れている。「(共生社会実現は)聴覚障害当事者の力だけでは成し得ないことだと思います。聴者の力も借りて、一緒に進めていかないといけない。障害者を助けるという視点ではなく、一緒に平等にやっていく」
具体例として、田原さんはバリアフリーの本質を説明する。
「車椅子の人を助けるのではなく、バリアフリーのスロープを作ることで車椅子が利用しやすくなる。視覚障害者用の設備を作ることで、見えない人が自分で行動できるようになる。文字表示を充実させることで、聴覚障害者が自分でできることが増える。そういうふうに聴者と聴覚障害者が一緒に協働で進めていくことがとても大切だと思います」
田中さんは、より根本的な組織文化の変革について語る。
「個人的な考えになりますが、周りの人が、障害者だからこの仕事を任せるとか、障害があるからこの仕事は難しいねと当事者が取り組む前にマイナスに評価をするのではなく、みんな平等に、それぞれができること、それぞれの強みを活かしていくことが大切だと思います。聴覚障害があるから、視覚障害があるからではなく、何ができるか、その人はどういうことが得意なのかということを、密接なコミュニケーションを取ってやっていくのがよいと私は思います」
共生社会実現を、技術革新の社会実装から実現していく取り組みについて、山下さんは明確なビジョンを示す。「多様な人材がその能力を最大限発揮できる環境を作っていくのが企業の責務だと思っています。障害がある人にとって働きやすい環境は、例えば聴覚情報処理障害(APD)のある人などその他の障害のある人にとっても、そして我々聞こえる側にとっても情報の理解・処理がしやすくなることに繋がります」
■ デフリンピック後を見据えた「継続的改善」
各部門の担当者からも、お客さま対応への継続的な改善への強い意欲が語られた。サービス品質改革部の小暮文章さんは、「すべての人の心豊かな生活を実現するのが我々のグループ理念です。つまり全てのお客さまに安心してご利用いただきたいという意味です。いろいろな方のお困りごとを抽出して、その解決をいかに実現するかに取り組んでいきます」

駅たびコンシェルジュでの手話教室を担当するグループ経営戦略本部 経営企画部門サステナビリティマネジメントユニットの山門紗奈さんは、業務の意義をこう語る。
「駅で働いていたころは、障害のあるお客さまも安心して鉄道をご利用いただくための接遇サービスに努めていました。今は障害当事者社員と協力し、誰もが過ごしやすい社会の実現に向けて、手話教室の開催という違う切り口で社会貢献できていることに新しいやりがいを感じています。今回の手話教室はデフリンピック開催を機に企画しましたが、デフリンピックの機運醸成以外の形でも、引き続き障害のある方と一緒に良い機会を提供していきたいです」

土屋さんは設備面での継続的な改善についても語る。「バリアフリーの整備のみに注力すればいいということでもありません。富士通さんとご一緒させていただいて、世の中に多様な進んだ技術があることがよくわかりました。それをキャッチアップして、鉄道業界に落とし込んでいくことが必要だと考えます」
2025年11月の東京2025デフリンピック開催は重要な節目だが、同社社員の関心はその後の継続的な取り組みに向けられている。富士通コンバージングテクノロジー研究所の今村さんが指摘するように、「デフリンピック後の取り組みがもっと大事」という認識のもと、同社は、一過性のイベントを超えた持続的な変革を目指している。
■ まとめ:「当事者が主役」の新たなモデル
エキマトペプロジェクトが示したのは、技術革新と当事者の主体的参画を組み合わせることで、真の共生社会実現が可能になるということだ。外部の専門家に依頼するのではなく、自社の聴覚障害のある社員が手話動画に出演することで、「当事者が主役」という理念が具現化された。
この取り組みは、障害者を「支援の対象」から「協働のパートナー」へと位置づけ直すパラダイムシフトを象徴している。田原さんの「障害者を助けるという視点ではなく、一緒に平等にやっていく」という言葉が、この変化の本質を表している。
プロジェクトは技術導入を超えた組織文化の変革をもたらした。現場レベルでの委員会活動の活性化、他の新技術導入への展開、社員の意識変化など、一つのプロジェクトが組織全体に波及効果を生んでいる。特に注目すべきは、多くの新技術導入が「聴覚障害のある社員の発案」によるものだということだ。エキマトペプロジェクトが触媒となって、当事者が積極的に改善提案を行う文化が醸成されている。
JR東日本の取り組みは、公共交通機関としての社会的責任を新たな形で表現するものではないだろうか。「誰一人取り残さない情報提供」という目標のもと、技術革新を社会実装し、その過程で当事者を主体的なパートナーとして位置づけている。山下さんの「公共交通機関を担うものとして率先して共生社会を実現していく」という言葉は、企業の社会的役割を明確に示している。
エキマトペプロジェクトが提示するモデルは、鉄道業界を超えた応用可能性を持っている。当事者の声を起点とした技術開発、トップダウンとボトムアップを組み合わせた組織変革、継続的な改善サイクルの構築—これらの要素は、様々な業界で共生社会実現に取り組む企業にとって参考になるアプローチだ。
田中さんと田原さんが語った「まず本人に聞く」「それぞれの強みを活かす」という基本的な姿勢は、技術的な複雑さを超えた、人間関係の本質を示している。
朝の上野駅で、エキマトペのディスプレイに映し出される手話表現は、単なる情報提供を超えた意味を持っている。それは、聴覚障害のある人々の「声」が、技術を通じて社会に響いていることの象徴だ。この「声」は、JR東日本の組織内で、富士通との協働関係で、そして駅を利用する多くの人々の心に、新たな変化をもたらし続けている。
エキマトペプロジェクトは終わりではなく、より包括的な共生社会実現に向けた始まりなのである。技術と人の力が融合し、当事者が主役となって社会を変えていく—この新たなモデルが、日本の公共交通から世界に向けて発信されている。































.jpg)



