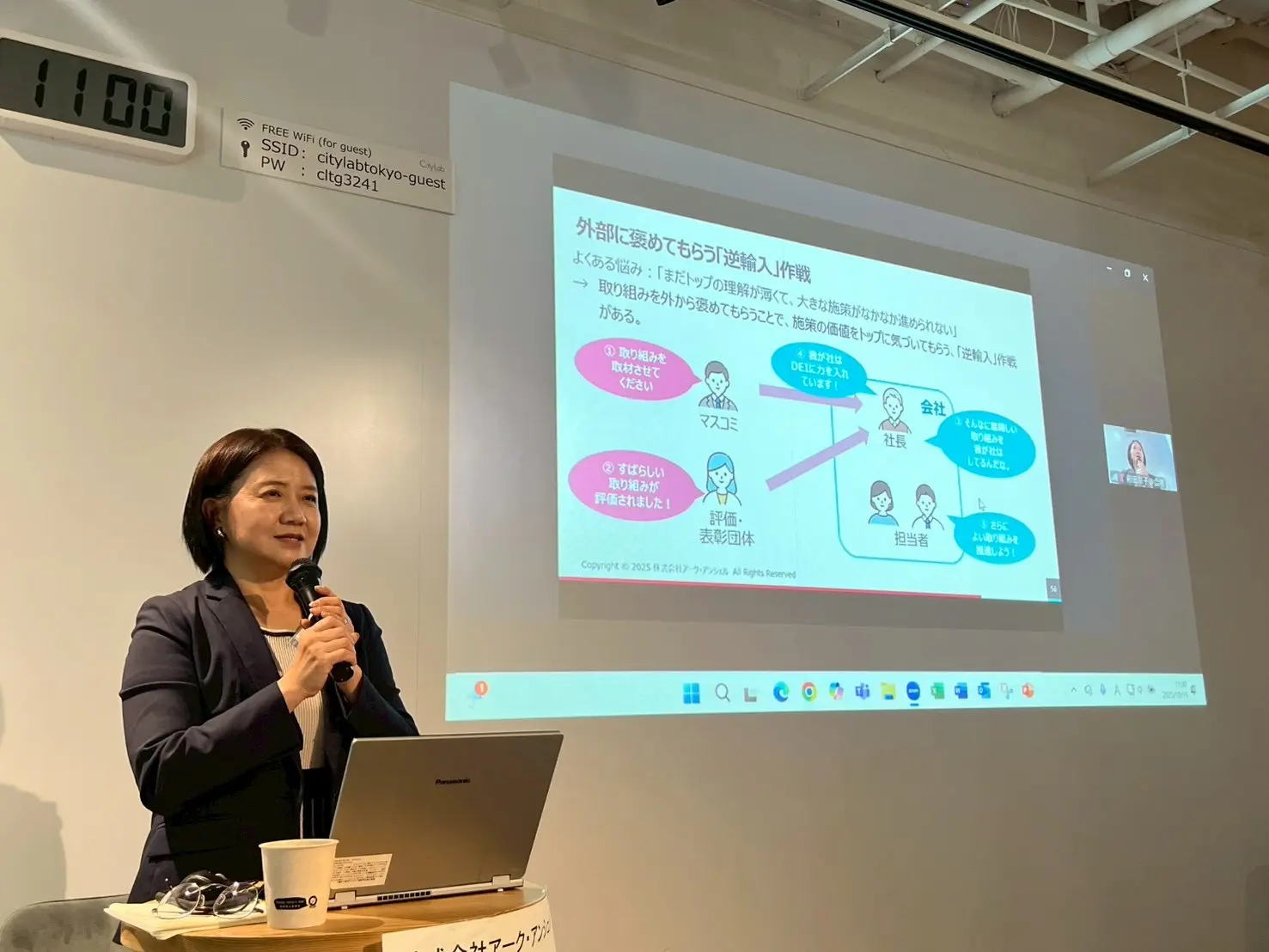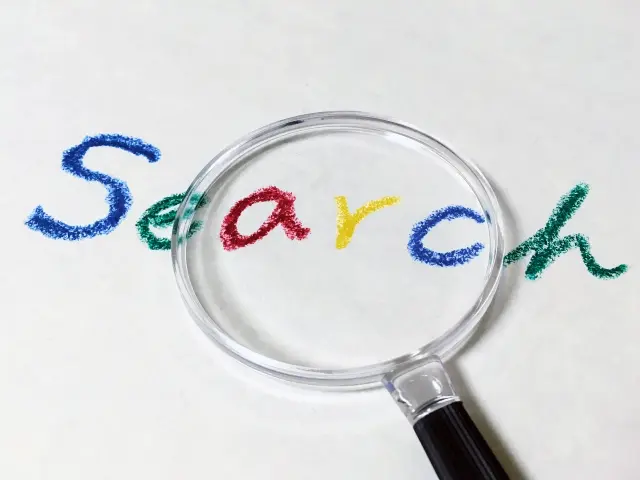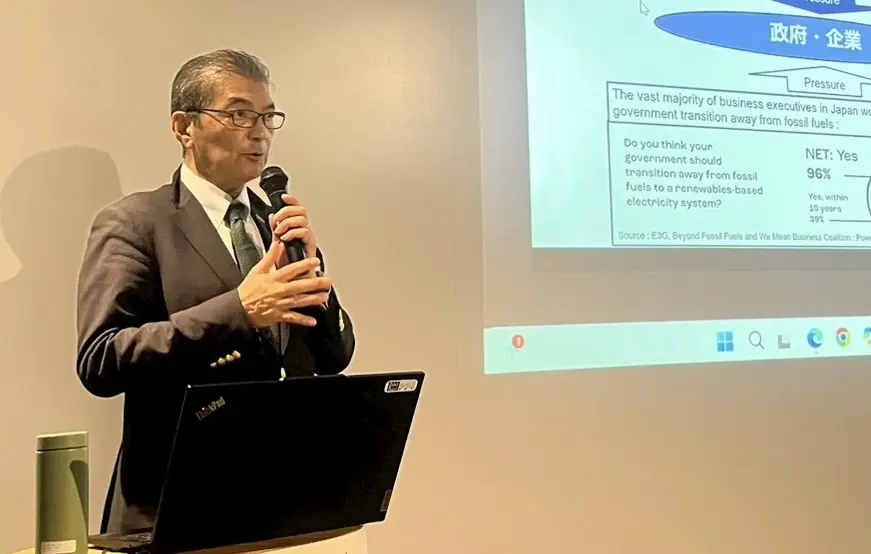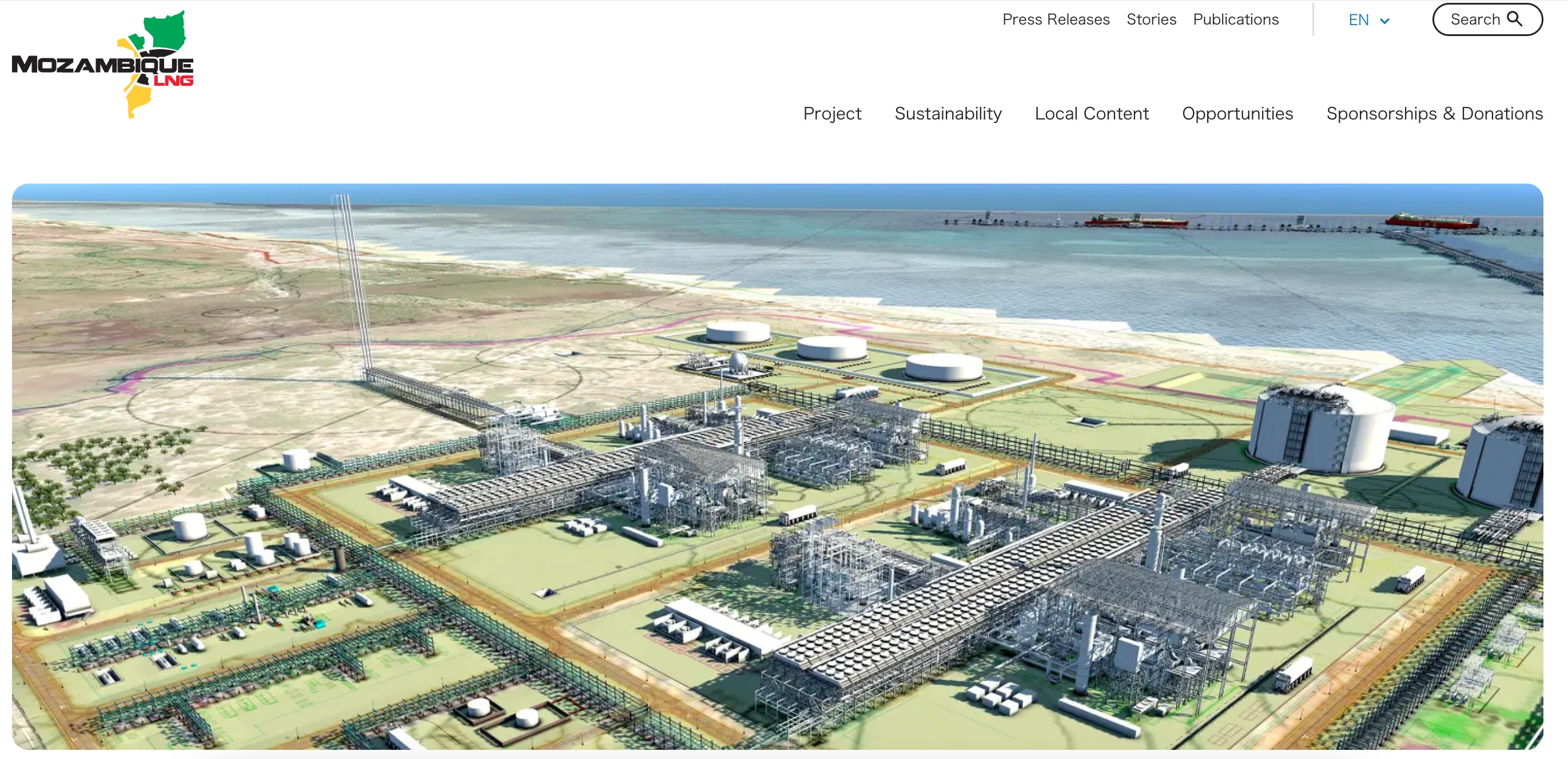記事のポイント
- リコー子会社はゴミに混入したリチウムイオン電池を検知するAIエンジンを開発した
- IHI検査計測のリチウムイオン電池を検知するX線装置に搭載して提供する
- 精度は検証時で94%、社会実装で火災事故ゼロをめざす
リコー子会社のPFU(石川県かほく市)はこのほど、ゴミに混入したリチウムイオン電池を検知するAIエンジンを開発した。共創パートナーのIHI検査計測(横浜市)が展開するX線装置「リチウムイオン電池検知システム」に搭載して、自治体などに向けて提供する。これまで複数の自治体で検証を実施し、検知率は94%だった。社会実装しながら、AIの再学習などさらに精度を高めることで、火災事故ゼロをめざす。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)

PFUは光学技術・画像認識技術を応用して開発した「廃棄物分別特化AIエンジン」シリーズを展開する。昨年4月からビンの選別工程を自動化する「Raptor VISION BOTTLE」を展開。今回のリチウムイオン電池を検知する「Raptor VISION BATTERY」はこのシリーズの第二弾となる。
このAIエンジンをIHI計測予測のX線装置に搭載する。X線とAIを掛け合わせることでリチウムイオン電池の混入のいち早い検知を実現する。
廃棄物処理施設などでのリチウムイオン電池の発火事故は社会問題となっている。環境省の統計によると、2023年のゴミ収集車・処理施設での発煙・発火事故の件数は2万件超。そのうち処理施設での事故は1万件超とされ、被害額は年間で100億円規模に達するという。モバイルバッテリーや加熱式たばこなどが不適切に廃棄されて、ゴミ処理の過程で内部のリチウムイオン電池に圧力がかかり、発火につながっている。
RAPTOR事業開発部の田畑登部長は「ビンの選別工程を自動化するAIエンジンを発表してから、社会問題となっているリチウムイオン電池の検知についてもニーズをいただいて開発してきた」と話す。
■ゴミ袋の中からリチウムイオン電池を検知
実際に、どのように検知するのか。10月下旬に報道陣向けにデモンストレーションを実施した。
装置のベルトコンベアにゴミ袋を流すと、内部のX線で画像を撮影。即座にPFUのAIエンジンが働き、リチウムイオン電池があれば検知する。装置に設置されたモニターがゴミ袋を水平・垂直の2方向で映し出し、リチウムイオン電池がある箇所を赤く囲む。同時にブザーが鳴り、作業者に知らせる。

水平・垂直に2方向からの撮影の方が精度は高いが、プラスチックゴミなどの比較的検知しやすいゴミを対象の場合には、水平・垂直のいずれか1方向からのみでも十分に対策できる。
現場での検知をこなすことで、AIモデルのアップデートも進める「AIモデル再学習機能」も提供する。加えて、検知数をデータ化するクラウドサービス機能をつけることで、混入状況を把握し分析に役立てられる。
今後は自治体での入札を経て導入を進める。各自治体が頭を悩ます問題であり、課題解決への寄与が期待される。













-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)