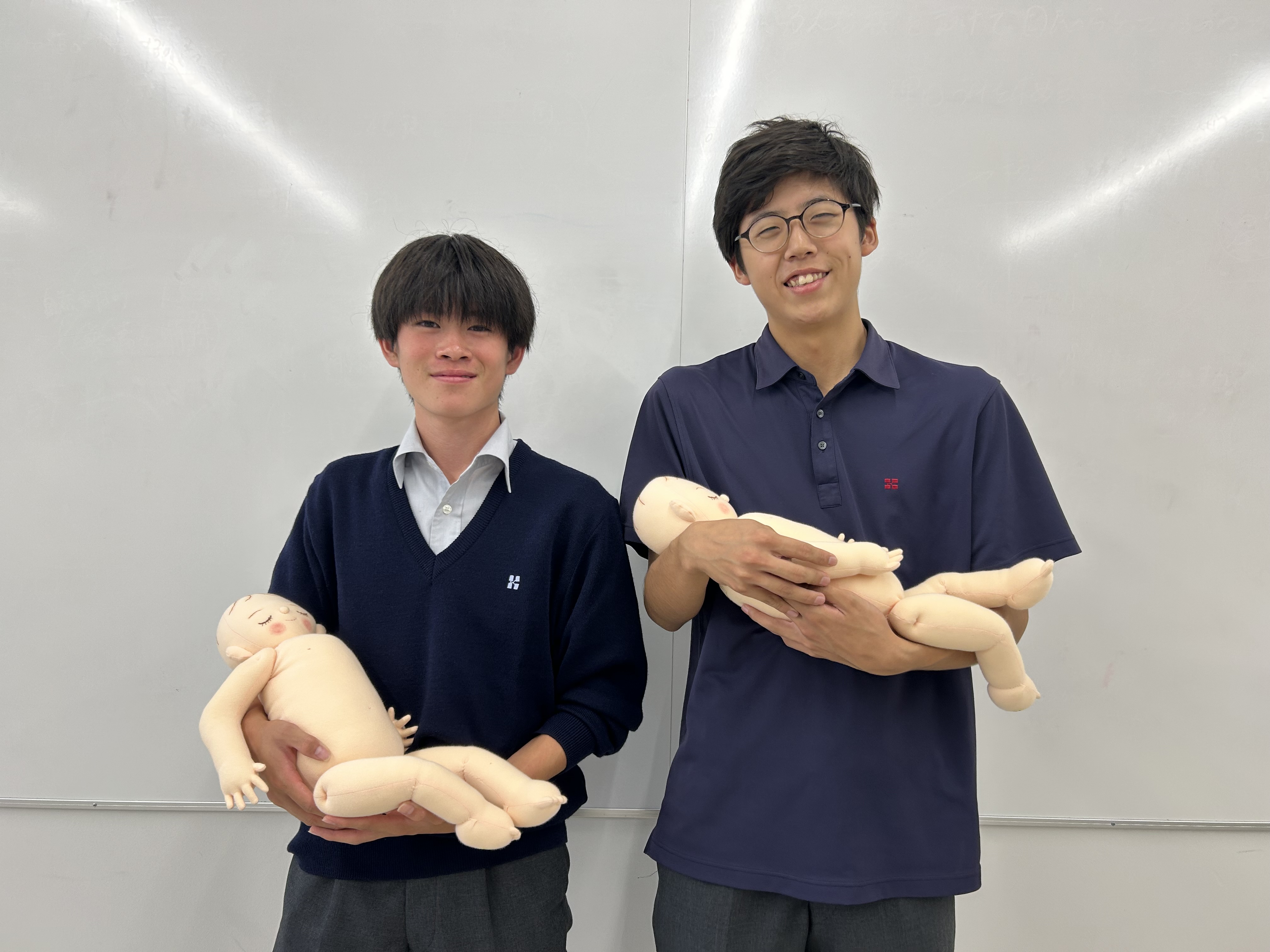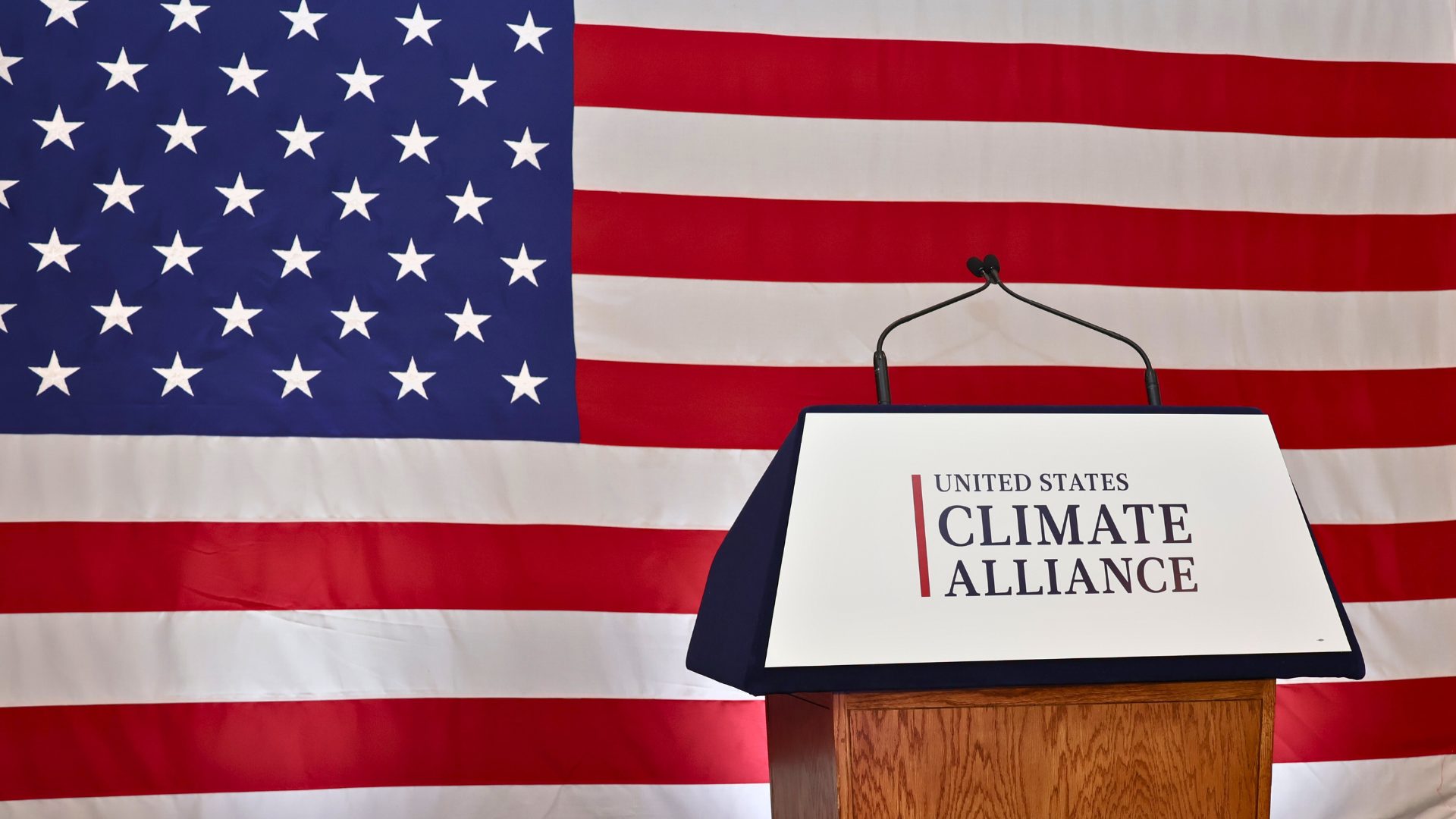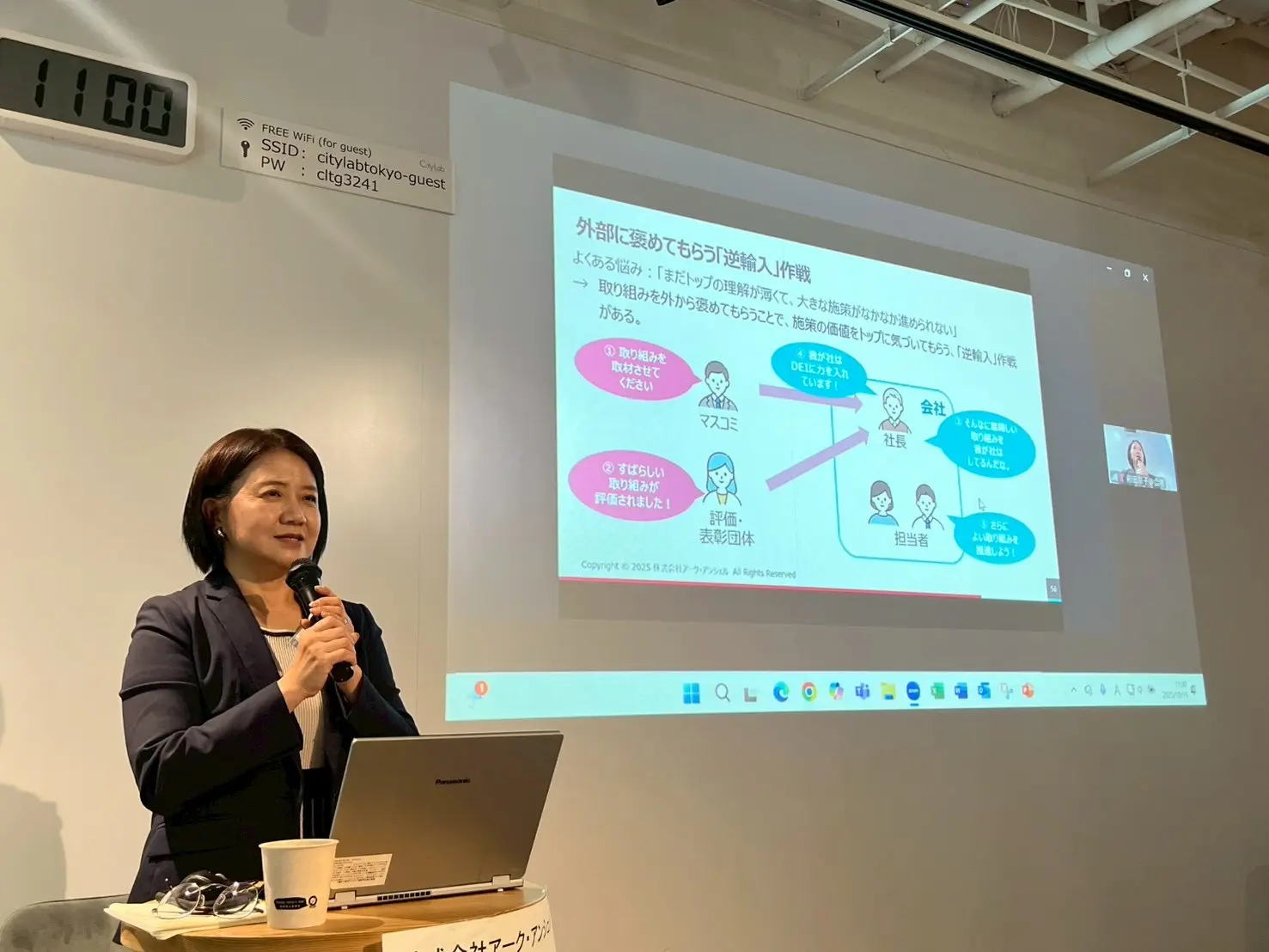オルタナ5号(07年12月発行)では「オーガニック 1%の壁」と題して、なぜ日本でオーガニックの農産物が普及しないかを特集した。記事を書き終え、オーガニック農産物の普及のためには、生産者と消費者の 意識をともに変えなければならないことを実感した。では流通業の役割はどうか。オーガニック生鮮・食品店チェーン最大手のナチュラルハウスの白川洋平社長 に、業界の問題点と展望を聞いた 。
―― 日本でオーガニックの農産物が全体に占める割合は0・16%。欧州諸国の3-10%はもとより、アメリカの0.5%、中国の0.41%にも遅れを取ってい ます。こんなに日本でオーガニック農産物の普及が遅れたのはどうしてでしょうか。

「日本のオーガニックの歴史を振り返ると、第二次世界大戦後、『哲学としてのオーガニック』が崩れてしまいま した。日本も戦前までは、農薬や化学肥料を使わないオーガニックだったのです。都市と農村の人口のバランスが崩れ、多品種少量生産から、大量生産に移行し た過程で、米モンサントなどの農薬が日本に入ってきたのです」
「その結果、生産性重視の慣行農法が当たり前になってしまいました。今、求められていることは、化学肥料や農 薬を使わないだけではなく、農業と自然との関わりを本来から考える哲学に立ち戻ることです」
――日本の有機JAS法は、基準があまりに厳格すぎたり、認証のためのコストがかさんだりして、農家が有機農法を始める上で逆に障壁になっているとの見方 もあります。
「もちろん、なんの基準もないと詐欺行為が起きかねないので、何らかの基準は必要です。日本の有機JAS法 も、ドイツのBIOもそうです。法律制度されたからこそ、大手が入ってきたのです。ただし、『有機JASマーク』がついていればいいのか、という疑問もあ ります。ローカルであること、サステナブルなものを大事にするという精神が本当に育まれているのか。オーガニック自体が工業化されてしまったきらいはあり ます」
「日本のオーガニック農産物の現状をみても、実は国産品よりも海外のオーガニックが多い。体感的には、日本の オーガニック農産物のうち純国産は3割程度です。こうなると、農産物を遠隔地に運ぶ「フードマイレイジ」や、バーチャルウオーター、食料自給率の観点から 見ると、これで良いのかという疑問は残ります」
―― 有機JAS法は、本来の日本の農業や有機農業を守るというコンセプトだったのが、逆に日本の有機農業をつぶしかねないということになりますね。
「有機JAS法は通過点としては必要だが、改めて、グランドデザインが必要だと思います。オーガニックが法 制化されて、大量生産、長距離移動という工業品的になってしまいました」
「欧州では、国の認証に加えてデメターやビオランドなどの認証団体がオーガニック促進の機能を担っていま す。米国ではホールフーズなど大手流通業が主導しています。その一方で、ファーマーズマーケットやCSAなど、小規模農家が活躍できる場があり、良い意味 での『二極化』が進んでいます」
―― 日本の消費者にもっとオーガニックを買ってもらうためにはどんな努力が必要でしょうか。
「オーガニック農産物、特に『リアルオーガニック』をもっと理解してもらう必要がありますね。リアルオーガ ニックとは、有機JASのマークがなくても、農薬や有機表を使っていない農産物のことです。認証がなくても、無農薬・無化学肥料の良品はたくさんありま す。
認証がないので、消費者は不安かも知れませんが、きちんと情報提供をしてあげればよい。結局は相互信頼が重 要なのです」
「現在のオーガニック農産物制度はその意味で不完全です。この農薬・この化学肥料を使っていないという『ネ ガティブリスト』だけで、『ローカル』や『サステナブル』などに対する評価基準が入っていません」
「あるオーガニック農家を訪れたときのこと。その地では生産者の平均が60歳を超えており、労働力の確保が 大変なのです。そして僕にぼそっと言ったことは『昨年、合鴨を入れたことを(私に)言えなかった』。いまや合鴨農法を売りにする農家さえありますが、彼に とっては合鴨を入れることが辛いのです。その言葉を聞いて、私は自分の責任の重さを改めて思い知り、15分ほど席から立ち上がることができませんでした。 彼のような究極のオーガニックの魂を伝えていきたい」
―― オーガニック農業を考えることは、結局は、日本の農業そのものを考えることにほかならないのですね。
「その通りです。まず、農家の高齢化が進み、将来の担い手がいません。日本の農業そのものをどうするかとい う話です。いまナチュラルハウスの会員組織「アップルヴィレッジ」でも生産者の数を集めるのが大変です。そのために慣行栽培からオーガニックへの転換も支 援しています。僕たちがどういう形で有機生産者と組んでいけば良いかを探っています」
「オーガニックへの転換は大変です。一緒に、生産者カレンダーをつくり、二人三脚で苦労をともにします。ま た、時期によっては有機農産物が余ることもあります。B級品(規格外)の販売も大事。加工食品の原材料にするなどの工夫も必要です」
―― オーガニック農産物をあつかう流通業の体制はどうですか。
「安定して販売をしてくれる流通が少ないと思います。安定的に流し続けられるプラットフォームがない。タイ ミングのミスマッチもあります。これだけできてしまったから、何とかしてくれと農家に頼まれることも少なくない」
―― 生産者の問題はどうですか。
「もっと経営マインドを持ってほしいと思います。コスト削減への努力、生産基準も必要です。
もっとシステマティックになるべきです。もちろん、最初にお話したような哲学が最も大事で、その意味では『理念と経営マインドのバランス』が求められてい るのではないでしょうか」
■白川洋平(しらかわ・ようへい)略歴
平成3年 3月 学習院大学経済学部卒業
平成3年 9月 ワシントン大学入学
平成4年12月 同校 John M.Olin School of Business MBA取得、卒業
平成5年 4月 三井物産株式会社入社
平成8年 3月 同社 退社
平成8年 6月 株式会社ナチュラルハウス 代表取締役 副社長に就任
平成12年3月 株式会社ナチュラルハウス 代表取締役 社長に就任



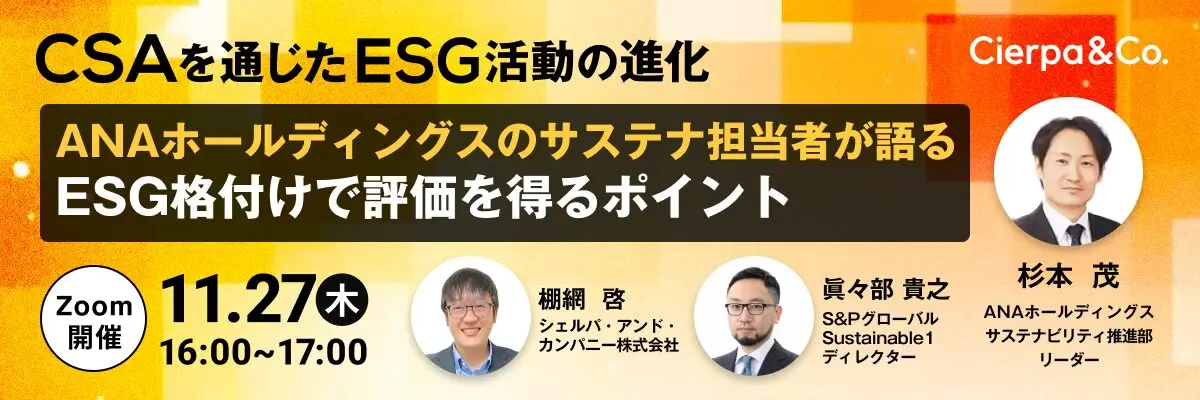










-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)