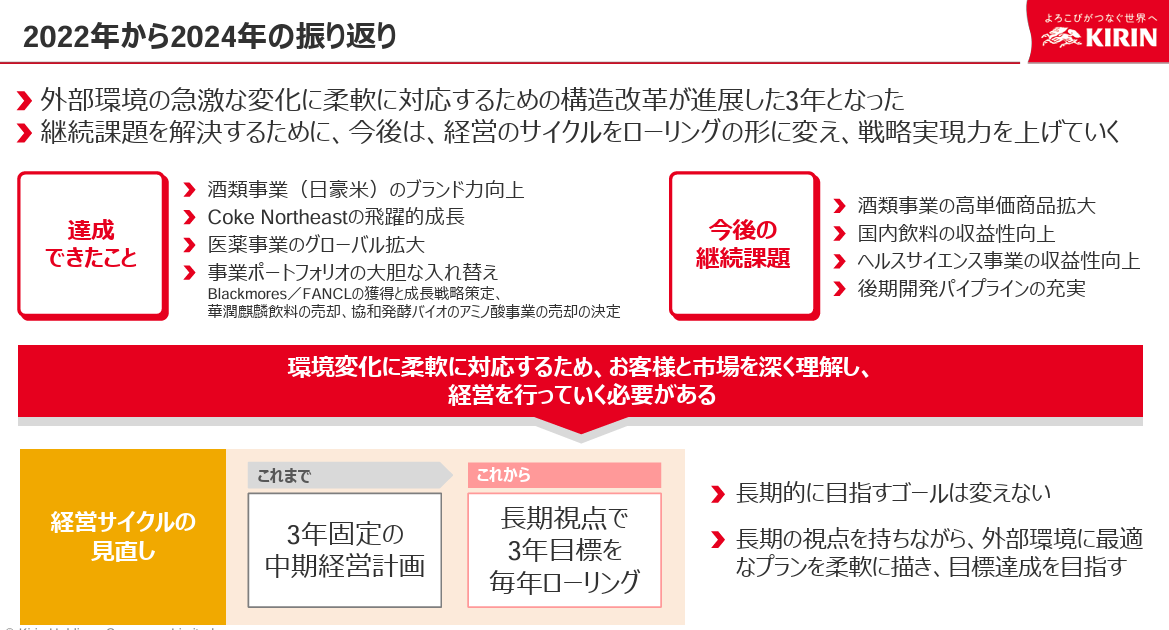――その当時、社会の意識はそこまで高くなかったと思います。周囲の反応はどうでしたか。
まったく相手にされませんでした。オーガニックコットンが一般名詞にすらなっていなかったので、商標登録ができたくらいです。
正直に明かすと、並大抵の努力ではなかったと思います。いろいろなアパレルメーカーにオーガニックコットンの生地を持っていきました。
「環境にいいものですから買ってくれませんか」と頼むと、「こんな色のないものを持ってきても、ファッションとは言えない」とか「そんなボロボロな生地を持ってきて、商売するつもりなのか」など散々な言われようでした。
流れが変わったのは、1993年に日本テキサスオーガニックコットン協会を立ち上げて日本で基準をつくったことです。
基準を満たした製品には、タグを発行する仕組みにしました。協会で集めた資金は、オーガニックコットンの普及啓発のために使いました。
紡績や織布、加工の専門業者と、それを取りまとめる商社が参画してくれました。2000年には、特定非営利活動法人日本オーガニックコットン協会 (JOCA)を設立し、多くのメーカーにも参画してもらいました。
――オーガニックコットンが知られていないなかで、企業はどのような点に賛同して協会に参画したのでしょうか。
まず注目を集めたのが、「素材の真新しさ」です。そして、誰がファーマーであるのか、どこで紡績や織布をするのかなど、「顔の見えるものづくり」への面白さを感じてくれました。
以前の紡績は、いろいろな国から調達した綿を混ぜて、特定の糸を作るのが技術だと見なされていました。
でも私は「どの農家が作ったのか」「何年製の綿を使ったのか」「どこの工場で服にしたのか」という一連の流れを可視化することが大切だと思いました。
私は素人だったから、説明を求められたら説明することでしか、信頼を得られないと考え、全ての情報を公開したのです。
こちらの記事の続き、「オーガニックコットンと苦楽の30年:アバンティ物語㊦」はこちら