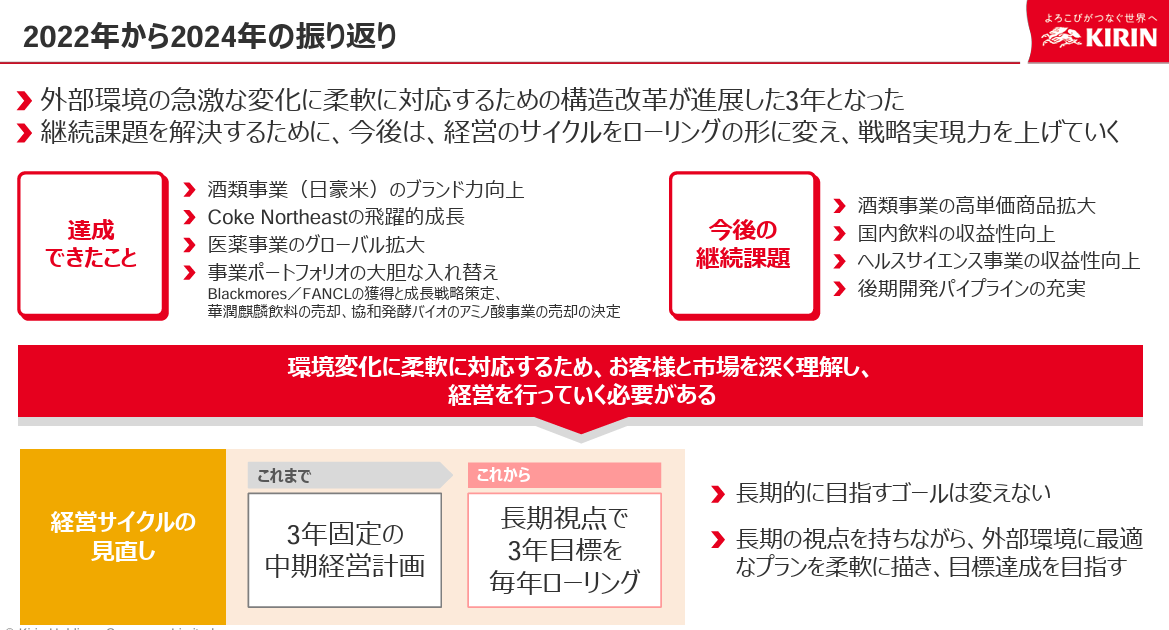■朝ドラのSDGs化
窯元散策路が整備されており、作業の見学開放も行っている。体験型の見学ができ、陶芸の体験コーナーを持っているやきもの事業所も多い。
随所に、朝ドラロケ地紹介パネルやポスターが貼ってある。今後は朝ドラのロケ地であったことも日本遺産のストーリーの構成要素に育っていくかもしれない。

朝ドラはロケの各地の活性化に役立っているが、ドラマ終了後の活用の仕方に差が出ているように見える。「あまちゃん」(2013年度上半期)の舞台は架空の町だが、主なロケが行われた岩手県久慈市・小袖海岸の「北限の海女」や、三陸鉄道北リアス線が話題となり、今でもまちづくりに使われている。
朝ドラは、まちおこしに直結するストーリーが多いので、SDGsを意識して番組作りをすると、日本でのSDGs認知度アップに大いに役立つのではないか。
各回の終わりには番組の案内や視聴者からのメッセージコーナーがあるので、SDGs11「住み続けられるまちづくり」やヒロインが活躍するSDGs5「ジェンダー平等」などがクローズアップできるであろう。今回の「スカーレット」はこれにSDGs9「産業と技術」が加わるだろう。
最近ドラマの中で、直接的にSDGsを取り上げたのが、テレビ東京「ハル~総合商社の女~」の第7話である(2019年12月2日(月)に放送)。商社が社会課題解決型のビジネスを行う内容で、主演の中谷美紀さんがSDGsをパネルで説明するシーンは話題を呼んだのではないか。
テレビ会社ではドラマ作りも本業の重要な一角である。発信性の強みを発揮したSDGs対応が可能である。今後様々な工夫が広がることが期待される。
また、大学の役割も大きくなっている中で、甲賀市と包括連携協定を結んでいる立命館大学では「SDGs地域共創型プログラムむらのこ」を実施している。他大学の学生や高校生も加わり、甲賀市をフィールドとして、4つのテーマに関する地域創生アクションプランを発表した(2019年2月3日、同市「フォト日記」より)。
以上のように、様々な制度も使い、人々のパートナーシップの芽が出て、発信力も強い。陶芸の町、信楽を見て、日本のSDGs的なポテンシャルの高さを感じ、他でも応用可能だと感じた。