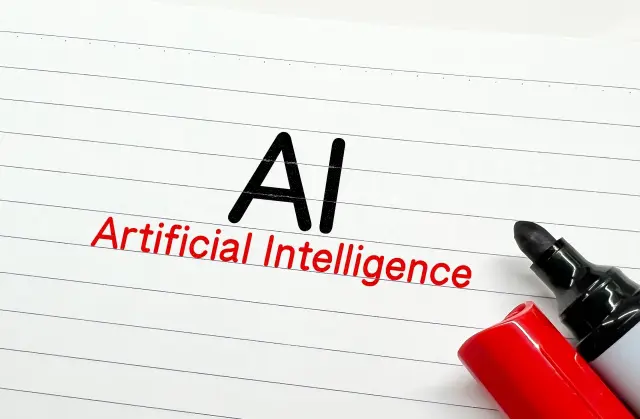近年のLGBTQ(性の越境)も、そうした人間観の多様化=ブロードバンド化の一環である。生物学的にも男女は0/1で截然と区別されるものではなく、連続的なグラデーションのなかでどちらに寄っているか、あるいは成長の過程でどちらに寄っていくか、という可変的なバリエーションとして捉え直されつつある(性スペクトラム)。
トランスジェンダーのアスリートを男女どちらの競技で出場させるかなど、現場的な再調整が必要な課題は多々あれど、基本的には19世紀的な「青年男子・健常者中心的」なスポーツ観・人間観の外部にひろがる未知の沃野でこれからの社会とスポーツ文化をデザインしてゆく、その先駆的なあり方をオリンピックは提示するのだ、という覚悟が五輪の主催者には求められていく。
だから今回、真に問われたのは単なる「差別意識」を超えたビジョンと構想の問題なのだ。JOCと日本国民が21世紀初頭のオリンピックを通じて「どんな社会を、どんな人間のあり方を、特に超高齢社会最前線の国として人類全体に対して提示し、共有化していきたいのか?」という意思が問われている。
浮き彫りにされたのはオリンピック組織委員会とその会長一個人の見識以上に、日本社会全体が長年「先送り」にしてきたーーあるいはアメリカなどに安易にアウトソーシングしてきた社会と人間のあり方に関する問いだ。
そこを自分事として引き受けることなしに、SDGs(人間と地球のサステナビリティ、ダイバシティとインクルーシヴ)の実現はあり得ないだろう。
ついでながら今回の世界的なコロナ第三波の状況においても、従来型の開催への拘りを示すのみで「ウイズコロナ時代のスポーツ文化」のあり方を片鱗でも提示しようという意欲が感じられないのは残念だ。
たとえば「無観客」でなく、チケットを持つ人を中心とした世界のオンライン観戦者のリアルタイムの熱狂がその場でスタジアムの客席に(遠隔操作の半リアル・アバターのようなイメージで)満ち溢れるような、バーチャルでありながらスタジアムの臨場感を担保するような「参加型」の観客席をデザインしてはどうか?
アスリートも満員のスタジアムで競技する実感を持ちつつ、観戦者も自分の歓声がリアルタイムに競技者に届いていることを「共感」しつつ、「地球大のオリンピック観戦(スタジアム)」をデザインすることが、いまの5GやAR・VR技術を持ってすれば十分可能なはずだ。
AIがいくつかの領域で人間を凌駕するようになっても、「痛み」や「感染」といった生身のからだを持つゆえの不都合、そして他者とともに場を共有する「共在感」の大切さをAIと共有しうるわけではない。生身の不都合とITバーチャル化の端境に、アメリカ西海岸とは違ったかたちで日本が開拓しうる新たなデザインの領域がありそうだ。
東京五輪は、そうした実験を世界に提示しつつ、日本自身が旧来の社会構造や人間観を「脱衣」する稀有のチャンスだと思うのだが、いかがだろうか?




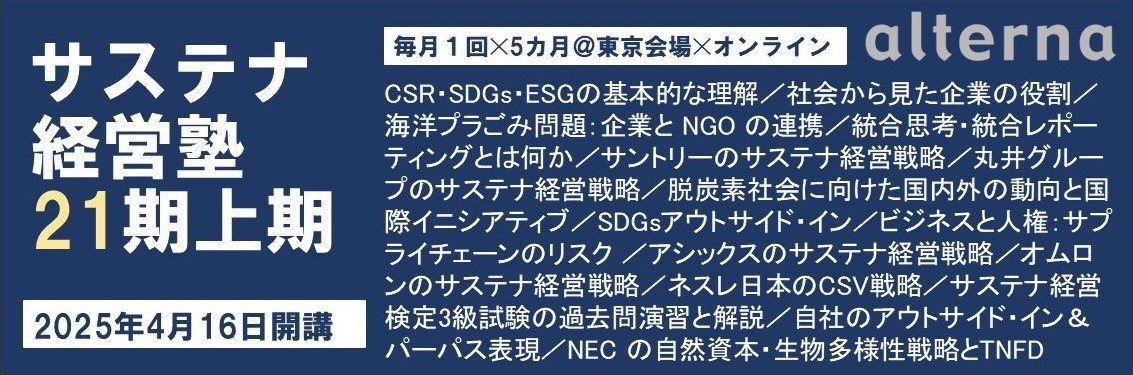




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)