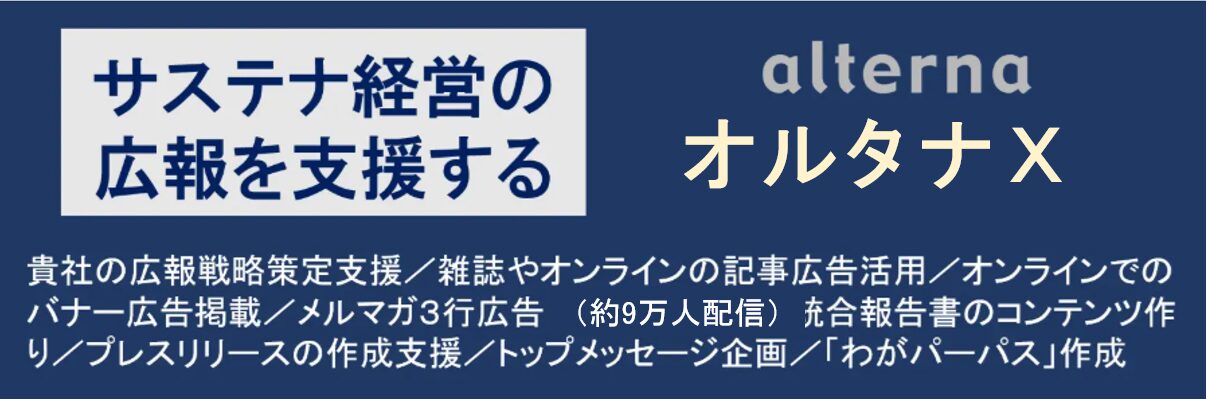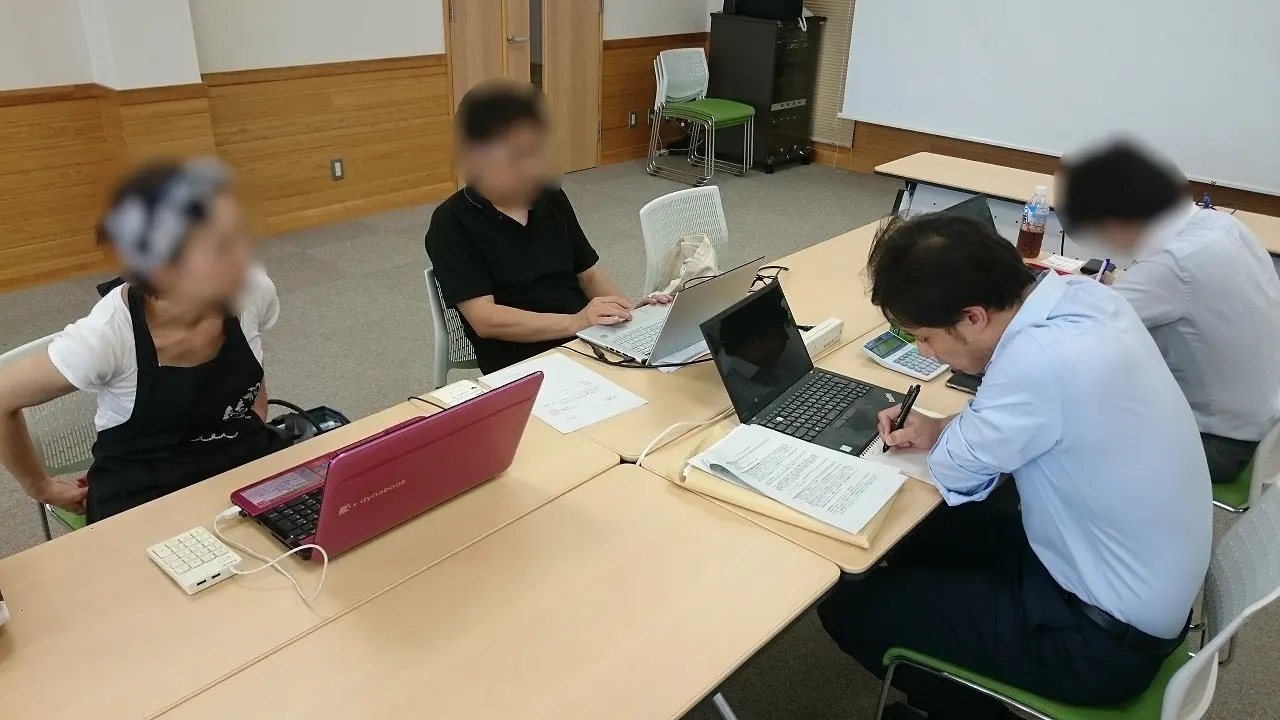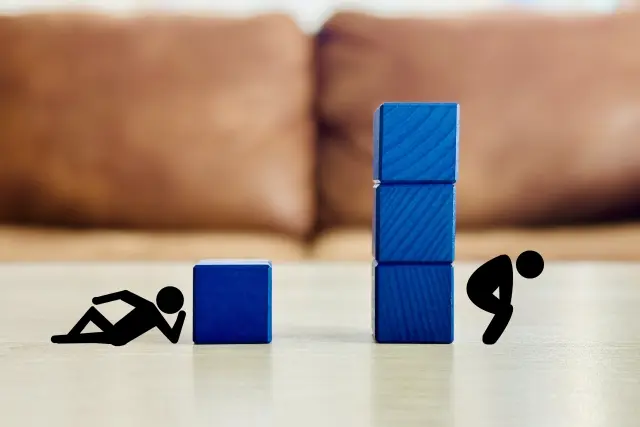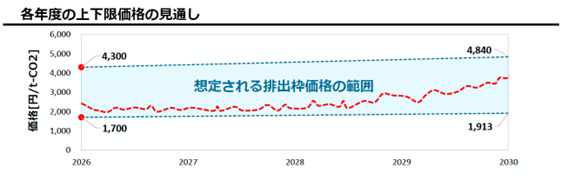【連載】地球の目線2021(3)
東京五輪組織委員会・森喜朗会長の「女性差別」発言が世界で波紋を広げている。これが日本社会に根強く残る差別意識の反映であることはすでに多く指摘されているので、ここでは別の観点から考えてみたい。

今回の事件で真に問われたのは「ビジョンの欠如」――つまり何のためにオリンピックを開催するのか、である。オリンピック・ムーブメントを通じて「どんな社会、どんな人間のありかたをデザインしていきたいのか」という、狭義のスポーツや競技に止まらない構想の欠如、人間観の問題ではないかと思う。
オリンピックは「人間の祝福」の祭典だ。スポーツは人間の高次元を可視化する回路であり、特に水陸の多様な競技が一同に会するオリンピック・パラリンピックは、人間の肉体と精神が持ちうる可能性を最も包括的なかたちで見せてくれる特別な場といえる。
「ここまでできるのか!」というアスリートの超常的なパフォーマンスに人は涙し、勇気をもらう。その特権性ゆえに、それは近未来の人間像と社会デザインを微分的に(つまり一歩先取りした形で)示すものでなければならない。現代において、近未来の人間像を集約した概念が「多様性」であり「越境」だろう。
たとえば、超高齢化社会の本質は「障がいのデフォルト化」だ。誰もが高齢まで生きるということは、視力や聴力、歩行能力などの衰えとともに、誰もが一つや二つ「障がい」を持つことが当たり前になるということだ。
かつては例外(マイノリティ)であり、正常値からの逸脱(欠損)であった障がいが、ごく一般的な多数派(マジョリティ)になり、そうした人間としての凸凹の「多様性」こそが人間の標準となる。
義足を付けたパラアスリートに体現されているような、機械技術で生身を補完したサイボーグ的な身体も、ロンドン五輪のレジェンド・パラリンピアンであるエイミー・マリンズが雄弁に語るように、そうした「多様な近未来の人間のあり方」の一つに過ぎない。(マリンズはむしろ義足を「着替える」ことで、気分に応じて背丈まで変えられるーー「これが私」という自己像や固定的な人間観から解放されると、障害を人間解放の回路として捉える。:TEDのマリンズ講演参照)
そして、「障がいのデフォルト化」によって、サイボーグ的な身体もより多くの高齢者の間で一般的なものになるだろう。何らかの意味でのサイボーグ身体がありふれたものになった時、「サイボーグ」も「パラアスリート」も死語になるーーそんな時代を見据えたスポーツ文化とそれをサポートする都市環境の整備が、巨大スタジアム以上に本当は設計すべきTOKYOの課題なのだ。