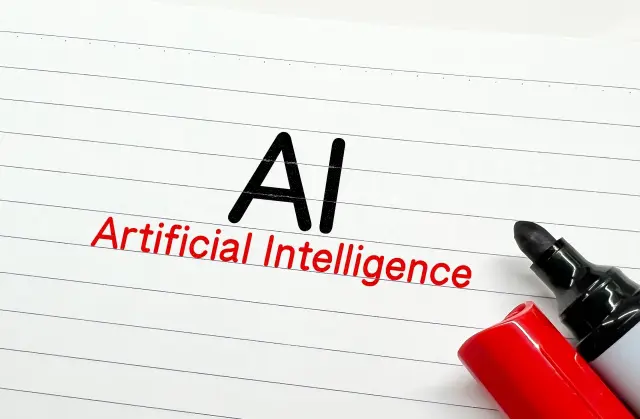■【連載】地球の目線2021(8)■
5万年前の認知革命以来、人類は「観察」という営みを通じて博物学的な知識を蓄積してきた。500年前のルネサンスと科学革命以降は「実験」という手法が確立され、人為的に条件を変えて自然の本性をあぶり出すやり方が科学の本流となった。そしてここ50年、計数技術(コンピューター)の発達によって「シミュレーション」という第3の科学的手法が加わった。それは地球や気象現象のように、その全体を丸ごと観察も実験もできない対象を、その生きた振舞いを仮想空間に再現(創造)することによって理解可能にする。(竹村 眞一・京都芸術大学教授/オルタナ客員論説委員)

地球温暖化と気候変動の予測に対する大きな貢献として真鍋淑郎氏に授与された今年のノーベル賞は、この人類が新たに手にした「想像力の飛び道具」の威力を顕彰したものであり、それが自然の新たな理解とともに人類の社会課題の解決にも直結する「知的な武器」であることを証明するものだった。
■希望のシミュレーション
実験という特殊環境で、自然のある側面、ある法則は抽出できても、それはしょせん複雑系のありのままの姿ではない。だがシミュレーションは、その複雑さを捨象して要素に分解するのではなく、その振舞いの全体を生きたかたちで見える化する。
また条件を変えることでその振舞いの変化を可視化し、異なる未来のシナリオを予測することも可能になる。個人の勝手な想像でなく、共有しうる「科学的現実」(SBT:Science-Based Targetの基盤)として、未だここにはない未来の現実を可視化する。
それは共同幻想(フィクション)を多数の脳でシェアすることで進化してきたサピエンス固有の能力のアップデートであり、コンピューター/AIとの共進化によるさらなるアップグレードを予感させるものだ。
たとえば地球温暖化の2つのシミュレーションを見比べてみよう。(スマフォで見る3D地球儀その1 下図参照)

おそらく多くの人が眼にしたことのあるであろう、IPCC排出シナリオRCP8.5(いわゆる「現状維持型」BAU:Business As Usualシナリオ)と、RCP2.6=「パリ合意」の長期目標(2℃以下に抑える)に沿った削減シナリオに基づくシミュレーションの比較だ。従来のメルカトル地図ではわかりにくい北極やシベリアの温暖化の違いが見やすいように、私どもが開発した「触れる地球/Sphere」地球儀に表示したものだ(データ提供:東京大学・国立環境研究所・海洋研究開発機構)。
前者では2100年にはユーラシア大陸北部全域が高温化する(黄色く白熱したような色で表現)のに対し、後者では黄色は北極圏のほんの一部で、永久凍土の融解・メタン爆発による温暖化のさらなる加速(正のフィードバック)が懸念されるシベリアの昇温はかなり抑えられる可能性があることが示されている。
いまの私たちの「選択」によって、地球と人類の未来はこんなに変わる!
もちろん、あくまでシミュレーションであり、複雑系の未来シナリオを完全に予測することは出来ないにしても、少なくとも「人間なんて地球に比べたら小さな存在で、何をしても変わらない」などと諦める必要はない、それどころか私たちの選択と行動は想像以上に地球のありように影響を与える、ということが確かにわかる。
(そもそも数十年で地球の大気組成や気候システムを変えるほど大きな人類の影響力は、ベクトルが反転すればポジティブな影響力も大きいはずだ。)
この地球温暖化シミュレーションの基礎を築いたのが、真鍋博士の「大気―海洋連結モデル」だった。1960年代、まだコンピューター革命の黎明期に先駆的に創始されたこの革新的な研究が、いまから30年前――地球温暖化が人類的課題として認識され始め、気候変動枠組条約がリオの「地球サミット」で締結された時期、それに同期して出されたIPCCの最初の報告書の礎となった。
この30年前の初期の段階で、すでに真鍋博士は温室効果と放射収支(CO2濃度と地球温暖化の相関)、北極圏高緯度域で温暖化が加速されること、南極では北極ほど温暖化は進行しないこと(南極大陸を取り囲む周極流で赤道付近からの暖流がせき止められるため)をシミュレーション上で明らかにしていたという。現在の精緻化した温暖化予測でもはっきり示されるこの傾向は、真鍋氏のモデルの確かさを証明している。
さらにIPCC第6次報告にも援用された最新シミュレーションでは、これまでのどの排出シナリオでも今世紀後半に北極の海氷が夏に消滅するのに対し、「1.5℃」シナリオでは夏の氷が完全にはなくならないで済むという劇的な違いが示される(スマホでみる3D地球その2 下図参照。このシミュレーションは東京大学の渡部雅浩氏らが中心となって真鍋氏のモデルをさらに発展させたもので、IPCCの最新報告AR6にも援用されている。データ提供:渡部雅浩氏)。

IPCCの最新報告(AR6)などでも参照される最新の地球温暖化シミュレーションでは、現状維持型シナリオSSP5-8.5 (RCP8.5相当)では2070年過ぎからほとんど夏季の北極海氷は消滅するが(右の地球)、削減型シナリオSSP1-1.9 (2100年までの気温上昇を概ね1.5度以内に抑えることを目指す)では2100年まで夏季の氷が残ることが示される(左の地球)。
なおQRコード1からリンクした画像も併せ、この動画は東京大学(渡部雅浩氏)、国立環境研究所(江守正多氏)よりご提供いただいた地球温暖化シミュレーションをデジタル地球儀「触れる地球/Sphere」(開発ELP(Earth Literacy Program;代表・竹村眞一)に投影表示したものを撮影した。
実際2018年に出されたIPCC「1.5℃報告」では、仮にこの範囲に世界の平均気温上昇が抑えられた場合には、「2050年に40億人」と懸念される水ストレス人口が半減、気候難民も数億人レベルで低減、永久凍土の融解も200万平方km(日本の国土の5倍以上)が免れ、海のオアシスとして貧栄養の亜熱帯の海に栄養と住処を与えるサンゴ礁も完全には消滅せずに済む(20%ほど残る)、といった可能性が示されている。
悲観的な警告として受け取られがちな「1.5℃」だが、実は数々の希望のシナリオが示されたレポートなのだ。
■地球における人間の位置――「人新世」Anthropoceneの再定義
近年、地球の履歴書を解読する古生物学・古気候学の急速な進展で、地球と生命の共進化の歴史が解像度高く復元されてきた。それによって、いまの豊かな地球環境は初めからあったものではなく、むしろ生物が「地球をテラフォーミング」して創ってきたものだということがわかった。
酸素のなかった地球を「酸化」させたシアノバクテリア、茶色い大陸しかなかった地球を「緑の惑星」に染め上げてきた陸上植物――地球の気候や大気組成を急変させつつある人類もその地球(共)進化史の延長上にある。
その意味で、人類は地球のOSを変える「唯一」「初」の生物ではない。だが、それをリアルタイムに自覚(モニタリング)し、その未来のシナリオを「選択」して行動を変える「自由」を持つ唯一、初の生物である。
その自由を生命進化史上(そして人類史上)初めて獲得した現代の私たちが、にもかかわらず指をくわえて激化する地球環境を傍観し、取り返しのつかぬ事態に至って後悔と反省を繰り返すとしたら、私たちはとても未来世代に対して顔向けは出来ない。
だが逆にこの認識と自己変革の力を十全に生かし、地球と人類社会のOSのポジティブなアップデートに成功したとしたら、いま「人新世」とか「人類世」と呼ばれ始めている時代の地球史的な意味を、いま使われているのとはまったく逆の意味に転換しうるかもしれないのだ。
パスカルは有名な「考える葦」というフレーズに続けて、次のように述べる。「人間はか弱い葦、しかし考える葦である。宇宙が小さな人間を押し潰すくらいわけないだろう。それでも人間は宇宙より偉大だ。なぜなら人間はその事実――自らの小ささを自覚しているから」。
それに続けて、現代の私たちは次のように続けるべきかもしれない。「自らの小ささとともに、その決して小さくはない大きな影響力も知っているから」と。




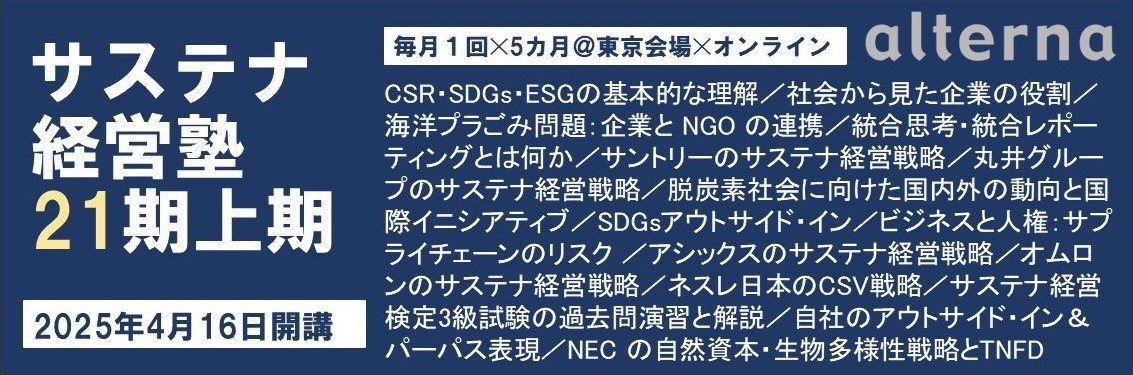




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)