気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は4月4日、緩和策に関する最新の報告書「第6次評価報告書第3作業部会報告書」(AR6/WG3)を発表した。同報告書では、GHG(温室効果ガス)排出量の増加率は鈍化しているものの、エネルギー、産業、農業、土地利用、建物、輸送などあらゆる部門で削減策を拡大しなければ、「気温上昇を1.5度に抑えることはできない」としている。2022年9月には統合報告書が公表される予定だ。(オルタナ副編集長=吉田広子)
同報告書によると、2010~2019年のGHGの増加率は2000~2009年の増加率よりも低かったものの、正味の人為的な GHG排出量は、2010年以降、すべての主要部門で世界的に増加しているという。
そこで、同報告書では、「地球温暖化抑制のためのシステム変革」を示す。例えば、次の通りだ(一部抜粋)。
・低排出電力を動力源とする電気自動車は、陸上輸送について、ライフサイクルベースで最大の脱炭素化ポテンシャルを提供しうる(確信度が高い)。
・エネルギー部門全体を通してGHG排出量を削減するには、化石燃料使用全般の大幅削減、低排出エネルギー源の導入、代替エネルギーキャリアへの転換、及びエネルギー効率と省エネルギーなどの大規模の転換を必要とする(確信度が高い)。
・持続可能なバイオ燃料、低排出の水素とその派生物質(合成燃料を含む)は、海上輸送、航空輸送、及び重量物の陸上輸送由来のCO2排出の緩和を支援しうるが、生産プロセスの改善とコスト削減を必要とする(確信度が中程度)。
・農業、林業、その他土地利用(AFOLU)の緩和オプションは、持続可能な方法で実施された場合、大規模なGHG排出削減と除去の促進をもたらしうるが、他の部門における行動の遅れを完全に補うことはできない(確信度が高い)。
(出典:「AR6 WG3報告書 政策決定者向け要約」)
WWF(世界自然保護基金)ジャパンの小西雅子・専門ディレクター(環境・エネルギー)は、「IPCC新報告書は、世界の温暖化対策が功を奏してきていることを示しているが、同時に気候変動の深刻化には間に合っておらず、私たちの動きがあまりにも遅いことも突き付けている」と危機感を表す。
「私たちの手の中にはすでに多くの緩和策がある。政策パッケージが取り組みを強力に推進することが改めて指摘され、日本は一刻も早く、新報告書でも有効だと示されている政策を導入していく必要がある。その筆頭は脱炭素化を強力に進めるキャップ&トレード型のカーボンプライシングや炭素税の強化だ。日本政府も参加した総会で、排出量取引制度によってほとんど『リーケージ』は起きていないということも新報告書で示された。日本でも導入を前提とした制度設計に直ちに取り掛かるべき」(小西ディレクター)




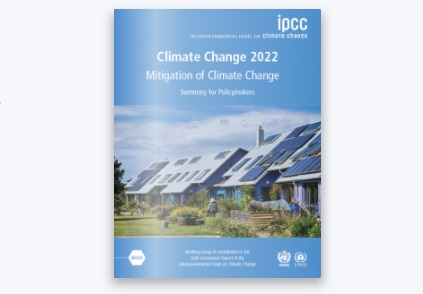





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























