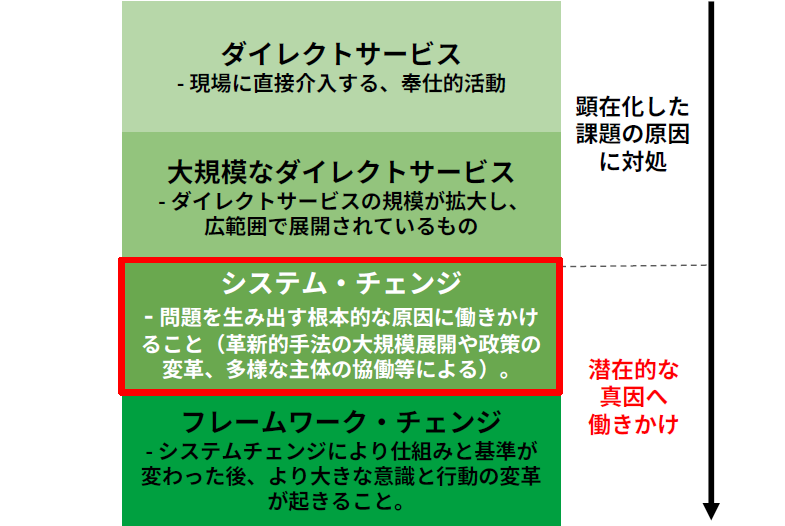記事のポイント
- 今年の3月で2030年を目標年に持つSDGsは「後半の7年半」に入った
- SDGsに関して2030年までの中期目標を持つ企業はわずか
- 後半の7年半では、企業は具体的にどう行動していくかシビアに問われる
SDGsは日本企業にも広く浸透していき、さまざまなPRが盛んに行われるようになってきた。しかし、多くの企業が具体的な行動や2030年までのゴール設定ができていないことが調査データから明らかになってきた。これまでSDGsはブームのような状態だったが、今後は具体的にどう行動していくかが、シビアに問われるようになっていくだろう。その前の踊り場にいる今、企業はどうしていくべきか。(伊藤 恵・サステナビリティ・プランナー)

■半数以上の企業が2030年のゴールを定めていない現実
SDGsの社内浸透に関する調査(※1)では、50.1%の人が「具体的な行動ができていない」と回答し、行動が出来ていない割合は中小企業の方が多い傾向がみられた。
SDGsを達成するメリットが現場の社員まで浸透していないことが原因と考えられる。目標を立てるだけではなく、従業員がなぜ取り組む必要があるのか理解し、自分事化できるような企業努力が必要になってくるだろう。
別の調査(※2)では、約7割の企業がSDGsに取り組んでいるものの、半数以上が2030年に達成すべきゴールを定めていないという結果も出ている。
さらに取り組んでいる企業の中で、メリットを感じている企業の割合も少ない。自社でも取り組みをはじめてみたものの、社内浸透や事業との結びつけに課題があり、壁にぶつかっている企業が多いことがみてとれる。
※1 SDGsの社内浸透に関する調査/IKUSA(2022)
※2 SDGsについての調査/月刊総務(2023)
■企業のSDGs活動を促進させるソリューション
SDGs活動への意識はあっても、なかなか自社だけではうまく促進できない。そんな企業ニーズに応えるためのソリューションも誕生しつつある。そのひとつが、電通ジャパンネットワークが開発に着手している環境配慮型ソリューションだ。
設定されたエコアクションに応じたポイント付与、炭素削減量表示、チャレンジランキング機能など、自社が定めた目標を自分事化し、行動喚起を促すための仕組みが備えられている。
博報堂が提供するのは、社会課題を起点としたマーケティング活動を支援する「ソーシャルインパクト創出支援プログラム」。ソーシャルインパクトを創出するためのクリエイティブ開発ツールと、ストーリー開発ツールを使用する。
企業のパーパスに基づいて創出すべきソーシャルインパクトを定義し、その実現に向けて、中長期的な視点でストーリーを組み立てるという。企業が掲げるパーパスからきちんと実行までプランニングをすることで、企業のSDGs活動をサポートしていく。
■本当に良いものを見極めたい消費者に選ばれるには
環境配慮に関する企業のアピールに、消費者の半数以上はもうすでに懐疑的になっているという調査データ※3もあり、もう上辺だけのSDGs活動は通用しなくなってきている。
これはSDGsに関する情報が氾濫する中で、企業の取り組みを評価する統一された指標がないことも一因として考えられる。
SDGsの目標17の中には、持続可能な開発の進捗状況を測るGDP以外の尺度を開発するというターゲットもある。
商品・サービスを選ぶ消費者にとっても、取り組む企業自身にとっても、行動をする上で指標になる基準の整備が、実のあるSDGs活動の促進において必要になってくるのではないだろうか。
※3 SDGsの項目に関する意識市場調査レポート/ GREEN NOTE(2022年)