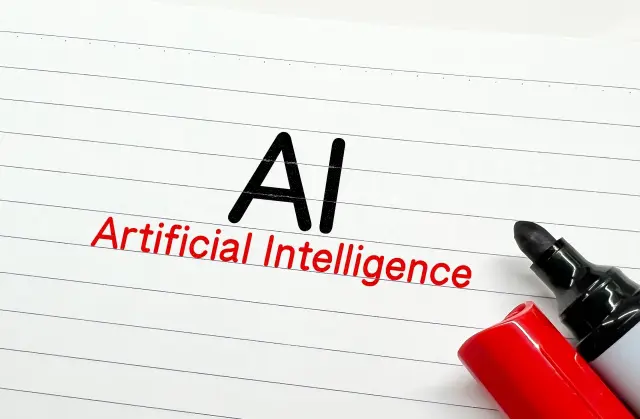記事のポイント
- J.フロント リテイリングは300年続く社是「先義後利」を掲げる
- 同社は従来型の百貨店モデルから脱却し、コロナ禍を経て再成長を目指す
- その原動力となるのが、若手社員の熱量だ
大丸松坂屋百貨店やパルコを抱えるJ.フロント リテイリング。300年続く社是「先義後利」(せんぎこうり)のもと、従来型の百貨店モデルから脱却し、コロナ禍を経て再成長を目指す。その原動力となるのが、若手社員の熱量だ。好本達也社長に、その狙いを聞いた。(オルタナ副編集長=吉田広子)

好本達也(よしもと・たつや)
J.フロント リテイリング取締役兼代表執行役社長。1956年、大阪府生まれ。79年、大丸に入社。2000年に札幌店開設準備室部長、08年に東京店長。10年3月に大丸松坂屋百貨店の経営企画室長に就任。12年に同社取締役、13年に同社社長。20年5月から現職。
■「先義後利」で札幌の地盤を築く

――社是である「先義後利(義を先にして利を後にする者は栄える)」は、サステナブル経営に通じる考え方です。好本社長はどのような場面で「先義後利」に支えられましたか。
小売りは本当に小さなものの積み重ねですから、その日のうちに刈り取り、成果にしなければならないことが多いのです。それでも、「先義後利」という大きな方向性があることで、目先の利益にとらわれず、将来を見据えて計画を立てることができました。
44年という会社員人生の中で、「先義後利」は、いつも私の「拠り所」でした。新入社員としてお客さまと直接対面していた時も、係長や課長になった時も、20年前に大丸札幌店を立ち上げた時も、拠り所だったのは間違いありません。
――大丸は1999年から営業改革に取り組み、札幌の新規出店はその最中でした。札幌店成功の背景には「先義後利」があったのですね。
私は43歳の時に、大丸札幌店の立ち上げに携わりました。初めて日々の営業から切り離され、3年後の開店に向けて知恵を絞る毎日。本当の大丸の資産とは何か、深く考えるようになりました。
大丸は関西で育ち、最北端は東京駅。札幌の人は、全く知らないわけです。積み重ねた「徳」がなかった。
しかし、徳もなければ、しがらみもない札幌だからこそ、「小売りのあるべき姿を目指そう」「気持ちさえあれば何でもやれる」という思いでした。
実際、ラグジュアリーブランドがたくさん入ったわけではないし、食品のお取引先様も北海道に工場を作らなければ販売できないなど、いろいろな課題があったのです。それに対して、商品や売り上げ、販売体制など、ブランドや売り場単位ごとに一つひとつ計画を立てて、きちんと実行していくことを徹底しました。
札幌では、ものすごい数の社員を採用し、取引先様も何千とありましたが、かなりの時間をかけて研修を行いました。当時、そこまでやる企業はありませんでしたから、大丸札幌店は「守るべきことを守っている」という信頼を得られたと思います。
確かに、札幌店の立地と器(うつわ)は立派でした。でも、だから成功したわけではない。「ありたい姿」を描いて、計画に落とし込んで、愚直にやった結果、今の大丸があるのだと思います。
――「先義後利」はどのように引き継がれてきたのでしょうか。
大丸の前身となる呉服店・大文字屋が1717年に開業し、20年ほど経ったころに「先義後利」が店是として定められました。それから300年、途切れることなく、受け継がれています。腹に落ちるし、端的で覚えやすい。いつの時代でも通じる言葉です。
大丸は2007年に松坂屋と経営統合し、J.フロント リテイリングが誕生しました。2020年にはパルコを完全子会社化しましたが、私たちグループ全体の上位概念として「先義後利」があります。ビジョンやパーパス(存在意義)を新たに作る企業も数多くありますが、こうした概念を何百年も前から持ち続けていることは、ものすごく強みだと思います。
■「会社都合の人生を送ったらあかん」

――20―30代のメンバーが中心の「2030年のありたい姿プロジェクト」を立ち上げました。投資家の「未来像に若手・中堅社員の意見が入っているのか分からない」という意見がきっかけだったそうですね。
日本企業にありがちだと思いますが、幅広く意見を聞いても、プロセスの途中に経営会議や取締役会があり、そのたびに年齢が上がっていって、平均年齢60歳の男性ばかりの世界で、すべて決まることがあります。それで良いはずがない。
これからの経営には、ダイバーシティ(多様性)が必要です。
「2030プロジェクト」を立ち上げたのは2021年10月、コロナ禍の一番苦しい時でした。私は10年後、当社グループにいる可能性は限りなくゼロに近い。逆にいまの20―30代が、一番重い責任を背負っているでしょう。
そこで、まずはプロジェクトのメンバーに、あこがれている人、社会に影響力がある人、会いたいと思う社内外の有識者にインタビューして、自由に「ありたい姿」を考えてもらったのです。
経営や企業価値向上に必要なことは、経営陣も外部のコンサルも考えます。しかし、自分がどうありたいか、原点は何か――。それは自分で考えるしかありません。
インタビューした50人以上の方々は、皆さん自分自身の喜びとして、環境や地域に貢献したいという思いで、自然発生的に取り組んでいる。そうしたなかで、私たちに欠けているのは「熱量」だと気付きました。
――「熱量に欠けている」という事実は、ショックだったのではないですか。
当社グループは比較的早い段階で、年功序列の賃金制度を見直すなど伝統的な雇用制度から距離を置いたと思いますが、メンバーシップ型雇用で「与えられた課題を真面目にやる」社風でした。
私はその典型的な人生を送ってきました。仕事の内容も、勤務地も、会社の都合で変わりますから。
これは、コロナの前後で、特に意識したことでした。コロナが拡大する少し前に、若手社員の退職が続いたのです。
私はもちろん、会社から言われたことについて、本当に一生懸命やってきました。でも、「自分がやりたい」と思って、内発的動機に基づいて仕事をしてきたわけではなかった。
これからの若い人たちは、そんな人生を送ったらあかん。自分のやりたいことを大切にしながら「こうやって会社に貢献したい」ということを考えるべきだと思います。誰かが考えたビジネスをやるのと、自分の思いで取り組むのとでは、熱量が違いますよね。
自分の中でふつふつと燃えたぎるものを感じ取って、形にして、会社がそれを支援する――。それが、本来あるべき姿です。
「2030プロジェクト」では、自分たちのやりたいこととして「文化で体温を上げる」というキャッチコピーに凝縮しました。それを日々体感する仕掛けとして、コンポストプロジェクトや、地域のアーティストとコラボレーションしたプランターを作成しました。
一気に大きな変化をおこすものではありませんが、文化で体温を上げる、豊かな文化が実る社会と未来をつくるのだ、という「目指す姿」を全従業員で共有したいと思っています。


[この後の記事内容]
■パルコの子会社化は、ダイバーシティの成功例
■高級ブランドを定額でレンタル、CSVを具現化する
■百貨店の存在意義は地域での役割を果たすこと








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)