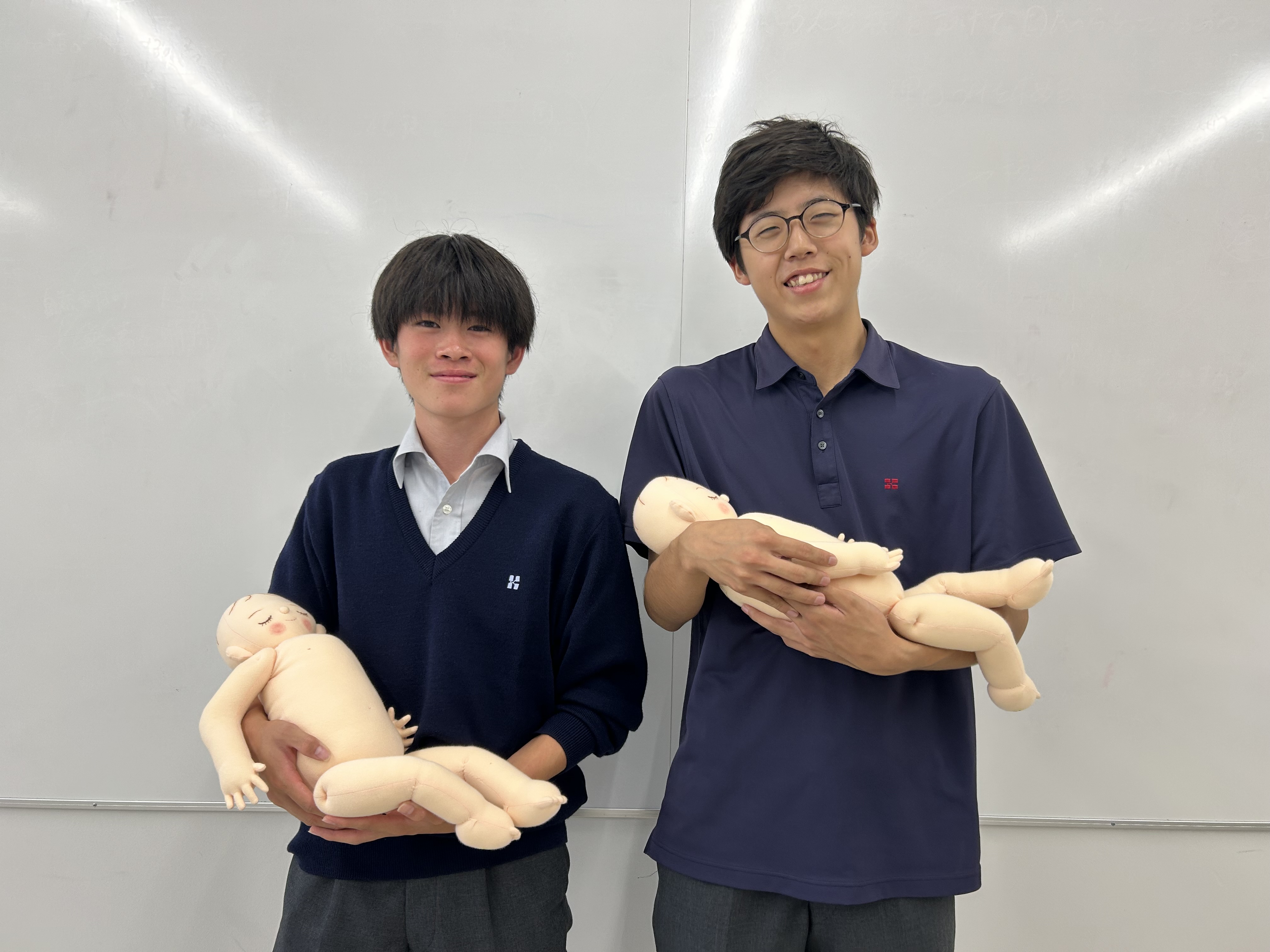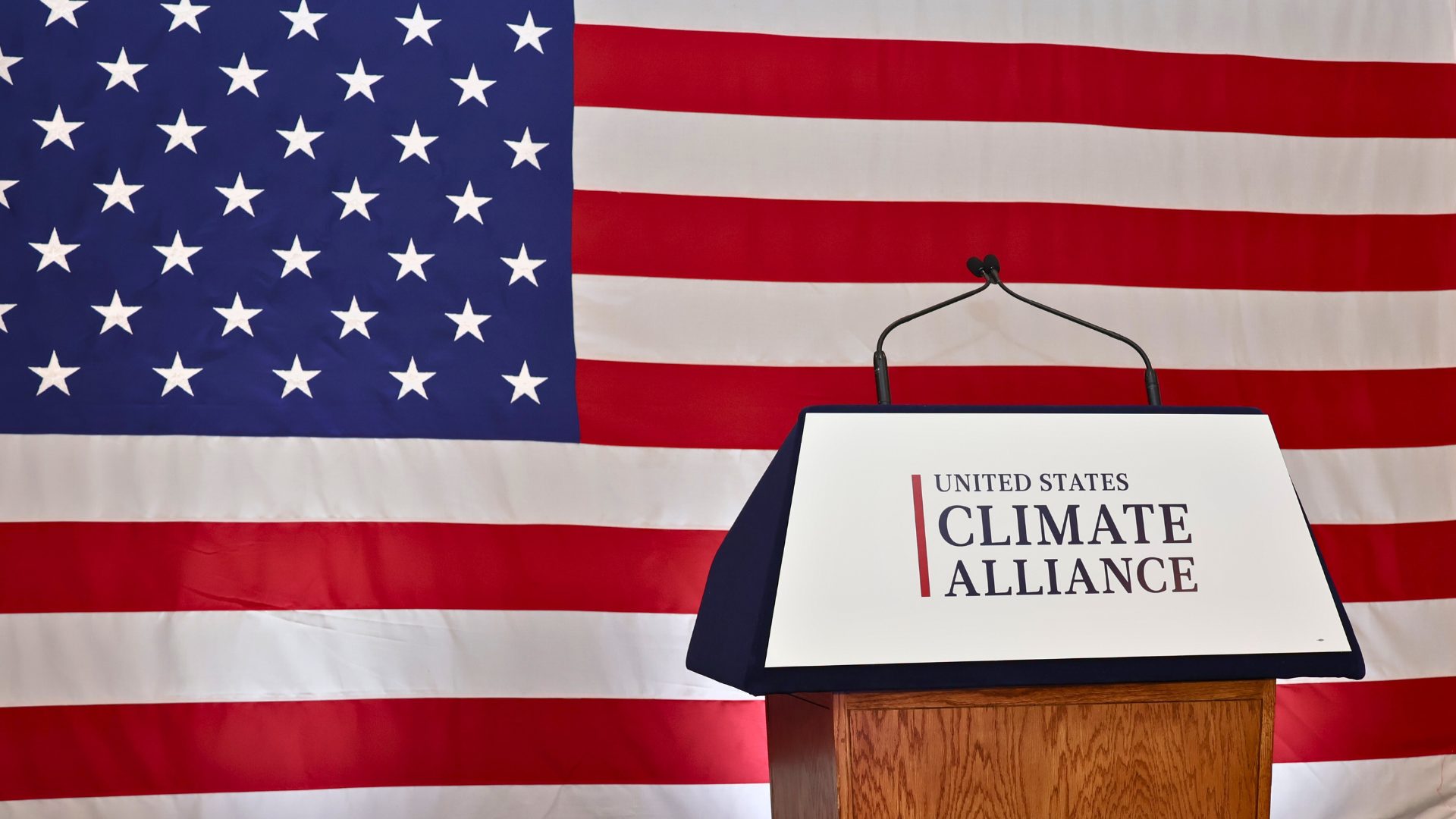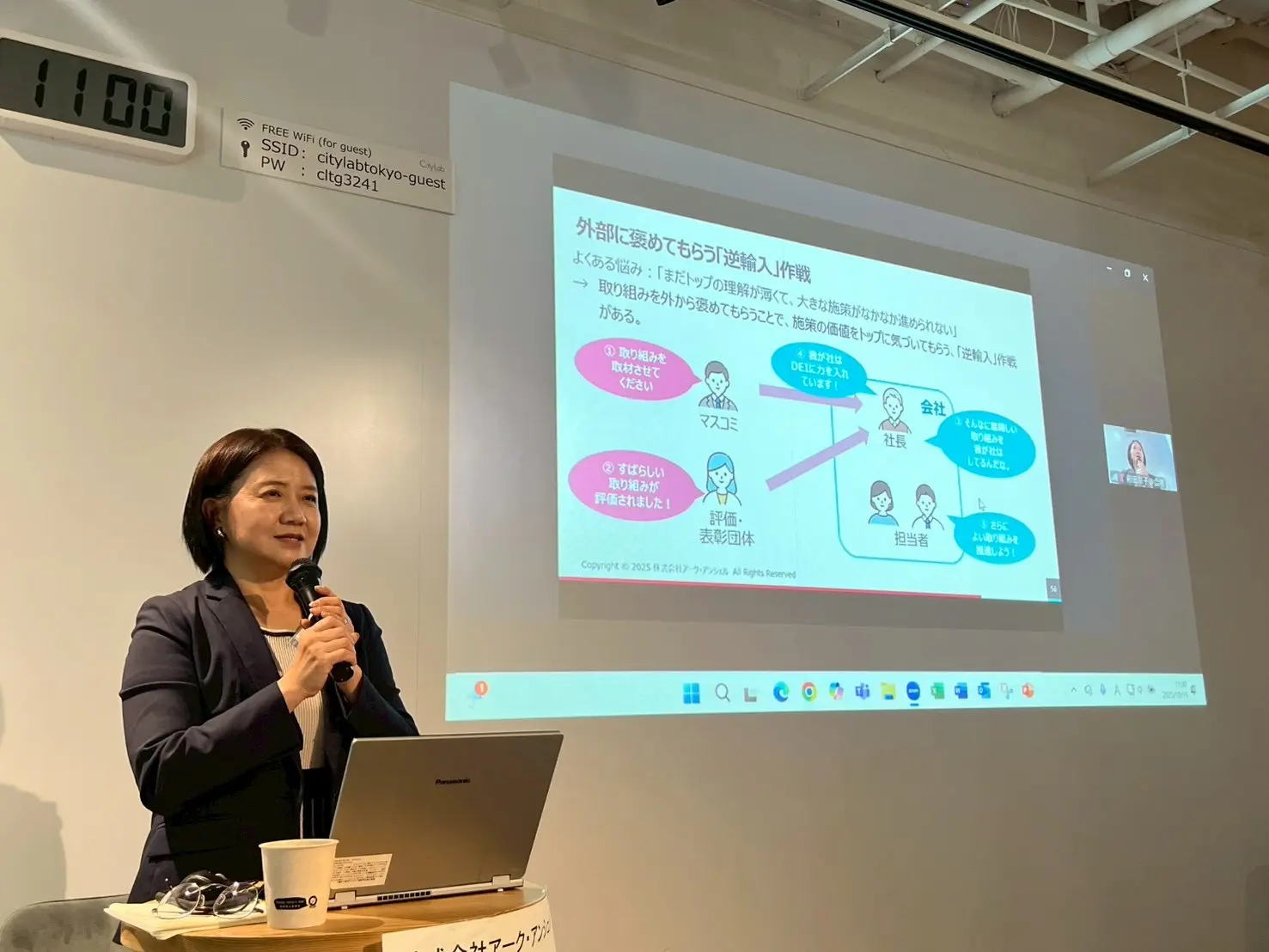「儲かるCSR」という言葉を初めて知った時、一瞬たじろいだ。CSRと儲けは次元の違う話だろう! CSRを長く研究してきた筆者には、何とも奇妙な言葉であった。
しかし、最近では今年2月に「儲からないCSRはやめなさい!」(仁木一彦著、日本経済新聞出版社)が出版され、日経エコロジー4月号の特集は「儲かるCSR:社会価値で成長する」であった。セミナーも開催され、ネット検索のヒット数も少なくない。
そもそも、「儲かるCSR」で何を訴えようとしているのだろうか。用語や語感の是非は別にして、筆者なりに解釈すれば、企業の中長期的な利益確保のためのCSRの商品化ないしブランド化である。つまり、マーケティングや事業戦略の観点からのアプローチであり、CSRマーケティングやCSRブランディングとも表現される。
具体的に言えば、企業が社会的課題に着目した寄付や社会貢献活動により、自社の主力商品(製品やサービス)あるいは事業に、環境を含む「社会価値」を付加することである。それを顧客や消費者に訴求し販売拡大や収益向上につなげ、さらに企業のブランドイメージを高めようとするものである。
代表的事例としてよく取り上げられるものには、二つのタイプがある。一つは寄付や社会貢献により「社会価値」を付加した日用品・汎用品(タイプ1)であり、他方は「本業の強み」を活かした社会貢献型の製品・サービスないし事業(タイプ2)である。
全文ダウンロードhttp://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2012/eye120718-2.pdf



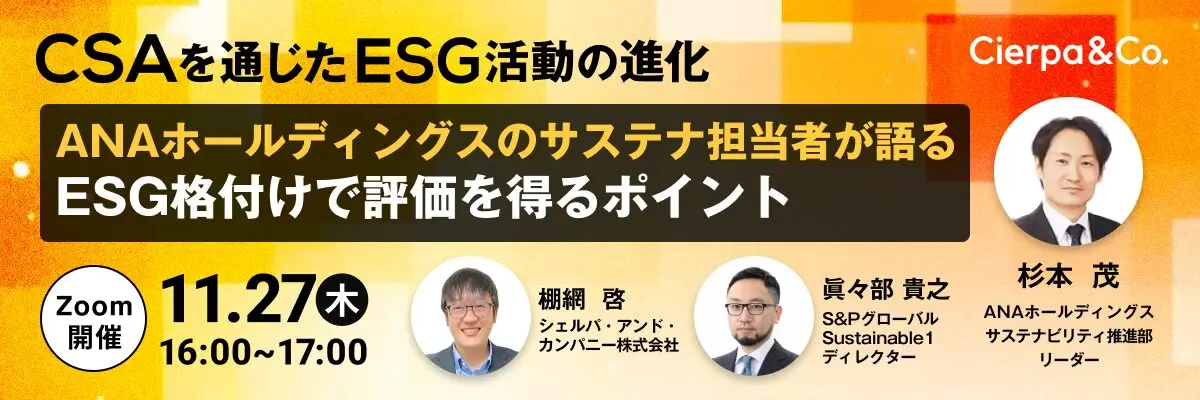









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)