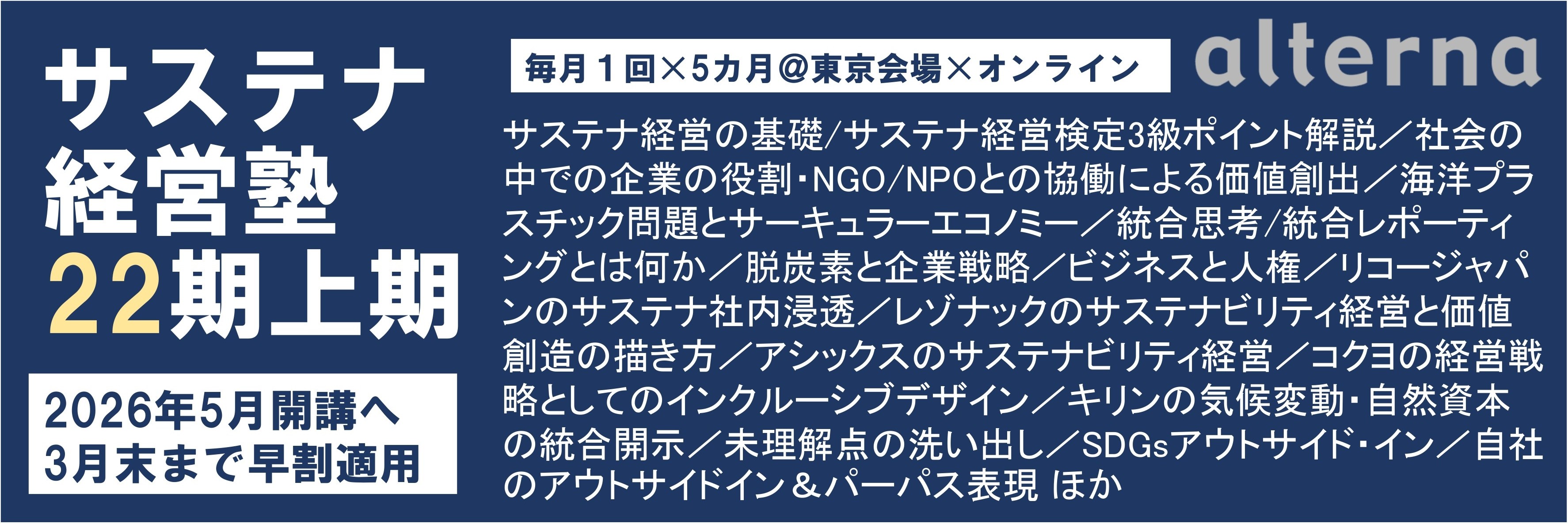記事のポイント
- 気象災害を報じる際に、気候変動と関連付けた報道は少ない
- 小学校の英語教師・小林悠さんは、署名「暑さの原因報道して」を開始
- 1万7447筆の署名を集め、近く報道各社に届ける
2023年は「史上最も暑い夏」となった。だが、日本では、猛暑や水害といった気象災害を報じる際に、気候変動と関連付けて報道することはほとんどない。小学校の英語教師・小林悠さんは、オンライン署名「暑さの原因報道して」を実施し、9月21日時点で1万7447筆の署名を集めた。近く報道各社に届ける。(オルタナ副編集長=吉田広子)

「先週、朝9時に仕事をしていると、体育の授業で校庭にいた子どもたちが、次々に体調不良を訴え、職員室に休みに来た。『35度じゃないだけ今日はマシ』という会話を聞きながら、子どもたちは命の危険にさらされているのを実感した」
オンライン署名を立ち上げた小林さんは、こう語る。年々、猛暑の日が増え、子どもたちが外で遊べない日やプールが中止になる日が増えているという。
「子どもたちの未来を守りたいという思いから、署名を開始した。今年の夏は最も暑い夏だったにもかかわらず、猛暑と気候変動を関連付けた報道はほとんどなかった。日常的に気候変動に関する情報に触れる機会が少ないので、『気候危機』が一般常識として広まっていないのではないか」と訴える。
例えば、BBC(英国放送協会)は、欧州で続く熱波や山火事の被害を報じる際に、気候変動の影響や環境の専門家の意見を紹介している。米CNNも、米国で多発するハリケーン被害について報道する際には、気候変動の影響に言及している。NASA(米航空宇宙局)は9月14日、2023年の夏の世界の気温は、1880年に観測を始めて以来、地球上で最も暑かったとの分析結果を公表し、気候変動対策の重要性を指摘した。
9月21日時点で、オンライン署名には1万7447筆の賛同が集まり、近くテレビ局やラジオ局など報道各社に署名を提出する予定だ。
「再エネや非ガソリン車の導入、設備の省エネ・効率化、生態系の保全など、すでにさまざまな気候変動対策が提示されている。あとはやるか、やらないか。メディアの責任も大きい。特別番組で取り扱うだけではなく、日常的な報道に『気候危機』に関する情報をちりばめてほしい」(小林さん)
小林さんは英語の授業のなかで、子どもたちの反応を見ながら、「気候危機」のショックを与えないように気候変動について伝えているという。なかには、小学校でSDGs委員会をつくったり、自分から積極的に情報を探したりする生徒もいる。
国立環境研究所の江守正多・上級主席研究員(地球システム領域)は、「メディアはこれを伝える機会がたくさんあったはずだ。これからでも遅くない」と記者会見でメッセージを寄せた。