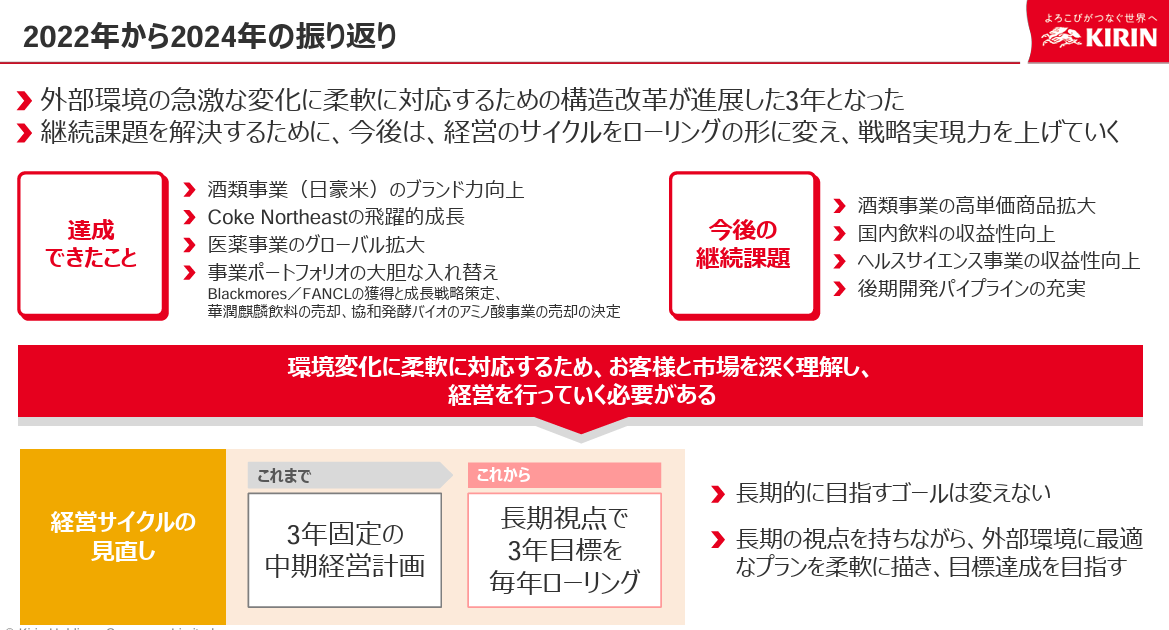記事のポイント
- 水の循環システムを手掛けるベンチャー企業WOTAが新たなファンドの創設を発表
- 全国の自治体を対象に、分散型水循環システムの導入を包括的に支援する
- 「過疎地域などでの上下水道の分散型システムの早期実現化」への構造転換に向けた一歩となる
水の循環システムを手掛けるベンチャー企業WOTA(ウォータ、東京・中央)は7月8日、全国の自治体を対象に、分散型水循環システムの導入を包括的に支援するファンドを創設すると発表した。政府が閣議決定した「過疎地域などでの上下水道の分散型システムの早期実現化」への構造転換に向けた一歩となる。WOTAは新たに開発した家庭用の水循環システム「WOTA Unit」も披露した。(海藤秀満)

■日本が抱える上下水道インフラの課題
近年、日本の上下水道インフラを巡る課題は深刻化している。過疎地域や山間部、島々の地域などで水道管の更新の遅延や老朽化した管路の破損や漏水、財政赤字という問題が顕著になっている。都市部でも老朽化した水道管の破損による道路陥没事故が多発し、2024年に発生した、能登半島地震でも寸断された水道管の復旧にこうした課題が浮き彫りになった。 日本の上下水道は戦後、長年にわたり高い水準のサービスを提供し、飲用可能な水を総人口の98%以上に安定供給し、排水処理を通じて公衆衛生の向上に貢献してきた。しかし、従来の集約型インフラは、人口密度が低い地域ほど1人あたりのコストが上昇する構造的課題がある。水道管の更新費用は全国平均で1kmあたり約1〜2億円に上り、資材費や人件費の高騰を背景に自治体の財政を圧迫している。
■上下水道の「ベストミックス」モデル
WOTAは2014年の設立以来、小規模分散型の水循環システムの開発に特化してきた。水道のない場所での水利用を可能にする「WOTA BOX」や手洗いスタンド「WOSH」を開発している。同社は2024年の能登半島地震の被災地に水処理システムを提供している。この度「WOTA BOX」を発展させた家庭用の分散型水循環システム「WOTA Unit」を新たに開発した。
住宅の浴室・キッチン・洗濯などの生活排水の最大97%を安全な水に再生して循環利用できるシステムだ。不足分は雨水などで補う。システムは、飲用水、生活用水とトイレ用水の3系統から構成され、量産型システムとしては世界初となる。
従来の集約型水インフラを基盤としながら、WOTAの分散型インフラを補完的に組み合わせる「ベストミックス」モデルによるインフラ転換を提案する。

■水循環システム導入ファンドが支援に
分散型水循環システムは上下水道の構造課題を抱える地域における現実的な解決策として注目されるが、導入にあたり実務上の課題もある。専門人材の不足や財源の制約など。こうした導入時のプロセスを支えるインフラファンド「Water 2040 Fund」をWOTAは金融機関・地域企業と連携して2026年度以降に100億円規模での創設を予定している。システム導入のサポートを希望する自治体は、9月末までに募集し、最大5000世帯に適用する計画だ。
7月8日時点、WOTAは三菱UFJ信託銀行、日本政策投資銀行、グローバル・インフラ・マネジメントの3金融機関とファンドに関する協定書を締結した。