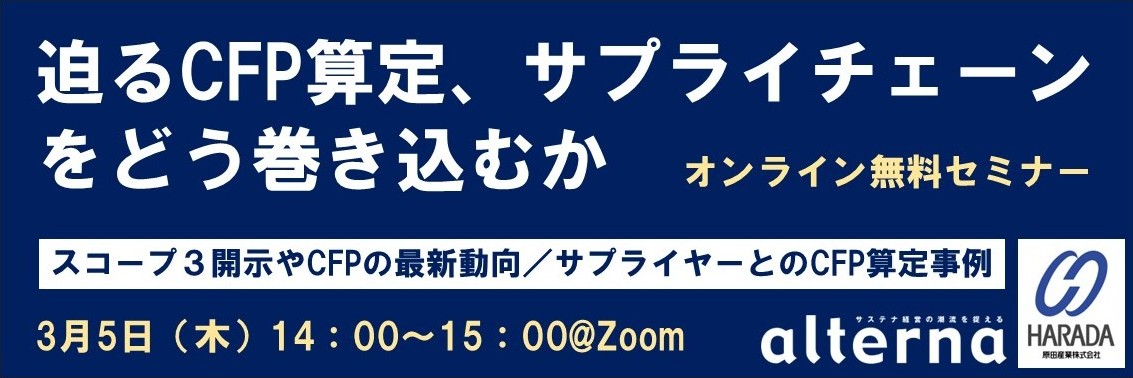記事のポイント
- 生物多様性の取り組みは、日本ではTNFD対応の開示への関心が高い
- 一方で海外企業はネイチャーポジティブに向け、活動を強化する
- 2025年以降、企業はどこから着手し何に注視すべきか、足立直樹氏に聞いた
生物多様性への取り組みは、日本ではTNFD対応の開示に注目が集まるが、海外ではネイチャーポジティブに向けて、開示よりも具体的なアクションが動き始めている。ネイチャーポジティブの本格始動に向けて、2025年以降、企業はどこから着手し、何を注視すべきか。企業による生物多様性保全に詳しいレスポンスアビリティの足立直樹代表に話を聞いた。(聞き手・オルタナ副編集長=北村佳代子)

足立直樹(あだち・なおき)氏:
東京大学理学部卒業、同大学院修了、博士(理学)。国立環境研究所、マレーシア森林研究所(FRIM)で基礎研究に従事後、2002年に独立。株式会社レスポンスアビリティ代表取締役、一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)理事・事務局長、一般社団法人 日本エシカル推進協議会(JEI)理事・副会長、サステナブル・ブランド ジャパン サステナビリティ・プロデューサー等を務める。
■日本企業の関心、世界で群を抜く
2024年10月にコロンビアのカリで開催された生物多様性COP16(第16回締約国会議)で、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)は、今後2年以内に世界で502社の企業がTNFDレポートを発行予定だと発表した。
このうち最も多いのが日本企業(133社)だ。2番手の英国(60社)はTNFDのお膝元だが、日本企業の数はその倍以上と、国内での関心の高さがうかがえる。
一方、TNFDの真意は、自社ビジネスの生物多様性への依存とインパクトを知り、そこでのリスクと機会を把握した上で自然と共生するビジネスへトランジション(移行)していくことだ。
COP16でTNFDは、トランジション計画の報告に関するガイダンスも提示した。リスクやインパクトの分析にとどまらず、トランジション計画の開示まで求められていることを企業はしっかりと受け止める必要がある。
■ネイチャーポジティブの動きは各国で始まっている
情報開示だけではネイチャーポジティブは進まない。COP16でも、ネイチャーポジティブの定義、測定の前提として「自然の状態」を測定する方法、企業の取り組み方やモニタリングの仕方などが盛んに議論された。
生物多様性を「減らさない」だけでなく、「ポジティブにする(増やす)」ための動きは、すでに各国で始まっている。2025年以降はさらに、具体的なアクション事例が出てくることになるだろう。
「ポジティブ」にするための具体的なアクションとして最も多いのは、植林だ。森林保全は脱炭素にも寄与する一石二鳥の取り組みとして、多くの企業が進めている。
しかしそれ以外にも、生態系を回復させるさまざまなソリューションがある。例えば、水に関する領域では、化学的な手法ではなく、藻類や水草などの水生植物を活用した生物的な手法で水を浄化するなどのネイチャー・ベースド・ソリューション(NbS)がそれにあたる。
こうした再生・復元といった「ポジティブ」への動きに、日本企業もどれだけ踏み込んでいけるか、今後、要注目だ。

■SBTNが「科学的根拠に基づく自然関連目標」を承認
生物多様性の情報開示はTNFDに集約されつつあるが、目標設定に関するガイドラインを出しているのがSBTN(サイエンス・ベースド・ターゲッツ・ネットワーク)だ。
SBTNは2024年10月、「グッチ」などのブランドを傘下に持つアパレル大手の仏ケリング、医薬品大手の英グラクソ・スミスクライン、セメントなど建設大手のホルシム(スイス)の3社の淡水に関する目標を、「科学的根拠に基づく自然関連目標(自然SBTs)」として初めて承認した。
生物多様性の領域の中でも、とりわけ淡水については、今後ますます多くの企業が具体的な行動を起こしていくことが予測される。
■世界で顕在化する水リスク、日本にも大きな影響が
水リスクに関して、水不足や干ばつは、日本や東南アジアなどの多雨地域では感じにくいものの、欧米ではすでにその影響が大きく出始めている。そして海外での水リスクの顕在化は、日本においても大きな問題だ。
例えば2024年には国内でオレンジジュースが品薄や販売中止などの事態に追い込まれた。
生産地ではずいぶん前から高温と渇水で収穫が難しくなっていたが、それが2024年に一気に顕在化した形だ。サプライチェーン上の水リスクや気候変動リスクを把握し、事前に対策を講じていれば販売中止は防げたはずだ。
日本においても、東京・大阪など人口密度の高い地域では、人口1人当たりの使用可能な水の量は世界的にも決して多くはない。蛇口をひねれば必ず水が出てくる状態が、将来にわたって約束されているわけではないことも頭に入れる必要がある。
水リスクは干ばつに限った話ではない。水害や、PFAS(有機フッ素化合物)をはじめとする水質汚染の問題も含まれる。
■水リスク把握はサプライチェーン視点で
企業がこうした生物多様性や水リスクを把握するには、まず、自社のサプライチェーン上で原材料はどこで作られているのかを把握し、その地域の水リスクや生態系リスクを評価・分析していくのが良い。取水量だけでなく生態系への影響も見ていくことが必要だ。
これはTNFD開示のプロセスの一部でもある。開示をするかどうかは別として、自社の生物多様性リスクを社内で認識・判断するためにも、TNFDのプロセスを一部でも経験することは有用だ。
自然関連リスクへのエクスポージャー(影響を受けること)を調査する無料オンラインツール「ENCORE(アンコア)」や、水リスク管理のデータプラットフォーム「Aqueduct(アキダクト)」などの測定・評価ツールも活用できる。
■2025年以降にもルールメイクか
2025年以降、生物多様性へのインパクトが大きい食品・飲料、アパレル、建築・資材、化学などの業界では、先駆的に取り組みを進めるリーダー格の企業主体で業界全体のルールを変えていく可能性がある。ユニリーバ、ネスレ、ダノンやケリングなどは非常に熱心だ。
EUでは、欧州森林破壊防止規則(EUDR)の実施の1年延期が決まったが、それでも13カ月後に施行されることに変わりはない。
国際的にビジネスをしていれば、厳しいルールのところに従った動きを取らざるを得なくなり、EUDRに適合したトレーサブルな原材料は今後どんどん価値が上がっていくだろう。
「自社は国内ビジネスだけだからEUDRなど関係ない」という企業もあるが、EUDRによって、今後、EUDRに適合した価値の高い原材料が調達しにくくなることを認識する必要がある。
そうした原材料の調達ノウハウが社内に蓄積されなければ、将来、いざ海外とビジネスを始めたいと考えたときに、全く動けなくなってしまう。
2025年以降、サプライチェーンの取引先から、生物多様性リスクへの対応が取引条件として求められる可能性も高まっていく。
そうしたビジネス継続リスクを回避する上でも、企業は、業界内で最も先進的な取り組みをしている企業をベンチマークにしながら、海外の規制動向にも注視をし続けていく必要があるだろう。(談)