サステナビリティに関する報告を義務付ける「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」が2023年1月、欧州連合(EU)で施行された。50 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す「欧州グリーンディール」の一環で、企業の情報開示を強化する狙いだ。日本企業はどう向き合えば良いのか。(中畑 陽一)
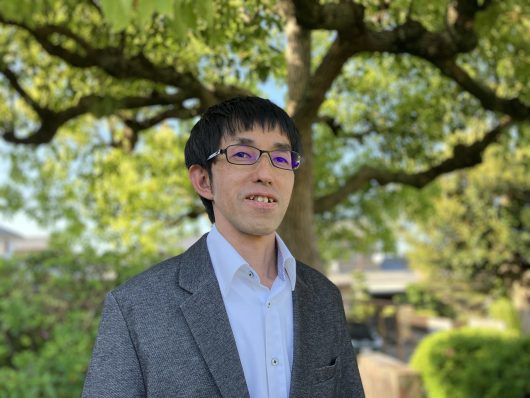
CSRDに基づく開示基準は、IFRS(国際財務報告基準)やGRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)などの開示基準との相互運用性向上を図っているほか、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」などに基づくデューディリジェンスの観点も盛り込んでいる。
人権や環境に関するデューディリジェンスを義務化する「欧州コーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令案(CSDDD)」(24年7月発効)は、CSRDと補完関係にある。
CSRDは「ダブルマテリアリティ」ベースであることが重要な特徴だ。企業が社会・環境に与える影響に関するマテリアリティ(インパクトマテリアリティ)と、社会・環境が企業の財務に与える影響に関するマテリアリティ(財務マテリアリティ)の両方の観点が必要という意味だ。
CSRDに関するサステナビリティ情報開示の具体的な基準策定をEUから一任されたEFRAG(欧州財務報告諮問グループ)は22年4月、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)第1弾の公開草案を発表。24年1月に発効した。
ESRSは「分野横断基準」(ESRS1・2)と「トピック基準」に分けられる。
開示基準について、企業にとって特に大きな影響が考えられるのは、第三者保証(当初は合理的保証より簡便な限定的な保証)を課す点だ。
限定的保証に関する基準は26年10月1日までに、合理的保証に関する基準は28年10月1日までに欧州委員会が採択する予定だが、まずは加盟各国の定めを抑えることが必要だろう。
(この続きは)
■域外の企業も対象に








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)






















