記事のポイント
- 海洋プラスチックごみの1割を、流出した漁具由来のごみが占める
- ごみが出る原因は、台風や事故による流出や経済的理由など
- WWFジャパンはサプライチェーン全体で連携しての解決が必要と指摘
海洋に流出するプラスチックごみの約1割を、魚網やカゴ、ロープなど漁具由来が占める。発生原因として、台風や事故による流出のほか、産廃コスト高騰によって適切に処分ができないなどの経済的理由が挙げられる。環境NGOのWWFジャパンは2月20日に報告書を発表し、「漁業者だけで問題を解決することは難しく、原料調達から製造・販売、廃棄までのバリューチェーン全体の連携が必要だ」と指摘した。(オルタナ副編集長=長濱慎)

プラスチック汚染は気候変動、生物多様性損出、環境汚染の全てに関わるため、環境NGOなどは「三重の危機」と呼ぶ。中でも、海洋には毎年800万トン以上のプラごみが流出していると推定される。世界経済フォーラム(ダボス会議)は2016年の報告書で「2050年にはプラごみの量が魚の量を上回る」と、警鐘を鳴らした。
海洋プラごみの約1割を、魚網やカゴ、ロープなどの漁具由来が占める。これらは「ゴーストギア(Ghost gear)」と呼ばれ、他のプラごみと同様に海洋汚染を引き起こし生態系にダメージを与える。さらに、特有の問題として指摘されるのが「ゴーストフィッシング」だ。
これは流出した魚網やカゴが海中をただよい、意図せずに生物を捕獲して漁業資源を減少させることだ。プラ製の漁具は自然界で分解されにくく形状を維持したまま残るため、こうした問題を引き起こす。
ゴーストフィッシングによる被害の全貌はまだ明らかになっていないが、米ワシントン州で行われた調査では870本の刺し網を回収し、カニや魚類など3万個体以上が被害に遭っていたことを明らかにした。調査はワシントン州魚類野生生物局が、2000年から2008年にかけて行った。
漁具由来のごみが出る要因として、台風や事故による流出や、産廃コストの高騰で適切に処分ができないといった経済的な理由が挙げられる。IUU(違法・無報告・無規制)漁業者が、逃航時に海中に漁具を放棄するケースもある。
WWFジャパンは2月20日に報告書「日本におけるゴーストギア対策の現在地」を発表。自治体、漁協・漁業者、水産企業、流通・販売企業、素材メーカー、政府(水産庁、環境省、経産省など)の各ステークホルダーが解決に向けて担うべき役割と、取り組むべき内容をまとめた。
報告書は、漁業協同組合と帝人が連携してポリエステル製魚網の回収・リサイクルを進める長崎県平戸市、漁業者が協力して使用済み漁具の回収・処分にかかるコスト負担の軽減を図る宮城県南三陸町など、国内各地の取り組み事例も紹介している。
自然保護室・海洋水産グループの笘野哲史氏は、「漁具由来のプラごみは意図せずに流出してしまうケースも多く、漁業者の努力だけで問題を解決することは難しい。原料調達から製造・販売、廃棄までのバリューチェーン全体の連携が必要だ」と指摘する。
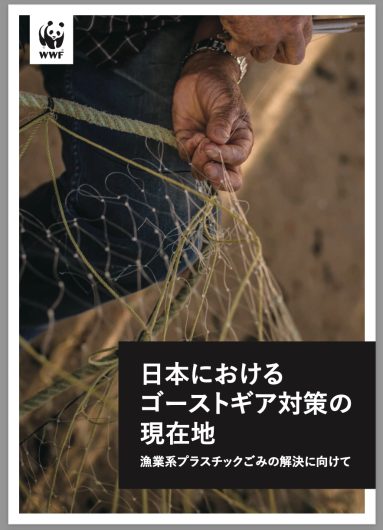
報告書はこちらからダウンロード可能









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)






















