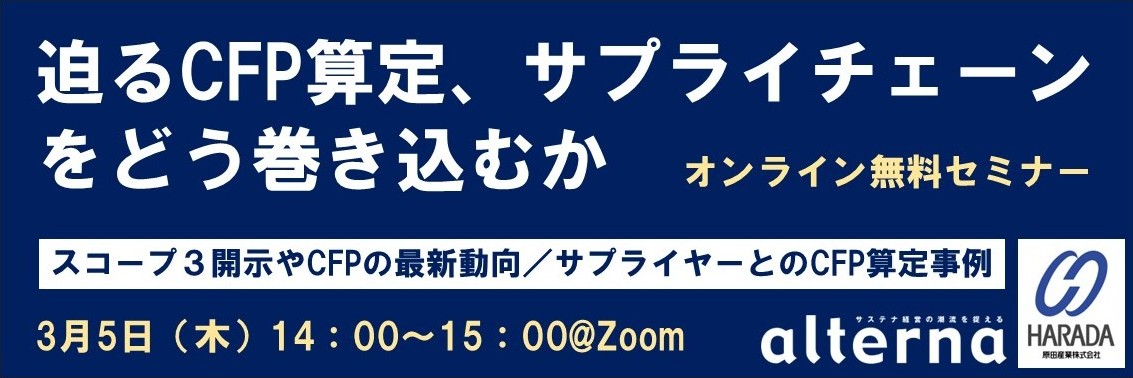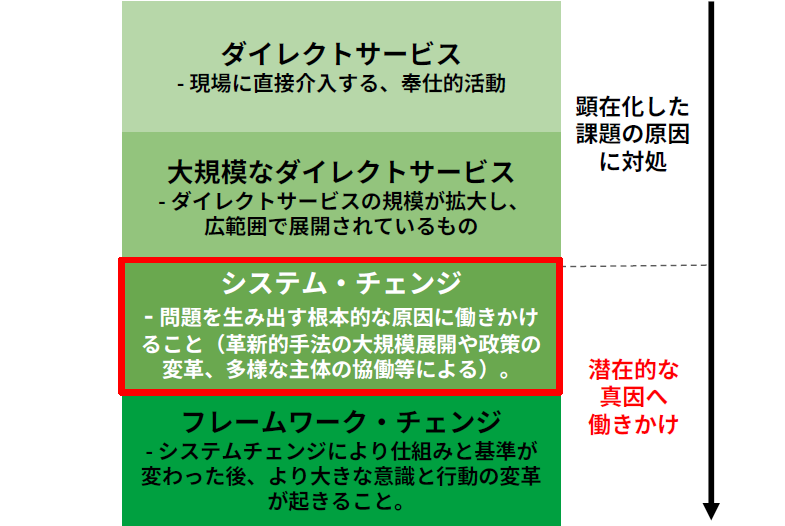記事のポイント
- JリーグはJ1からJ3に加盟する全60クラブの気候変動対応の順位付けを始める
- 気候変動対応を可視化し、順位付けすることで各クラブに対応を促す
- 12億円の助成金を活用して、各クラブに分配する
Jリーグはこのほど、2026年度からJ1からJ3に加盟する全60クラブの気候変動対応の順位付けを行うと発表した。各クラブの気候変動対応を可視化し、順位付けすることで対応を促す狙いだ。Jリーグは、クラブの活動を支援するため、3年で約12億円の助成金を用意した。(オルタナ輪番編集長=池田 真隆)
Jリーグは国際的なイニシアティブ「Sport Positive League (スポーツポジティブリーグ、以下SPL) 」への参画を決めた。SPLは、サッカークラブの気候変動対応をスコア化し、定量的に把握できる仕組みだ。順位付けすることで、各クラブに対応を促す効果もある。
SPLは、欧州サッカー連盟(UEFA)の環境諮問委員であるクレア・プール氏が2018年に立ち上げた。2025年現在、イングランドプレミアリーグやドイツのブンデスリーガ、フランスのリーグアンなど欧州の4つのプロサッカーリーグが参画しており、Jリーグの参画は5番目だ。アジアでは初の参画となる。
■スポーツ業界にも「グリーンウォッシュ」排除の動き
■スペイン「ラ・リーガ」は週に8時間のESG研修を行う
■「再エネ」「ゴミ削減」など12項目を独自にスコアリング
■Jリーグ、天候が理由で中止した試合数は10年で5倍に
■Jリーグのサステナ担当役員「活動を点で終わらせない」
スポーツ業界にも、グリーンウォッシュ(環境によいことをやったふり)を排除する動きが起きている。サステナビリティへの意識が高い英国では、ファンや株主、政府が各クラブに対して、環境性や社会性を強く求めるキャンペーンを頻繁に行っている。
こうしたことを背景に、欧州主要リーグの各サッカークラブは、「ESG(環境・社会・ガバナンス)担当者」を置いた。スペインのプロサッカーリーグ「ラ・リーガ」では各クラブのESG担当者を集めて週に8時間の研修を開くほど力を入れる。
英国プレミアリーグに所属するリバプールFCは2023年、「ISO 20121」の認証を取得した。これは、持続可能なイベント運営のためのマネジメント規格だ。プレミアリーグのサッカークラブとして初めての取得となる。
■再エネやゴミ削減など12項目をスコア化
SPLが評価する気候変動対応は12項目ある。①ポリシーとコミットメント、レポーティング②再生可能エネルギー③エネルギー効率④環境負荷の少ない移動手段⑤使い捨てプラスチックの削減・廃止⑥ゴミの削減管理⑦水の効率的な利用⑧プラントベース・低炭素食品⑨生物多様性⑩教育⑪コミュニケーション⑫持続可能な調達――の12項目だ。
この12項目の実績を基に、SPL独自のスコアリングシステムで定量的に分析する。Jリーグは2025年度をSPL参画への準備期間と位置付け、各クラブの気候変動対応を促進するため、総額2億4千万円の助成金制度を立ち上げた。
助成金は2026年度以降も続け、3年間で総額11億9000万円を予定する。助成金の分配配分については、順位を参考に決めるという。
■天候が理由で中止した試合数は10年で5倍に
Jリーグのサステナビリティ領域を担当する辻井隆行執行役員は、SPLへの参画について、「好事例を共有できるので、これまでの各クラブの活動を線にして面に変えることができる」と話す。
Jリーグは2030年までにリーグ全体で排出するCO2を50%削減する目標を掲げる。加盟クラブはカーボンニュートラルを掲げ、リユースカップの導入やサステナビリティ関連イベントなどを開いてきた。だが、他クラブとの協働は少なく、活動が点で終わることが多かった。
SPLでは各クラブの気候変動対応に関する強みやストレッチポイントを可視化できる。好事例も共有できるので、リーグ全体で気候変動対応を加速できると、辻井執行役員は期待する。
Jリーグによると、天候が理由で中止した試合数は1996~2017年はシーズン平均で1.86試合だったが、18~24年は9.57試合と約5倍に急増している。「ゲリラ豪雨」による夏場の中止が多く、気候変動への対応は急務だ。
辻井執行役員は、「Jリーグの60クラブ全体で取り組みを加速して、リーグ全体で気候変動に対するメッセージを発信し、ステークホルダーに届けたい」と話した。