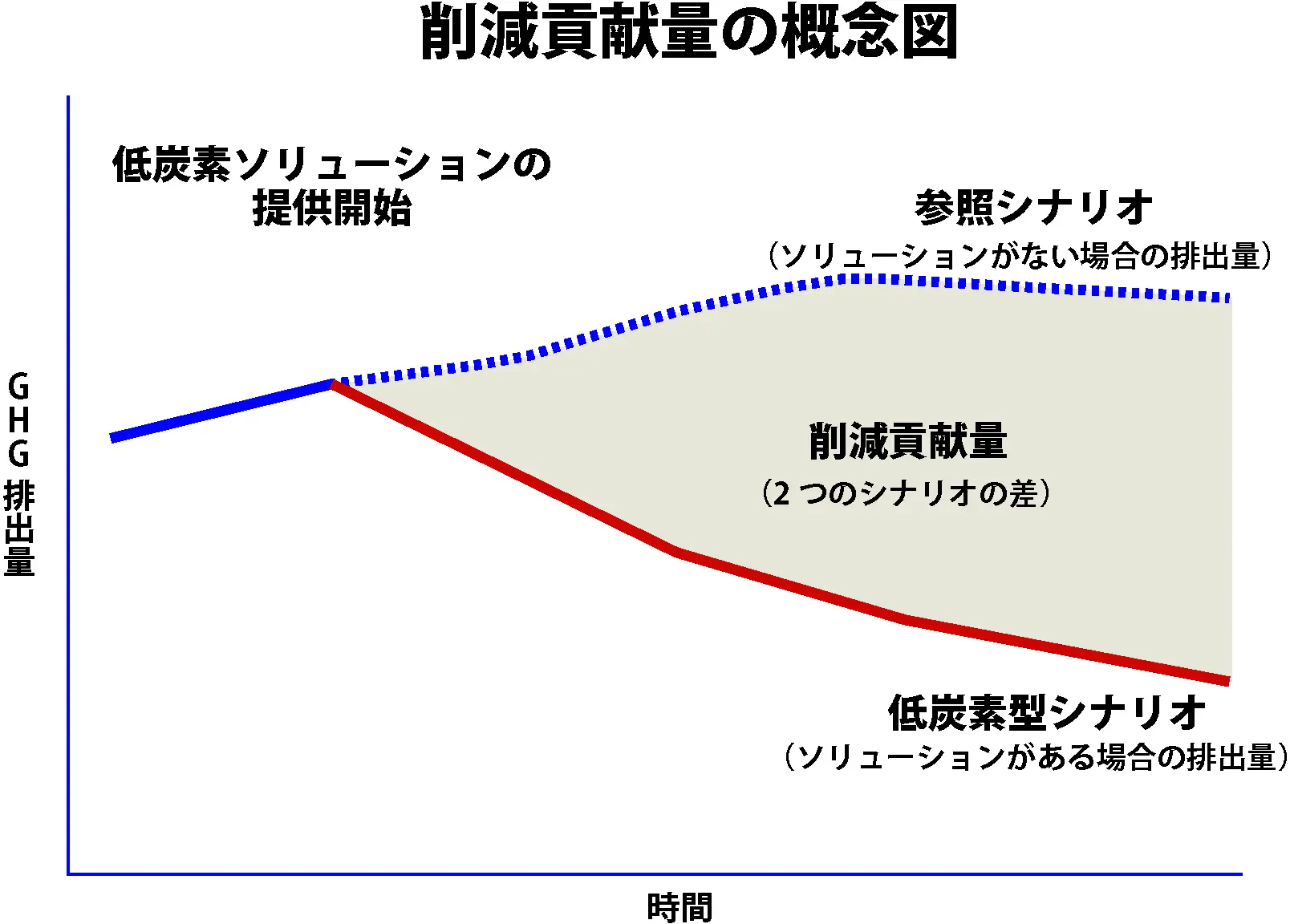記事のポイント
- 丸井グループ の塩田裕子執行役員が登壇し、同社のサステナ経営戦略について講義した
- 「『好き』が駆動する経済」という経営ビジョンのもと、インパクトと利益の両立を目指す
- 塩田役員は、「社会課題の解決と事業戦略を一体で捉えることの重要性」について語った
オルタナは6月18日、サステナ経営塾21期第3回を開いた。第1講には、丸井グループ の塩田裕子執行役員が登壇し、同社のサステナ経営戦略について講義した。同社は「『好き』が駆動する経済」という経営ビジョンのもと、インパクトと利益の両立を目指す。講義レポートの全文は下記の通り。(オルタナ輪番編集長=吉田広子)

■利益と社会課題解決の両立を目指す
丸井グループは、1931年に家具の月賦商として創業し、現在では小売と金融を融合させた独自のビジネスモデルを展開しています。
小売事業では、「マルイ」や「モディ」などの商業施設を、関東を中心に東海・関西・九州にかけて22店舗展開し、年間取扱高は3255億円、年間の入店客数は約1億8810万人に上ります。金融事業では、エポスカードの会員数が790万人を超え、年間のカード取扱高は4兆5305億円に達しています。
丸井グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「人の成長=企業の成長」という経営理念に基づき、事業活動を通じてお客さまの「しあわせ」を共に創ることをミッションに掲げています。
企業として利益を出すことは必須です。株主への責任を果たし、社員の雇用を守るためには稼がなければなりません。しかし、その一方で社会課題解決も重要なミッションです。私たち丸井グループでは、「稼げること」「できること」「したいこと」「ステークホルダーが求めること」のど真ん中にあるものを追求する「インパクト」の考え方を経営の軸に置いています。
社会課題解決企業を目指す丸井グループは、2021年に「インパクト1.0」を発表しました。しかし、最初からうまくいったわけではありません。インパクト目標を掲げることはできても、それをビジネスの中でどう具体化し、実行していくかが大きな課題でした。試行錯誤と学びを重ねながら、現在は3テーマ10項目のインパクトに取り組んでいます。
この過程で、会社の定款も変更しました。1931年の創業以来ほとんど変えてこなかった定款に、「ビジネスを通じて社会課題解決と利益の両立を目指す」という文言を加え、株主の承認を得ました。
これは私たちの決意表明であり、今後も変わらない会社のルールとして位置付けられています。変化の激しい時代において、企業の核となる理念を明確にすることは、持続可能な経営の基盤となります。
(この続きは)
■「インパクト」と「事業戦略」に乖離
■「好き」を軸に、間接的にアプローチする
■資本主義社会の限界と新しい経済の形
■「『好き』を応援するビジネス」の具体例
■「好き」を応援するファイナンシャル・エンパワーメント
■社員の「フロー」状態を高める
■協業を通じたインパクトの創出
■インパクトと利益の二項対立を乗り越える
■2030年に向けたインパクト目標