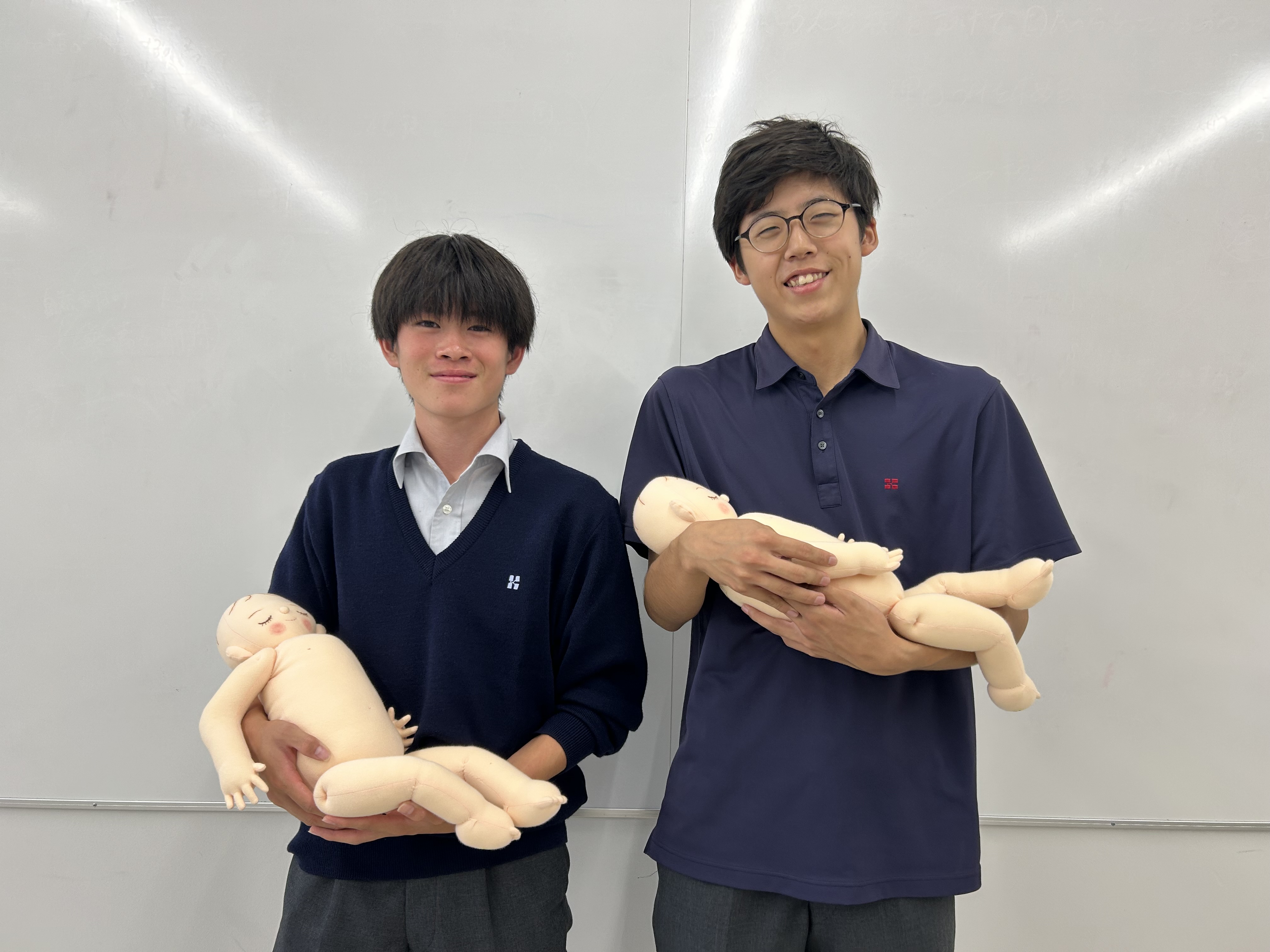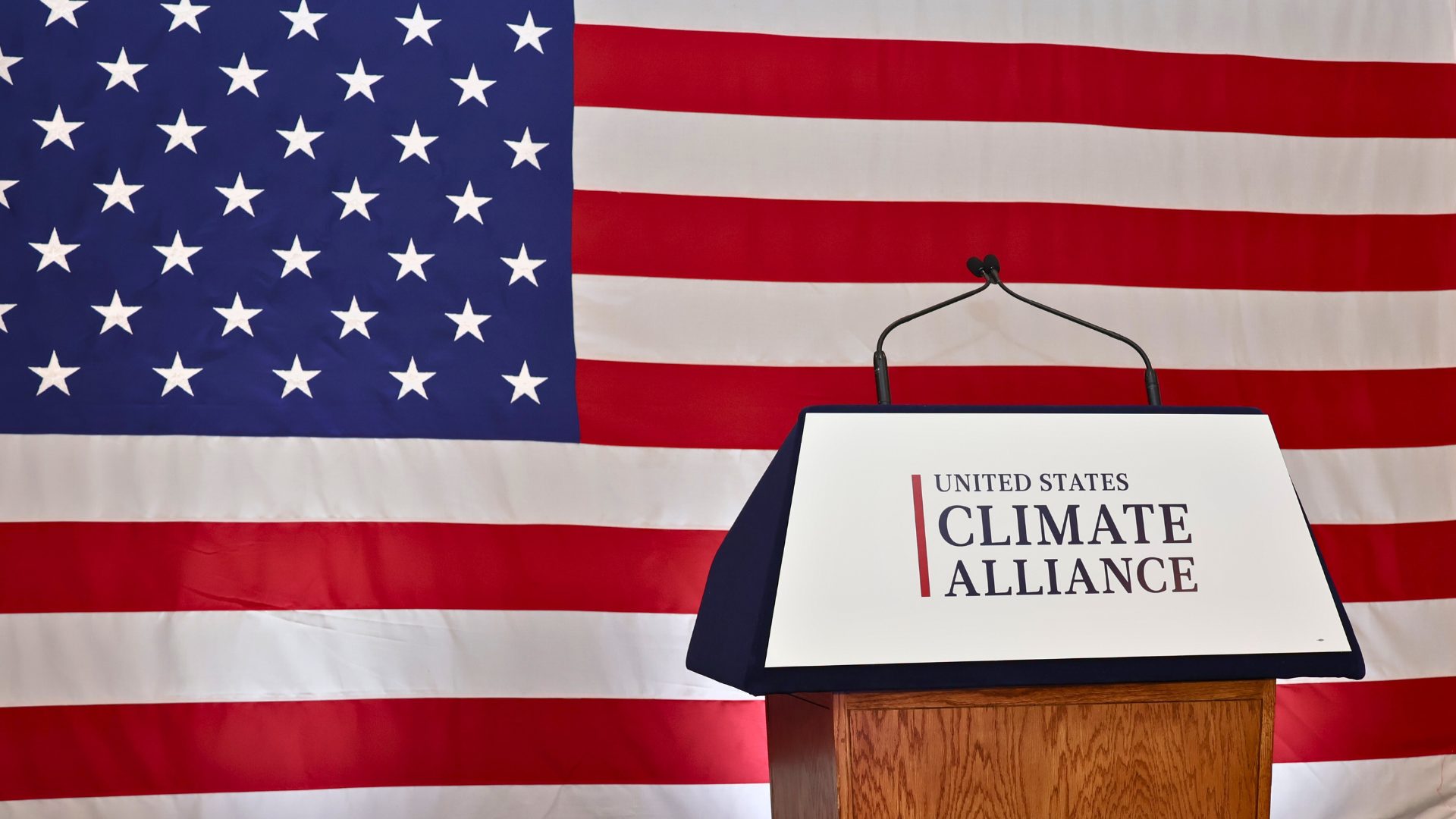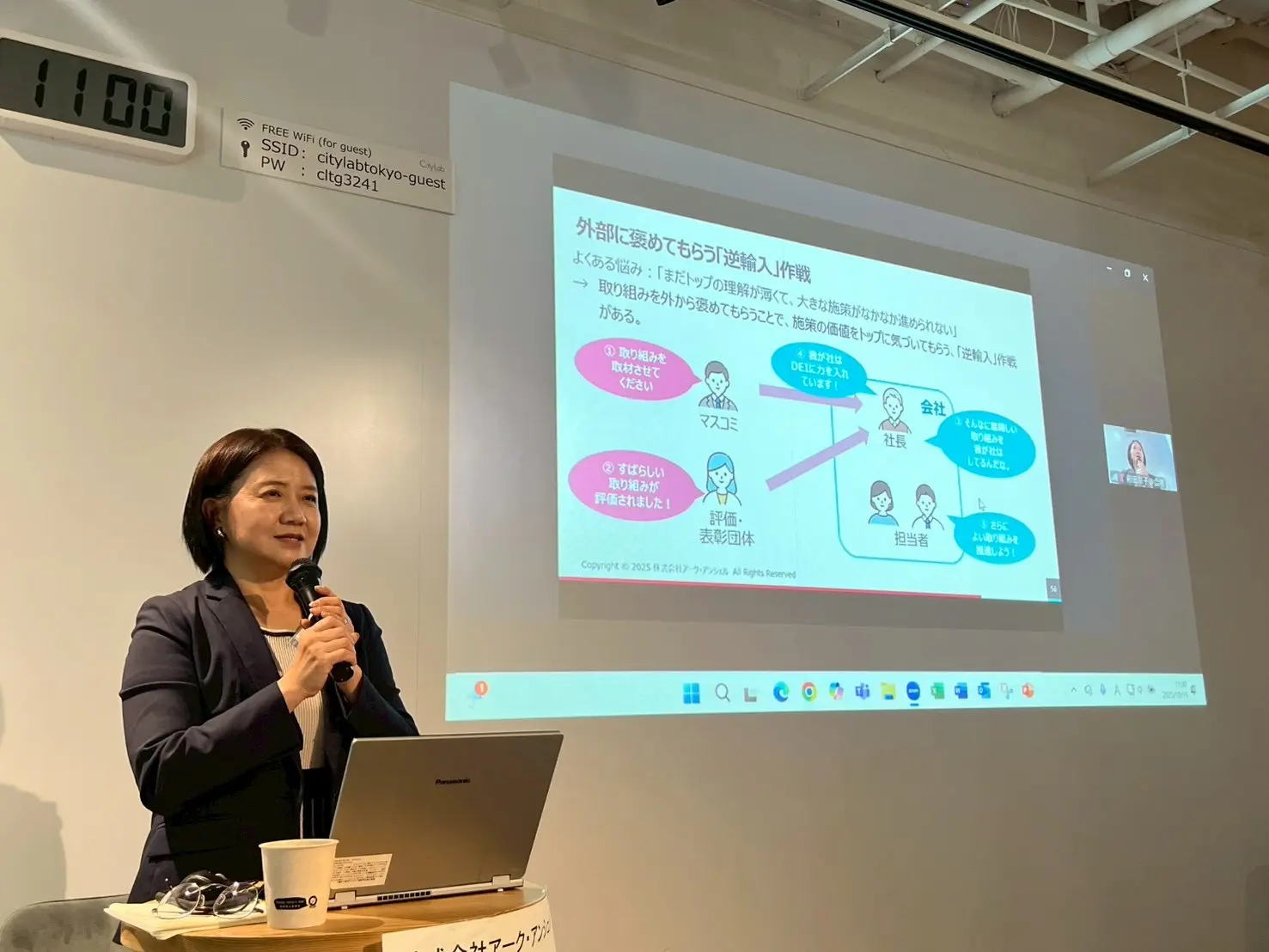生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が10月18日から名古屋市で開かれる。メディアの報道もかなり増えてきたが、生物多様性の論客として知られる足立直樹・レスポンスアビリティ代表は、単一的な報道のあり方に警鐘を鳴らす。
「生物多様性を、日常生活と切り離された特別な問題とするのではなく、日々の生活や事業活動の中に持ち込むこと、生物多様性を『主流化』することが重要だ」と指摘する。足立さんの主張を紹介する。
■ステレオタイプの報道に危惧
COP10の開幕を控えて、マスメディアが生物多様性を取り上げて下さることが多くなって来ました。
ただ、生物多様性が経済に与える影響などをきちんと丁寧に取材・考察している場合もあるのですが、そうした紹介の仕方をしているのはむしろ少数派で、多くはステレオタイプな切り口が目立ちます。
つまり、こんなに多くの生物種が絶滅の危機にあるということだけを強調したり、遺伝子資源から莫大な経済的利益が生まれ、それを巡って 先進国と途上国が対立しているなど、思わず「またか」と言いたくなるような、そんな切り口ばかりが目立ちます。
確かに両方とも重要な点ではあるし、短時間で読者や視聴者に印象づけようとすると、そういう取り上げ方をしたくなる気持ちも分かるのですが、これでは「生物多様性とはそれだけのことだ」という誤った印象を植えつけてしまいます。
多くの一般企業にとって生物多様性が重要なのは、遺伝子資源だけでなく、生物資源全般が、これからの産業と社会を支える持続可能な資源であり、それを確保すること、そして活用することこそ、今後の企業としての命運を決める課題だからです。
生物多様性という大きな問題の全体像をフォローするのは難しいと思いますが、企業人の皆さんにはぜひ産業と社会を支える唯一の持続可能な資源であるという観点から、生物多様性という問題を考えて頂きたいと思います。
■結局、購買行動は変わらなかった
遺伝子資源もそうなのですが、資源としての重要性や、経済的価値や経済メカニズムの話を強調すると、今度はすぐに読者や視聴者の方から反論が来ます。
「生物多様性の重要性はお金には変えられない」「生命そのものが重要なのであって、それをすぐに金銭的価値に結びつけたり、経済問題に矮小化して欲しくない」。
おっしゃる通りだと思いますし、そう言いたい気持ちもよく分かります。それでも敢えて、「本当にそれで良いのですか」とお聞きしたくなります。
なぜなら、これまでいくら声高に「自然は大切だ」、「経済よりも生きものを優先しよう」と主張して来たのに、結局、そうした意見はほとんど通らなかったからです。
それが今の危機的な状況を作って来たのです。そして私たち自身も、ほとんどの場合、自分自身の経済的メリットを優先した行動をとって来ました。
「環境に配慮した商品であれば、少し高くても買いますか?」というアンケートには多くの人がイエスと答えるのに、実際には安い商品の方が売れるのです。
「あなたが買った商品の原料が原因で、熱帯地域で野生生物が絶滅しようとしています」と言われても、ほとんどの人が一瞬顔を曇らせても、結局、購買行動を変えることはないのです。
だとしたら、ただ生物多様性の危機を訴えるのではなく、経済メカニズムを利用して、生物多様性の問題を日々の生活や企業活動にリンクさせた方がよっぽど問題解決につながるのではないでしょうか。
つまり、生物多様性に配慮していない商品や、生物多様性に大きな負荷をかけている商品はより高価になり、きちんと配慮した商品を作る方が儲かるようになれば、誰もが自然と生物多様性の保全に協力するはずです。
■生物多様性を「主流化」しよう
生物多様性を日常生活と切り離された特別の問題とするのではなく、日々の生活や事業活動の中に持ち込むこと、それが生物多様性を「主流化」するということです。
耳慣れない言葉ですが、国際的には”to mainstream”という表現がよく使われていて、これを直訳すると「主流化する」になります。
そして私は、生物多様性を「主流化する」ことこそが、いま世界が目指していることであり、それができて初めて、生物多様性の危機的な現状が改善し、生物資源を活用した持続可能な企業活動も可能になるのだと思います。
これからCOP10に向けてますます増えるであろう生物多様性に関する報道を見ながら、皆さんにはぜひ、どうしたら生物多様性を主流化することができるかを考えて頂けたらと思います。
(オルタナ編集部)













-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)