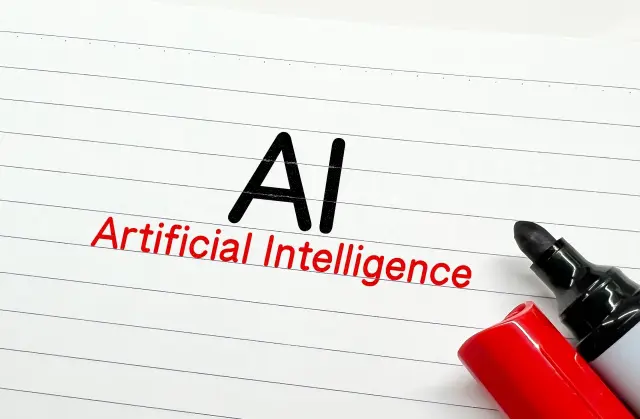■小泉進次郎・衆議院議員インタビュー
小泉進次郎・衆議院議員は、日本政府の「カーボンニュートラル宣言」(2020年10月)を実現しようと菅義偉首相(当時)に働き掛けた。その後、産業界も脱炭素に向けて舵を切り、再エネ比率も順調に増えてきた。しかし、新型コロナやウクライナ戦争、そして石油高騰で、その動きが止まっているようにも見える。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆、写真=川畑 嘉文)

――日本は「2050年カーボンニュートラル」に向けて脱炭素政策を進めてきましたが、ウクライナ戦争が起きたことで、その動きが停滞しているように映ります。
私が環境大臣のときに「2050年までのカーボンニュートラル」を当時の菅義偉首相に働き掛けました。菅首相の決断があったおかげで、産業界の歯車を間違いなく動かせた思っています。
いま考えても、あのとき(2020年10月26日)に日本がカーボンニュートラルへの一歩を踏み出していなかったらと想像すると恐ろしいですね。G7で日本だけ脱炭素を宣言していない国になっていた可能性もあります。
しかし、残念なことに日本はコロナ禍とロシア・ウクライナ危機を受けて、あたかも脱炭素政策の推進がスピードダウンしているように感じることがあります。一方で国際社会はウクライナ危機によって、脱炭素政策の「強度」と「速度」を上げています。
日本は脱炭素に向けてまだまだやるべきことがあります。いまこそ脱炭素を加速させるべきだと強く訴え続けていかないといけません。
■石炭火力の「抑制」が「2050年脱炭素」のきっかけ
――菅義偉さんが所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル宣言」をした当時は産業界や政界からは否定的な意見も少なくありませんでした。宣言できた勝因は何でしたか。
カーボンニュートラル宣言ができたきっかけは、日本政府が石炭火力を抑制する政策に転じたことが大きかった。私が環境大臣の時、2019年12月にスペイン・マドリードで開かれたCOP25(第25回 国連気候変動枠組条約締約国会議)に行きました。
本当はCOP25には、日本の石炭火力の政策を前向きに変換した後で行きたかった。あの時は残念ながら、石炭火力の政策を政府内で調整できませんでした。COP25で「政府内の調整が間に合わなかった」と発言したことは当時批判もされましたが、海外からは「率直だ」という前向きな評価の声をもらいました。
これを契機に、なぜ日本はこれほど石炭火力のことで批判を受けるのか、なぜ小泉はこれだけ石炭火力で批判を受けているのか、こうした報道が増えたことで、一気に国会でも石炭火力抑制に向けた議論が活発になりました。
2020年1月にはベトナムのブンアン2石炭火力事業計画に反対を表明しました。こうした流れによって、2020年7月の石炭火力の「原則輸出支援禁止」という政府の方針変更につながりました。これは安倍政権でのことです。これが前段にあったから菅総理の「カーボンニュートラル宣言」につながりました。
■「菅首相の決断によってしかできない英断だった」
これは、菅首相によって実現した英断です。そう言える理由は、当時は政府内の抵抗も激しく、産業界もカーボンニュートラルに踏み切るだけの前向きな議論をしきれていなかった。日本は積み上げの発想が強いですが、積み上げだけでは「答え」が出ないのがカーボンニュートラルです。
フォアキャスティング(積み上げ)ではなく、バックキャスティング(未来の目標から逆算する考え方)が大事なのに、その理解が当時は進んでいませんでした。そういう意味でも英断です。
菅首相の宣言によって、その後、日本経済新聞は、まるで「日本環境新聞」のように脱炭素に関する報道が一気に増えました。
企業は相次いで再エネへの切り替えに声をあげ、政府は脱炭素政策を強化しました。まさに「歯車が回った」瞬間でした。これこそ、政治の仕事だと思います。

――COP(気候変動枠組み条約締約国会議)25では国際NGOが気候変動対策に後ろ向きな国に与える「化石賞」を受賞しました。相当悔しい思いをしたと聞いています。
化石賞を取ったことに悔しい思いはしていません。化石賞に対しては、日本のメディアは正確な報道をしてほしいです。COP期間中、NGOが毎日1~3位を発表します。つまり、1カ国だけに与えるわけではないのです。そして、化石賞をもらったからと言って、政策が進むわけではないのです。

ただし、「悔しい思いをした」のは事実です。間違いなくカーボンニュートラルの方向に早く踏み出すべきだ、それこそが日本の国益になると確信していたのに、政府内で調整できずにCOP25に参加することになったからです。
早く決断していたら、もっと得られたはずの企業の機会と国家としての利益があったでしょう。早期に宣言できなかったことへの機会損失が、私にとってはすごく悔しい。
■脱炭素先行地域を軸に「100人規模の議連」立ち上げへ
――日本で脱炭素政策を進めていくためのカギは何でしょうか。
さまざまなセクターを巻き込むことです。私は環境政策や気候変動政策は環境省だけで議論するものではないという認識がありました。経済と環境はすでに一体化しています。それに、ロシア・ウクライナ危機で明らかになりましたが、気候変動対策は安全保障対策でもあります。だから、大臣のときに、多様なプレーヤーがかかわってくれるように、産業界やNGO、Z世代などとの対話の機会を持ちました。
一番象徴的だったのが自治体との連携です。政府のカーボンニュートラル宣言への大きな後押しになりました。政府が宣言をする前に、日本の大半の自治体が「ゼロカーボンシティ宣言(2050年までに実質カーボンゼロを目指すこと)」をしていました。これは「中央政府包囲網」になったと思います。
もう一つは、経団連との連携です。経済と環境が一体化した時代に政治・行政と産業界との連携が非常に重要です。これまで環境省と経団連の距離は決して近くなかった。だからこそあえてパートナーシップを結ぼうと働きかけたのです。これがいまサーキュラ―エコノミー(循環経済)を推進する「循環経済パートナーシップ(J4CE)」につながっています。
大臣のときに仕込んだ政策でこれから花開くのが、2030年までに実質カーボンゼロを目指す「脱炭素先行地域」です。公募の結果、4月に26地域を発表しました。最終的には100カ所選定します。
この政策の狙いは、地域の脱炭素化の加速と同時に、環境に関心を持つ議員を増やすことです。先行地域の自治体が選挙区の衆参両議院で議連をつくれば、最終的には100人以上の議連になります。今まで環境や気候変動政策に関心がなかった議員でも、地元が脱炭素先行地域になればきっと関心を持つ。
そうやって、とにかく仲間を増やすことが脱炭素政策を進めるためには重要です。一部の「環境族」だけが環境政策に取り組むという状況を早く脱しなければいけない。自民党から見ていると圧倒的に環境省の「サポーター」が少ないと感じます。
――Z世代との対話も重視しています。
Z世代は気候変動の影響を最も受ける世代ですので、次世代に対する責任があります。それに、脱炭素政策でこれから創出する経済の担い手でもあります。
近頃の若者は政治に悲観して、将来に夢を持てず、あまり多くを期待しないと言われています。それでも、少しでもみんなの声を「聴いて、政策につなげているよ」と伝えたい。もちろん、多勢に無勢で負けるときもありますが、戦っている姿を見せたいと思っています。

■「再エネ最優先の原則」、消えかかったことも
――気候変動に関する国際イニシアティブ「RE100」や「SBT」に加盟する日本企業の数は世界でもトップです。ポテンシャルは高いと思います。
これからの世界の潮流は間違いなく、石炭を含めて「脱化石燃料」です。これを力強く進めていけるかどうか。菅政権で内容を議論した「エネルギー基本計画」の基本的な構造と考え方が、これからの時代の一つの指針になると思います。これまでのエネルギー基本計画基にはなかった「再エネ最優先の原則」を入れたからです。
クリーンエネルギー戦略(温暖化対策を成長戦略につなげる戦略)に向けて、自民党内の提言をまとめる作業の中では、一時期、「再エネ最優先の原則」という言葉が消えかかったときがありました。でもいまは、しっかりとこの原則は共有されています。
日本というエネルギー自給率が極めて低い国(編集部注:11.8%、2018年)は、純国産の電源である再エネを最優先に進めていくべきです。ただし、いまは再エネでは電力需要を十分にまかなえません。足りない量はほかの電源を活用していく。その中でいかに化石燃料を減らしていけるかが問われます。
減らすには、ライフスタイルの様々な場で「脱化石燃料」を進めることが重要です。原油価格の高騰で、毎日当たり前に使っているプラスチック製品の価格が上がり、サントリーは10月1日からペットボトル飲料を約20円値上げすると発表しました。
環境大臣の時に「プラスチック新法」(プラスチック資源循環促進法)をつくりましたが、使い捨てのプラスチックをできる限り減らしていくことが狙いです。そしてそのことが、石炭・石油・天然ガスで多い年で17兆円にも上るような輸入経費を減らしていくことにつながります。脱化石燃料を進めることは、エネルギー問題だけでなく、このようにプラスチックを含めて関係しているという理解を広めないといけません。
■最終処分場の「文献調査」に20億円、「電気料金に跳ね返る」
――エネルギー価格の高騰で「原発再稼働」を求める声が出てきました。原発との向き合い方はどう考えますか。
原発、再エネ、化石燃料と電源構成ごとにコストがどれだけかかっているかを消費者に可視化すべきだと思います。それがイデオロギーの論争に陥らせずに現実的なエネルギー政策を立案するための大前提です。
消費者からすると毎月の電気料金がいくらかかるのか、これが一番気になるところです。よく「再エネは高い」と言われますが、その最大の理由は再エネだけが「賦課金」という形で電気料金の明細に見える化されているからです。
しかし、その「高い」と言われている再エネ賦課金は年間で3兆円です。ピークでも5兆円という試算です。今後5兆円からはピークアウトしていきます。一方で、「安い」と言われる石炭や石油、化石燃料のコストは少ない年で再エネ賦課金の3倍の10兆円、そして、多い年で17兆円、直近ではこれだけ原油が高くなっているので、おそらく20兆円を超すでしょう。
しかし、これは消費者に電気料金としては表示されません。原子力についても同じです。例えば最終処分場の建設をするための「文献調査」がありますが、受け入れた自治体には交付金として20億円が支払われます。この20億円は電気料金に跳ね返ります。福島原発の廃炉費用も一体いくらなのか、これも不明なままです。
これらのことは電気料金に表示されていないため、広く知られていません。
これからはそれぞれの電源がどれだけコストがかかるのかを明確にした上で議論して、国民に理解されるエネルギー政策を考えていくべきです。その方針で、日本の安全保障、安定供給を達成し、かつ、カーボンニュートラルに向かう形でつくらないといけない。
■原発派の議員も「原発コストを明らかにすべき」
――こうした考えは自民党内でどの程度、支持されていますか。
自民党の中では同じ思いを持つ議員が増えています。特に最近の大きな変化として感じたのは、「原発派」と言われていた重鎮の議員が党内で経産省に対して、「コストを全部明らかにすべきだ」と強く訴えだしました。
再エネの調整電源として火力発電などを備えていますが、そのことでどれだけ再エネコストがあるのか、そして、原発の不透明なコストを全部明らかにした上でエネルギー政策を議論すべきだという話が出ました。
私はそれに対して、「私も賛成だ」と言いました。どの電源にどれだけのコストがかかるのか、国民に共有した上で判断をすればいい。それ抜きに再エネだけが賦課金として可視化されていて、しかも「高い」というフェアではない形で議論が進むのはよくない。
コストが明らかになればフェアな議論ができる。その上で立案するエネルギー計画であればイデオロギーの対立は起きない。そこに向かう一歩が進みつつあります。
本格的な議論は参議院選挙後になると思いますが、カーボンプライシング(炭素税や排出量取引など)の具体化を含め、脱炭素政策の行方に注目していてください。




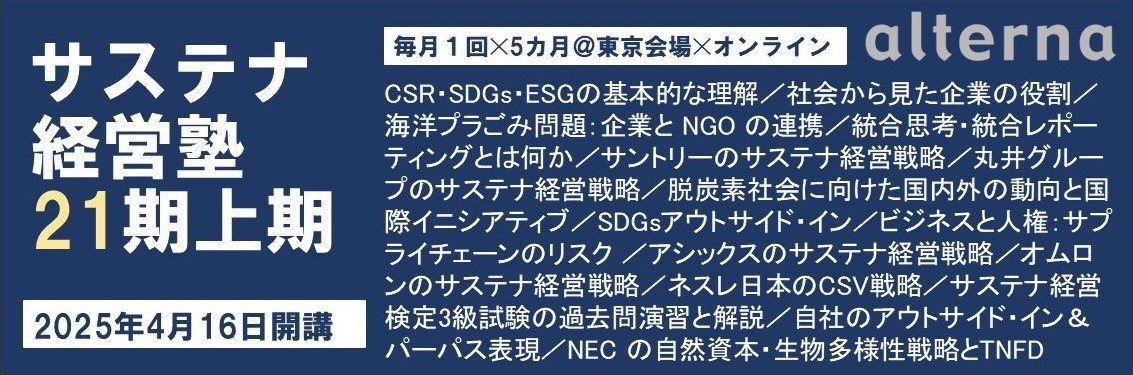




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)