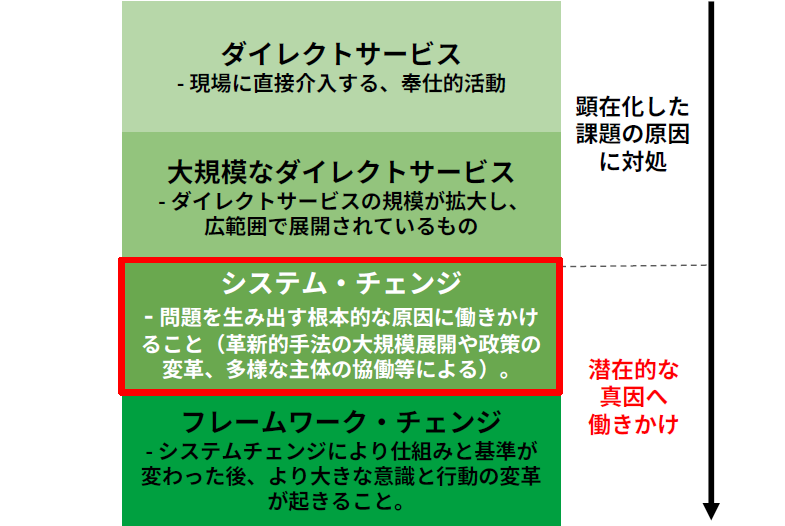記事のポイント
- 円安をカギに、政府はインバウンド熱を高め国内景気を高めようと動く
- 資源に恵まれない日本は輸出立国として外貨を稼いで生きていくしかない
- しかし、日本だけが豊かさを享受するなど、世界が許さなくなってきた
国を挙げてのインバウンド熱が高まっている。海外からの旅行客を増やし、たくさんお金を落としてもらう。それでもって、国内景気を高めようという算段だ。そのカギは円安である。海外からの旅行客からすると、円安はそれだけ日本への旅行がお得となる。宿泊費やショッピングで割安感を、たっぷりと味わえる。(さわかみホールディングス社長=澤上 篤人)

国内のインバウンド受け入れ側も、たくさんお金を落としてもらえるから大歓迎である。それだけ地域経済はじめ国内景気にはプラスとなる。まさに、円安サマサマである。
そもそも日本では円安を待つ風潮が根強い。その典型が、円安イコール株高論である。
円安になると輸出産業には追い風となり、外貨をガッポリ稼げる。企業の業績も向上するからと、株価は上がる。株価が上がれば資産効果が働いて、消費を拡大させ景気にもプラスというわけだ。
日本のような資源に恵まれない国では、加工貿易で外貨を稼いで生きていくしかない。つまり輸出立国でもって豊かになっていく。そのためには、なにがなんでも円安だという論理が、まかり通る。
たしかに、かつて日本が貧しかった頃は、この論理を通せた。そして国民が一丸となって輸出拡大に邁進できた。その努力が実って日本は世界有数の豊かな国になった。
しかし貿易立国も、世界という市場があってこそである。日本だけが突出して豊かさを享受など、世界が許さない。そういった声が高まって、エコノミックアニマルだという批判の集中砲火を浴びることになった。
もうひとつは、円高圧力である。1971年8月のニクソンショックで、戦後ずっと1ドル360円に固定されてきた為替レートが変動相場性に移行し、一気に308円となった。
■円高克服努力が日本を押し上げた
■円安大合唱を機に日本企業の国際競争力が一気に低下
■安売りに走ることがないスイスフラン