記事のポイント
- PRIは日本に投資のサステナビリティ・インパクトの指針の明確化を促した
- レポートで、指針の明確化やガイダンスで投資家のリードなどを提言している
- 執筆者は「取り組みは進んだものの、諸外国に比べ遅れている」と指摘した
PRI(国連責任投資原則)協会などはこのほどレポートを発行し、日本政府に対して投資におけるサステナビリティ・インパクト(以下、サステナ・インパクト)について指針を明確にするよう促した。サステナ・インパクトは、事業活動が人々や地球に与える影響のことだ。レポートは「日本はサステナ・インパクトをもたらす投資への明確な指針がない」と指摘する。レポートの執筆者のひとりは「取り組みは進んだものの、まだ諸外国に比べ遅れている」と指摘した。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)
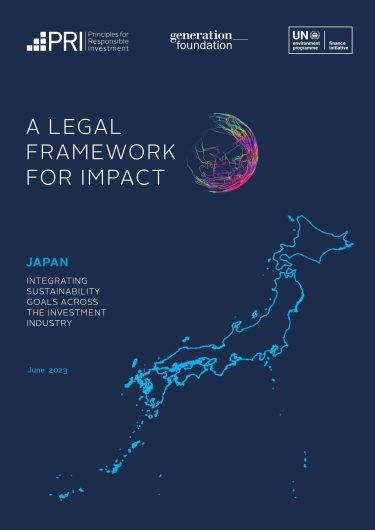
レポートは「インパクトをもたらす投資に関する法的枠組みの日本版ポリシーレポート」。PRI協会(本部: ロンドン)と国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP Fi)、ジェネレーション財団が発行した。
報告書は、投資家が責務を果たす上でサステナ課題に取り組むことについて、法律や規制がどの程度求めているのか、あるいは認めているのかについて包括的に分析した。
この報告書で言われるポジティブなサステナ・インパクトは、パリ協定やSDGsの目標、国連のビジネスと人権に関する指導原則、国際人権章典、ILOの条約など、グローバルなサステナ目標に沿ったものを指す。
■日本は「ESG投資に比べて不十分」だと指摘
報告書では日本のESG投信の取り組みについて評価する。サステナファイナンスや気候変動に伴う経済社会の移行に関して世界的なコンセンサスと歩調を合わせているとする。
その一方で、「日本の規制当局からサステナ・インパクトをもたらす投資に関しては、同様の明確さを示していない」とする。
報告書では「システムレベル・リスクに対処するため、あるいは他の目的を達成するため、意図的にサステナ・インパクトを追求することが受託者責任と整合するか否かは、既存の規制やガイダンスでは十分に明確化されていない」とする。
システムレベル・リスクは、システマティック・リスクとシステミック・リスクを合わせた用語である。前者はたとえば、気候変動の影響による世界経済の成長低下リスクやSDGsの未達成による機会損失などを指す。後者は金融システムの不安定化などだ。
たとえば、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では社会的起業家への投資や官民ファンド等によるインパクト投資の推進を掲げる。
一方で、スチュワードシップ活動やポリシー・エンゲージメントなど、広範なアプローチについては触れていないと指摘する。
レポートではこの傾向の顕著な例として、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)を挙げ、「積立金基本方針及びGPIF中期目標は、いずれもサステナ・インパクトに言及しておらず、インパクトの考え方について指針を一切示していない」とした。
■企業の情報開示やスチュワードシップ・コードも課題に
企業開示やスチュワードシップ・コードも課題として挙げる。
たとえば企業開示では、3月よりジェンダー平等指標などを有報に記載することが義務付けられたが、サステナ・インパクトを開示することは求められていない。
加えて、サステナブルファイナンス・タクソノミーの導入を予定していないことにも触れる。PRIでは2月にレポート「日本におけるサステナブルファイナンス・タクソノミーの必要性」を出していて、日本固有の事情と国際的な規範に適合したタクソノミー開発の必要性を指摘する。
レポートは「このような情報開示の枠組みの限界から、投資家は自主的に企業に開示を求めなければならない状況が続いている」と指摘。「しかし、提供される情報は、限定的で企業間の比較可能性に欠けることが多い」と続けた。
またスチュワードシップ・コードについても「署名機関はその期待事項に対する責任を負わず、監督・レビュー機能がないため、投資家がどの程度準拠しているかを確認することは困難」、「システムレベル・リスクについての言及もない」とする。
これらの課題を指摘したうえで、レポートでは5つの提言を発している。その内容は下記の通り。
1.投資家の義務において、サステナ・インパクト目標の追求を考慮することがどの程度、許可もしくは義務化されているかの明確化
2.既存の規則、基準及びガイダンスを更新することにより、投資家による企業のサステナビリティ関連情報へのアクセスを確保
3.スチュワードシップ・コードの改定や、その他の支援策を通じて、投資家がいつ、どのようにスチュワードシップ活動を通じて、サステナ・インパクトを追求できるかを明確化
4.開示、表示、分類に関する規則やガイダンスを導入することにより、責任投資の主張に関する透明性と市場規律を強化
5.関連するガイダンスを導入することにより、インベストメント・マネージャーとその顧客および受益者との間で、サステナビリティ目的および選好に関するより良いコミュニケーションを確保
■「省庁とのエンゲージメントを図る」
今回のレポートの執筆者の一人である、PRIの大崎一磨ポリシースペシャリストは、日本の取り組みについて「近年加速的に進んでいるものの、まだ諸外国と比べると遅れているところがあるという印象」だと話す。
大崎氏は「先行している国では、投資家の幅広い義務においてサステナ・インパクトがどのように考慮されるべきか、政策レベルのガイダンスが少しずつ出てきています」と指摘する。
今回のレポートが「日本でもこれからこの議論が重要なテーマとして取り上げられていくことが期待される」としたうえで、「関連する省庁には直接レポ―トを送り、今後エンゲージメントを図っていく予定」だという。



































