性加害問題を巡り、ジャニーズ事務所との契約を見直す動きが広がっている。同事務所を非難する過熱報道も続く。一方、「ビジネスと人権」に詳しい、菅原絵美・大阪経済法科大学国際学部教授は「このままでは被害者が声を上げにくくなってしまうのではないか」と危惧する。(オルタナ副編集長=吉田広子)
■「契約解除」で問題は解決するのか

「ジャニーズ事務所との契約を見直すこと自体は理解できるが、果たして、それまでのビジネスを振り返ることなく契約を解除して、問題解決につながっているのか疑問だ。契約を継続することで、取引先企業は変化を促すプレッシャーになることもできた。人権尊重はどうあるべきか、よく考える必要があるのではないか」
こう語るのは、国際人権法を専門とし、「ビジネスと人権」を研究する菅原教授だ。
ジャニーズ事務所は9月7日、記者会見を開き、性加害を事実だと認めた。英BBCが3月にドキュメンタリーを放送して以来、静観していた日本企業だったが、同事務所との契約を見直す方針を相次いで発表した。
一見、国際社会の目を意識した迅速な対応ともいえる。しかし、菅原教授は「いまの状況は、かえって被害者が声を上げにくくなっていないだろうか」と疑問を投げかける。
「声を上げられない、隠れた被害者はまだまだいるはず。特に、年齢が若かったり、知名度が高くなかったりするタレントや元所属タレントは立場が弱い。仕事を失う不安から、言い出せない可能性もある。被害者の声を再び埋もれさせてしまうようなことがあってはならない」(菅原教授)
■ 複数の選択肢を示す「救済のブーケ」が必要
ジャニーズ事務所は9月15日、被害者救済委員会による補償受付窓口を設置したことを発表した。10月2日に記者会見を開き、被害補償の具体的方策や会社の運営体制などについて詳細を発表する予定だ。
菅原教授は、被害者救済にあたり、複数の選択肢を花束のように示す「救済のブーケ」の視点が重要だと話す。「救済のブーケ」は、自社による相談窓口や救済措置に加え、関連企業、国家、NGOなど多様な主体による多様な選択肢を提示するという考え方だ。
「被害を受けた当事者が声を上げやすい仕組みが必要だ。一つの手段だけで、被害者を救済できるわけではない。通報窓口や救済措置を一覧化するなど、当事者にとってアクセスしやすい仕組みを社会全体で考えていかなければならない」(菅原教授)
7~8月に訪日調査を行った国連ビジネスと人権の作業部会は、日本には独立した「国家人権機関」(NHRIs)がないことについて、「深く憂慮し、政府の取り組みに『大きな穴』が開いている」と厳しく指摘した。
そうしたなか、民間団体が自ら動き出す例もある。
例えば、ビジネスと人権対話救済機構(JaCER、東京・千代田)は、「対話救済プラットフォーム」を立ち上げ、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)に基づく苦情処理を受けられる非司法的プラットフォームを提供している。
日本政府は2022年9月、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)に基づき、「人権尊重ガイドライン」を策定。法的拘束力はないものの、人権リスクを特定し、対策や予防策を講じる「人権デューディリジェンス(DD)」は、企業にとって必須の対応だ。
「これまで原材料の調達や労働環境などを中心に人権DDが実施されてきたが、ジャニーズ問題は、広告・宣伝、広報の分野での人権リスクを浮き彫りにした。人権リスクは業種や規模にかかわらず、どの企業も抱えている。企業が本当の意味でどう人権を尊重していくのか、持続可能な未来を描いていくのかが問われている」(菅原教授)



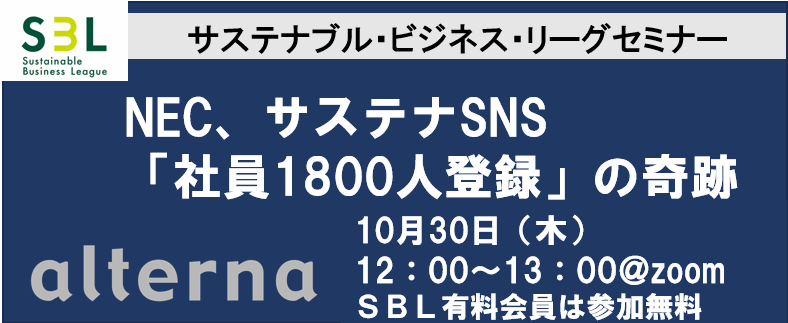







-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)





















