記事のポイント
- 従業員エンゲージメント向上やDEI推進の一環として、ERGに注目が集まっている
- ERGとは、従業員リソースグループの略で、社員が自主的に作るグループだ
- 日立のERGはこのほど当事者の視点を体験する社内イベントを開催した
従業員エンゲージメント向上やDEI(多様性・公正性・包摂性)推進の一環として、従業員による自主的な集まりERG(従業員リソースグループ)に注目が集まっている。中でも、ERG活動が活発な企業の一つが日立グループだ。障がいのある社員のインクルージョン(包摂)を後押しする同社ERGはこのほど、当事者の視点を体験する社内イベントを開催し、社員200人以上が参加した。(辻陽一郎)
ERGとは、「Employee Resource Group(従業員リソースグループ)」の略で、同じ価値観や共通の目的を持つ社員が自主的に作るグループを意味する。
日立グループには、キャリア採用者や若手社員、外国籍従業員など、9つのERGがある。その一つが、「日立インクルーシブなみらいプロジェクト(I-MIRAI)」から発展した、障がいのある社員のインクルージョンを後押しするERGだ。
本ERGは、障がいやアクセシビリティ、インクルージョンについて学ぶ場づくりを目的に発足した。障がいに対するマインドセットを見直し、誰もが平等な機会を得て活躍できる職場や社会を目指して活動している。
本ERGはこのほど社内イベントを開催し、対面とオンラインを合わせて200人以上の社員が参加した。

本ERGのリーダーの伊藤芳浩さんは「3人で始めた活動が今では115人にまで増えた。今日は新しいコミュニケーション方法を学び、職場に持ち帰ってほしい」と呼びかけた。
グループワークでは、「聴覚障がい」「視覚障がい」「発達障がい・ニューロダイバーシティ」に分かれて体験会を実施。聴覚障がいの体験では、PCのスピーカーをオフにし、音声認識の字幕を見ながら、コミュニケーションをとる体験を試みた。
他にも、聞こえない人との対面でのコミュニケーションの際に、スマートフォンなどで字幕を表示したり、筆談やジェスチャーで対応したりする体験、日本手話と日本語対応手話体験なども行われた。
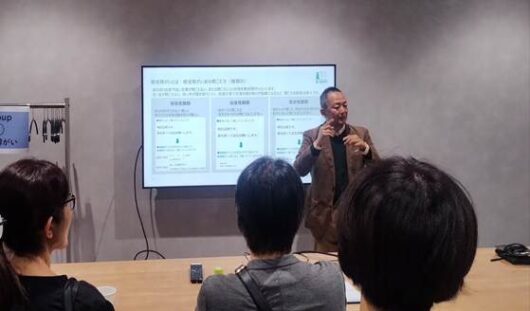
視覚障がいのグループでは、特別なメガネを使用して「見えない」と一口に言っても、人によって見え方が異なるという世界を擬似体験した。白杖を使っている社員の一人からは「よく人にぶつかって白杖が折れることがある。だから、大きな音を出して道を空けてもらうようにしている」という解説もあった。
発達障がい・ニューロダイバーシティのグループでは、発達障がいの特徴である感覚過敏を実際に疑似体験できる映像を視聴。映像を見ることで、パニックになりかける時の感覚を体験することができた。「感覚過敏は見た目に出ないので本人しか気づかない。この映像を通じて自分ごとにしてほしい」という声もあった。
グループワークで体験する以外にも、外部ゲストの講演やパネルディスカッションも行われた。伊藤さんは「障がいがあるなしに関わらず、とにかく繋がればオッケー。それがインクルーシブの心得」と語る。
200人を超える社員がこの日をきっかけにつながることで、誰もが自分らしく働ける職場が広がっていくはずだ。































.jpg)


