環境省はこのほど、G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組に基づく「第3次G20海洋プラスチックごみ対策報告書」の最終版を公表した。国別行動計画の策定や法規制の整備が各国で進んでいる一方、課題としてデータ収集、リサイクルシステムの改善、廃棄物処理や技術革新への経済的援助の欠如が明らかになった。(オルタナ総研フェロー=室井孝之)
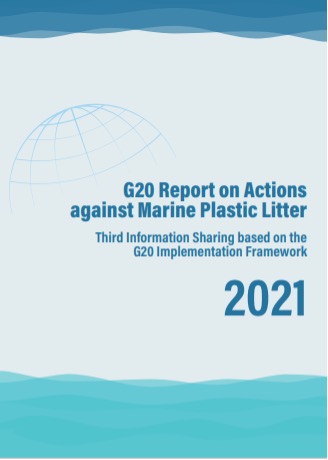
2019年6月G20大阪サミットにおいて、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有された。
報告書は19年10月に第1次、20年9月に第2次が発表され、第3次報告書は本年7月のG20環境大臣会議にあわせて、議長国イタリアの主導、環境省の支援で策定され、この度、最終版が取りまとめられた。
第3次報告書には、42か国と13の国際機関・NGOから情報提供があった。豪州など国家行動計画を策定した国が26か国、2030年までに国全体のリサイクル率を50%に引き上げる目標を設定した米国など取組の進捗を測る指標を設定した国が19カ国だった。
報告書には、マイクロプラスチックの発生抑制・流出抑制・回収に役立つ日本企業の技術・ノウハウを国内外に情報発信した環境省の取り組みが報告された。
その一方、課題として多く挙げられたのが、データ収集、リサイクルシステムの改善、廃棄物処理や技術革新への経済的援助の欠如だった。
第3次報告書に情報提供を行った国と国際機関・NGOは以下のとおり。
G20: 日本、EU、アメリカ、英国、イタリア、インドネシア、オーストラリア、カナダ、韓国、サウジアラビア、中国、ドイツ、トルコ、フランス、メキシコ(15か国)
G20以外:イラク、ウルグアイ、オマーン、オランダ、キリバス、サモア、シンガポール、スペイン、スリランカ、タイ、チリ、ドミニカ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、バングラディッシュ、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブータン、ブルネイ、ミャンマー、モルディブ(27か国)
国際機関・NGO:アジア開発銀行(ADB)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)、エレン・マッカーサー財団、地球環境ファシリティ(GEF)、国際原子力機関(IAEA)、国際資源パネル(IRP)、オーシャン・コンサーバンシー、経済協力開発機構(OECD)、国連環境計画(UNEP)、国連工業開発機関(UNIDO)、世界銀行(WB)、世界経済フォーラム・グローバルプラスチックアクションパートナーシップ(WEF GPAP)


































