■トップインタビュー
記事のポイント
- 日本のカーボンプライシングの本格導入は「30年過ぎ」を見込む
- 2030年に温室効果ガス「46%減」の中間目標は達成できるのか
- GX実行会議の有識者・伊藤元重・東大名誉教授に聞いた
岸田文雄首相は昨年末、GX(グリーン・トランスフォーメーション)化に向けた原案を公開した。カーボンプライシングの本格導入は「2030年過ぎ」、原子力をベースロード電源に位置付け、水素・アンモニア混焼・専焼で、石炭火力を延命——などだ。5月に広島で開くG7で各国の首相に日本のGXをアピールする狙いだ。だが、これでいいのか。原案の作成に関わったGX実行会議有識者の一人である伊藤元重・学習院大学教授(東大名誉教授)に聞いた。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆)
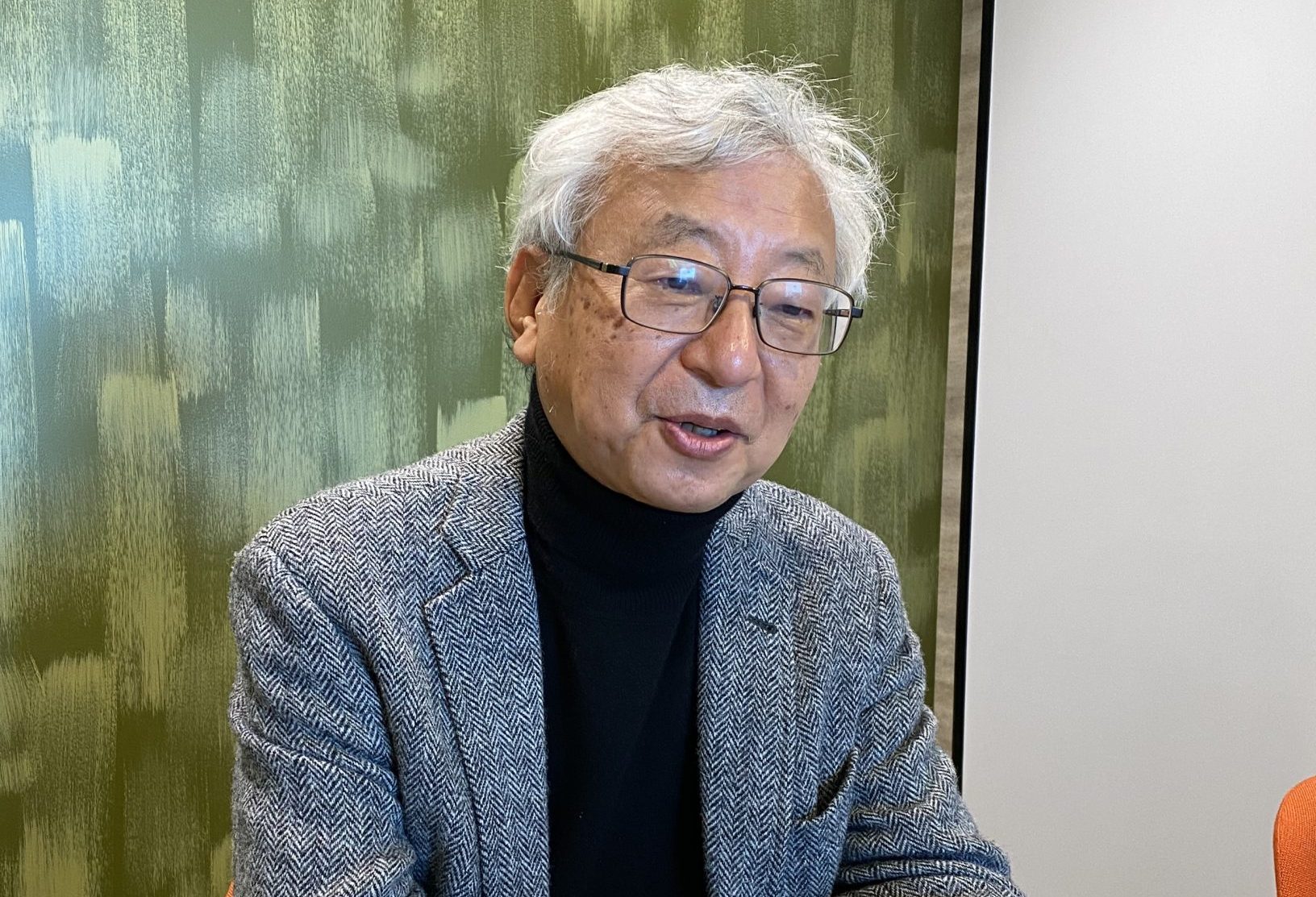
――GX基本方針案ではカーボンプライシングの本格導入を「2030年以降」としています。このペースだと「30年46%減」の中間目標の達成に影響が出るという声もあります。
今回のGX基本方針案は、あらゆる産業のGX(グリーン・トランスフォーメーション)化を促すものだが、特に鉄鋼業のように脱炭素化への代替技術が確立していない産業を主な対象にした。
その根底には、岸田首相が強調する「成長志向型のカーボンプライシング(CP)」という考えがあり、長期的な時間軸でCPの仕組みを構築することがポイントだ。
一方で、電力の需給ひっ迫など足元の課題もある。CPの価格をいきなり諸外国並みの水準に引き上げることで成果が出るならいいが、現実はそうはならない。経済が停滞する恐れもある。
企業には、将来、CPが高くなると見越して今から対応することが重要だ。そうしないと、10年後の社会で企業は生き残れないだろう。
「2030年46%減」という中間目標が目の前に迫っている。30年までに水素エネルギーの生成、貯蔵、輸送などの新技術を確立することはできないだろう。
CCUなどこれらの新技術を30年以降に活用できるように、今から実証実験に取り組む。30年の中間目標には、既存の技術でどうにかしないといけない。
主要企業に関しては、各社が掲げている2030年目標を達成できれば自ずと成果は出る。最終的な目標は、すべての国民・企業がCPを意識した行動変容が起きることだ。
ただし、これは最終目標である。直近10年の勝負はそこではない。今の勝負所は、発電・製造・運輸・住宅など温室効果ガス(GHG)の多排出産業をいかに減らしていけるかだ。
――日本のカーボンプライシングは、電力・ガス・石油元売り・商社を対象にした「炭素に対する賦課金」と「排出量取引」です。「炭素税」は選択肢に入っていません。


































